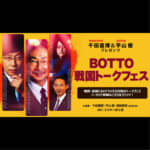現代につながる日本の骨格を創った男・江藤新平 明治維新を全力で駆け抜け、非業の最期を遂げた波乱の人生
4:すべての子どもに教育を! 国民皆教育の導入
廃藩置県が実行されてからわずか4日後の明治4年(1871)7月18日、新たに文部省が設立されたが、当初は長官である文部卿が不在だった。そのため、次官の文部大輔に就任した江藤が実質的なトップとして教育行政を指導した。江藤の就任前、明治政府は旧幕府から昌平学校や開成学校、医学校を引き継ぎ、大学に統合したが、洋学系・国学系・漢学系による三つ巴の対立で、教育行政は機能不全に陥っていた。
江藤は大学を廃止し、教育行政を文部省が統括し、洋学系の南校と医学系の東校を管理下に置いた。これらの学校は後に東京大学の基盤となる。また、江藤は文部省務の大綱を定め、『全国の人民を教育して其の道を得せしむる』という教育方針を掲げ、全ての国民に教育を提供することを目指した。
江藤はわずか17日後に左院に転出し、教育行政は初代文部卿に就任した大木喬任に引き継がれる。明治5年(1872)8月には全国に大学校、中学校、小学校が設置され、身分や性別に関わらず「国民皆学」を目指す学制が発布された。これにより江藤の構想した近代的な学校教育制度が創設されることとなった。
<CHECK POINT>
現代の法曹人材養成の展開にも大きな貢献
司法卿となった江藤は、明治4年(1871)フランス法研究機関として設置された明法寮に教育機関の役割を与え、明治5年に一期生が入校した。授業料は無料で全国から優秀な人材が集まり、後の京都大学や明治大学、関西大学の創設者などを輩出している。教官として招かれたのが、近代法の制定や外交顧問として大きく貢献したギュスターヴ・エミール・ボアソナードである。明法寮は江藤没後の明治8年に司法省法学校となり、明治17年(1884)に文部省に移管され東京大学法学部と発展した。間接的ではあるが、江藤は日本における法曹人材の養成の展開に大きな役割を発揮したといえるだろう。
5:現在の裁判制度は、ここから始まった!
江戸時代の訴訟事務は、奉行所が所管したが、行政・警察と司法が未分離であった。明治5年(1872)、司法卿となった江藤は司法制度改革を推進し、フランスやオランダの制度を参考にした『司法職務定制』を制定。これにより「司法省ハ全国法憲ヲ司リ、各裁判所ヲ統括」として、行政から司法権を独立させ、司法省のもとに司法権を統一するとともに、全国各地に裁判所が置かれた。また、検事を設置し、法憲及び人民の権利保護、犯罪の摘発、裁判の監視を担わせた。さらに「証書人・代書人・代言人職制」を定め、公正証書を作成する証書人(公証人)、契約書作成を担う代書人(司法書士)、法廷で弁論を行う代言人(弁護士)の制度を導入。制度発足当初は、代書人は戸長が兼任し、代言人も資格制度が整備されておらず判事や検事より低く扱われるなどの課題はあったが、江藤の改革により近代的な司法制度の基盤が築かれた。
.jpg)
前列右から3人目が江藤新平・司法省高官とともに(佐賀県立佐賀城本丸歴史館蔵)
■江藤新平の足跡を追いかけて佐賀を知る
佐賀城本丸歴史館
佐賀城は佐賀戦争で本丸御殿と鯱(しゃち)の門、続櫓(つづきやぐら)のみが焼失を免れた。御殿は裁判所や学校に転用後、御座間を除き解体。残された図面や古写真を基に、鍋島直正が再建した当時の本丸御殿主要部が復元され、2004年に県立の博物館施設として開館。幕末維新期の佐賀の歴史を伝えており、「江藤新平コーナー」を常設展示している。
所在地:佐賀県佐賀市城内2-18-1

江藤新平銅像
江藤新平の銅像が立つ神野(こうの)公園は、鍋島直正の別邸「神野のお茶屋」が大正12年に佐賀市へ寄付され公開された。江藤新平の命日の翌日である4月14日には「銅像まつり」が毎年開催される。
所在地:佐賀県佐賀市神園4丁目1-3 「神野公園」内

万部島
龍造寺家兼が永正2年(1505)に、国家安泰、万民安楽を祈願するために法華経一万部読誦を行い、鍋島家の歴代藩主も石塔を奉納した。佐賀戦争で犠牲となった江藤新平や島義勇らを弔う招魂碑が建立され、毎年4月12日には慰霊祭が開催される。
所在地:佐賀県佐賀市水ヶ江1丁目7-9