朝ドラ『あんぱん』昭和2年の日本 その時歴代ヒロインたちは何をしていた?
NHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』がスタート。国民的キャラクター“アンパンマン”を生み出したやなせたかしさんと妻である暢さんの夫婦をモデルに、生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかった2人の人生を描く。第1週は「人間なんてさみしいね」と題し、2人の幼少期から始まった。今回は昭和2年の日本がどのような状況にあったか、そして歴代の朝ドラ主人公たちがどこで何をしていたかを取り上げる。
物語は、昭和2年(1927)から始まる。主人公・朝田のぶは8歳だ。まずはこの頃の日本と世界の時代背景を簡単にみてみよう。
この時期は所謂「戦間期」だ。大正8年(1919)に第一次世界大戦の講和条約であるヴェルサイユ条約が締結されてから約8年が経過し、世界は足並みが揃わないながらも軍縮を進めながら牽制し合っていた。
日本では、第一次世界大戦の終結によって、大戦景気から一転して戦後不況に陥り、さらに大正12年(1923)の関東大震災によって経済的混乱が続いた。そうしたなか、昭和2年に昭和金融恐慌に突入して、社会全体が不況に喘いでいたの頃である。
4月には第1次若槻内閣が総辞職し、田中義一内閣が成立。5月には中華民国山東省に日本が軍を派遣する「第一次山東出兵」があった。まさに戦後の政財界の混乱と、その後の戦争の種が蒔かれつつある中間地点だった。
さて、ではこの頃歴代の朝ドラヒロイン(主人公)たちは何をしていたのだろうか? ここでは比較的近年に放送された作品から、何人かピックアップして取り上げたい。
のぶと年齢が近いのは『ブギウギ』の花田鈴子だ。鈴子は昭和2年時点で12歳。小学校を卒業し、「梅丸少女歌劇団(USK)」に入団した頃とちょうど重なる。さらに、『らんまん』では槙野万太郎が理学博士号を受けるという栄誉が描かれた一方、妻・寿恵子が病に倒れた。愛する妻の名を冠することになる「スエコザサ」もこの年に発見している。
BSで再放送が始まった『チョッちゃん』の初回も、昭和2年からスタートだ。同年12月、北海道・滝川に北山蝶子が帰省するところから物語が始まる。同時期に放送される『あんぱん』と時代背景を重ねながら視聴できそうだ。
先日BS再放送の最終回を迎え、改めて名作と絶賛されている『カーネーション』では、小原糸子が14歳の女学生になり、集金途中に枡谷パッチ店で初めてミシンを見て衝撃を受けて店に通いつめだす時期である。そして、こちらは作中では描かれていないものの、『ごちそうさん』では昭和7年時点で長女・ふ久、長男・泰介、次男・活男が誕生しており、昭和2年は西門め衣子が次男・活男を出産した頃となる。
昭和初期を描いた朝ドラは数多い。例えば近年の朝ドラヒロインを見てみると、昭和2年は『カムカムエヴリバディ』の橘安子が2歳(つまり日本でラジオ放送が始まってから2年)、『虎に翼』の猪爪寅子は13歳、『おちょやん』の竹井千代は21歳になる頃で、翌昭和3年夏に京都の鶴亀撮影所を離れ、新しい喜劇の一座に参加するため道頓堀に戻ってくる時期になる。
激動の昭和という時代を、たくましく生き抜くヒロインたち。のぶにもこの先、第二次世界大戦という大きな悲劇が待ち受けているが、どのように乗り越えていくのだろうか。昭和100年を迎えたこの年に、激動の時代を振り返りながら見守りたい。
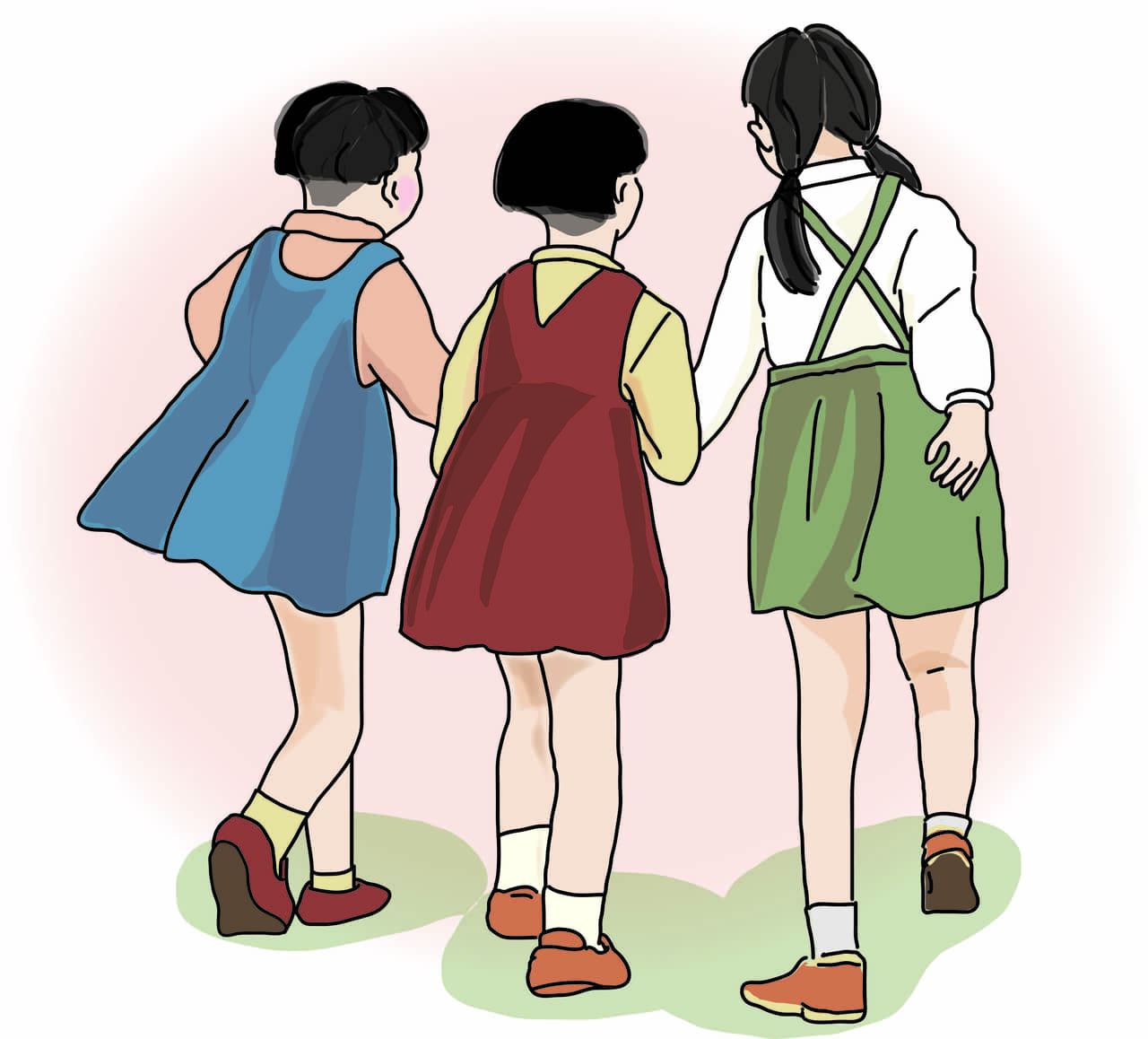
イメージ/イラストAC






