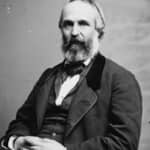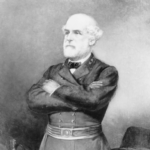「戦略」の概念は19世紀と現在でどう変わったのか? 用語の定義の限界と今後の課題は?
軍事史でみる欧米の歴史と思想
■そもそも「戦略」という概念の定義とは?
戦略の概念は、古くから多義的で曖昧なものであって、悪名高いほど定義が難しいものである。しかしだからこそ、高名な思想家や軍人はその定義を試みつづけてきた。たとえば、19世紀前半のカール・フォン・クラウゼヴィッツの『戦争論』によると、戦略とは、「戦争の目的を達成するために戦闘を使用する」術であった。だが、彼の定義に文字通り従うと、戦闘だけが戦争目的を達成するための手段であり、他に手段がないかのように映る。
クラウゼヴィッツと並び称される同時代のアントワーヌ・アンリ・ジョミニの『戦争概論』によると、戦略とは、「図上で戦争を計画する術であって、作戦地の全体を包含するもの」であった。そして戦術とは、「図上の計画と対照しつつ、現地の特性に応じて、戦場に部隊を配置し、これを行動に移し、かつ地上で戦闘させる術」とされる。ただしこう引用すると、戦略がまず構想され、戦術がその後に考案される印象が強い。だが、実際にそうだろうか。
19世紀後半のヘルムート・フォン・モルトケ(大モルトケ)によると、戦略とは、「所定の目的達成のために軍人に委任された諸手段の実際的適用」であった。また戦略は、「自由で実際的かつ芸術的な活動」で、「臨機応変のシステム」だとも想定される。実務家らしい後半の想定はともかく、前半の定義は、戦略を軍人の専権事項と捉えているように見える。しかし特に、総力戦の第一次世界大戦後、戦略は政治家も考慮すべきものとされてきた。
このような歴史的経緯があって今日では、戦略という用語が、軍事以外のさまざまな領域でも使われるようになっている。たとえば、国家戦略や経営戦略、環境戦略といった言葉がよく見受けられるようになってきた。それゆえ、先の三人のような軍事戦略の定義だけでは不十分に思う向きも増えてきたのではなかろうか。
またたとえ戦略を、軍事・国家戦略の領域に限定しても、今日では、戦争の回避策や抑止策、戦後のより良い平和を構築する方策などを含めて戦略は語られている。仮に国家戦略を「広義の国家目標の達成を図るための方策」だと規定すれば、非強制的な外交や貿易、平時の同盟、人道主義など「非」軍事的なものがそこには数多く含まれよう。
したがって、現代のウィリアムソン・マーレーらは、戦略という用語の定義の限界を指摘し始めている。戦略とはすぐれてプロセスをめぐる問題であり、敵・味方の相互作用であると強調しているのだ。面白いことに元プロボクサーのマイク・タイソンも、「誰にでも計画(プラン)はある。顔面にパンチを食らうまでは」と述べ、戦いの相互作用性と戦略の可変性を明らかに認識していた。石津朋之も、戦略とは「偶然性、不確実性、曖昧性が支配する世界で状況や環境に適応させる恒常的なプロセス」だと綜合的な提案をしている。
では、戦略をめぐる今後の課題としては何があるだろうか。戦略の根拠となるような文書の存在が不可欠なのか、または後付け的なもので充分なのか、という疑問がまずあげられる。次に、最も高次の国家戦略がなければ軍事戦略は存在しえないのか、低次の軍事戦略を積み上げた総体が国家戦略なのか、というさらに大きな検討課題が残されている。後者の課題は、戦略と戦術(たとえば委任戦術)の関係にも該当するであろう。今後、検討してみたい。

ヘルムート・フォン・モルトケ(大モルトケ)はプロイセン参謀総長を務め、ドイツ統一にも貢献した軍人。その功績から「近代ドイツ陸軍の父」とも称される。
ガリカデジタル図書館蔵