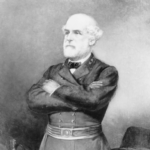幕末の長州藩では洋式の軍事思想がどのように導入されたのか? 大村益次郎の先進的な戦術・戦略研究
軍事史でみる欧米の歴史と思想
■討幕を目指して最新の洋式軍事思想を取り入れた長州藩
19世紀半ば以降の幕末に、討幕派の中心勢力の一つとなった長州藩では、巨大な存在の幕府を倒すため、最新の洋式軍事思想をどのように導入したのであろうか。ここでは、竹本知行の労作『大村益次郎』を主な手がかりに、当時の長州藩において参謀長的存在になった村田蔵六(後に大村益次郎と改名)に注目しよう。なお村田は、早くも1850年代末から、品川の台場に対し、「タクチツク」(英語だとtactics、戦術のこと)だけで「ストラトギイ」(strategy、戦略)ということを知らぬ人がこしらえたものと批判的であった。
このような考えを抱いていた村田は1861年から、長州藩の西洋兵学の中心となった博習堂で、研究・教育に携わることになった。博習堂では、従来の西洋兵学の核であった砲術操典の比重が大幅に減り、野戦造築術などに加え、戦闘術「タクチイキ」や将帥術「ストラトギー」にも焦点が当てられたのである。おそらく正確を期してのことだが、オランダ語など外国語のカタカナ表記が揺れるのは当時からであったのかと興味深い。ただ、タクチイキを「決戦の術を示す」もの、ストラトギーを「政治に渉り(わたり)、…廟算を建て三軍の令を司る」ものとした村田の定義は、現代にも通じる極めて先進的なものであろう。
1865年に三兵学科塾と改称された山口の兵学校でも村田は、自分で翻訳した蘭書をテキストとして、戦術「タクチーキ」や戦略「ストラトギイ」等の教育を施す規則を作成した。三兵学科塾では短期間の下士官教育をめざし、築城術や「答苦知幾(タクチーキの当て字)」、「斯多良的義(ストラトギイの当て字)」、万国史などの教科が段階別に配置された。ここでの教育は先の博習堂の教育を圧縮していたが、万国史を最終段階に置いたところから、戦史教育の重視が博習堂とは異なる特徴だと考えられる。
戦史研究の重視は、1866年の第二次幕長戦争における大村益次郎(改名後)の行動からもうかがわれる。この戦争で彼は、小倉口では積極攻勢をとり、他の三方面では専守防御の持久戦を展開するという防衛戦略をたてていたが、石州口では思わぬ攻勢に出られることになった。そこで島根西部の石州へ出張した大村は、『セバステポル戦争記 三冊』などの戦記ものを携えていたのである。19世紀半ばのクリミア戦争最大の攻囲戦であったセヴァストーポリ要塞の戦いの知見から、石州での城攻めのヒントでも得ていたのであろうか。
とはいえ大村は、先例にならうばかりではなかった。1868年の戊辰戦争中の会津攻略で彼は、「枝葉を断ち根本を枯らす」構想を抱き、会津領攻撃の後回しを考えていた。しかし前線の板垣退助たちは、「根本を撃ち枝葉を枯らす」方針を採り、会津領攻撃に踏み切って結局成功したのである。自らの意に反する作戦であったにもかかわらず、現場の臨機応変の判断による成功を、大村は後に激賞したのであった。なお、同時代のドイツの参謀総長「大モルトケ」によれば、戦略とは「臨機応変のシステム」であった。臨機応変を受容する大村とモルトケの姿勢には、図らずも軍事思想上の共通性があったように思われる。

日本陸軍の創始者、陸軍建設の祖とも評される大村益次郎。靖国神社参道にある大村の銅像は、日本で最初につくられた本格的な西洋式銅像でもある。