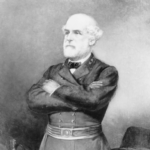南北戦争後の余剰兵器はいかにして幕末の日本で利用されるようになったのか?
軍事史でみる欧米の歴史と思想
■南北戦争終結後、余剰兵器が日本に渡る
1865年にアメリカの南北戦争が終戦した時、北軍の兵力は100万人以上であった。南軍の兵力については正確な資料が残っていないが、アメリカ連合国(南部)の陸軍省の最後の報告によれば、36万人弱であった。しかし戦後、合衆国の陸軍正規軍は規模が大幅に縮小され、1872年には約28,000人、1890年頃までには年平均約25,000人にまで減らされた。正規軍とは別に州軍(National Guard)が存在していたことなどから、武器をもち帰った者がいたとしても、大量の余剰兵器が生じることは避けられなかったのである。
では、アメリカで生じた余剰兵器、とりわけ大量の小銃は、すでに幕末の動乱期を迎えていた日本でどのような環境に直面したのか。1866年の日本では、第二次幕長戦争(第二次長州征伐、四境戦争とも)がおこり、それ以前の戦いとあいまって、新式の洋式銃に対する需要が高まっていた。椎の実型の弾丸を銃口から装填する前装式ライフル銃のミニエー銃やエンフィールド銃が、英仏からまず導入された。そして、この尖頭弾を銃尾から装填するさらに新しい後装式ライフル銃のスナイドル銃やシャスポー銃、ドライゼ銃、アルビニー銃などが、英仏独ベルギーなどのヨーロッパ各国から導入されたのである。
このような新鋭ライフル銃の国際的な市場であった日本に、アメリカからも余剰の小銃がもたらされた。前装式ライフル銃としては、南北戦争で最も広範に使われていたスプリングフィールド銃やレミントン銃が、後装式ライフル銃としてはスタール銃やスペンサー銃、シャープス銃などが日本に渡来していた。ただし、『兵器廠保管参考兵器沿革書』によれば、銃身内部にらせん状の溝(ライフリング)が施されていない滑腔式の旧式レミントン銃も日本で購入されていた。一般に滑腔銃は、ライフル銃より命中精度や射程の点で劣っていたのだが。
幕末の諸藩のなかでも洋式化に最も熱心であったとされる肥前佐賀藩の事例を、『佐賀藩銃砲沿革史』に基づいて具体的に紹介しよう。佐賀藩では1866年に、エンフィールド銃2,400丁余りを二回に分けて購入し、イギリス式に改めていた銃陣に同銃を活用した。だが翌1867年にはスペンサー銃1,000丁を注文し、後にこのうち500丁をレミントン銃に注文替えしたのである。ただ付属品はなかったので、これらは別途注文せねばならなかった。
このスペンサー銃が、1868年の戊辰戦争における秋田方面の戦闘で威力を発揮し、庄内藩の軍勢の前進を押しとどめ、新政府側の危機を救ったのである。しかし同銃の弾薬筒は、尖頭弾を銅管に仕込んだ輸入品で高価かつ補充が困難だったため、一発必中を期して距離を測って発射せねばならなかった。このように最新式のスペンサー銃には、付属品の補給難という課題がつきまとったのだ。とはいえ同銃は、当時のアメリカのA・ハード商会によれば、日本人に最も好ましく思われていた。新製品の功罪が、当時からも垣間見えよう。

佐賀県立佐賀城本丸歴史館には、ゲベール銃、エンフィールド銃、スナイドル銃、スペンサー銃が展示されている。