大河ドラマ『べらぼう』自死に追い込むまで苛烈な取り立てを行う高利貸し “強欲非道”な鳥山検校の裏の顔とは?
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第8回「逆襲の『金々先生』」では、妓楼「松葉屋」の大名跡を継いだ瀬川(演:小芝風花)の元に、新たに鳥山検校(演:市原隼人)という客が来た。目が見えないながらも瀬川の一挙手一投足をまるで見ているかのように言い当て、さらに花魁と新造や禿が楽しむためにと本や装飾品、双六などを差し入れる粋な振る舞いに、瀬川も驚く。さて、鳥山検校とは一体どのような人物なのだろうか。
■金でのし上がって高利貸しで財を築く
そもそも「検校(けんぎょう)」とは、室町以降に盲人(めしい)の最高位の役職だった。江戸時代、幕府は「当道座(とうどうざ)」という組織に盲人が所属することを推奨し、自治的な運営をさせていた。
平曲、地歌三弦、箏曲などの演奏や作曲、もしくは鍼灸や按摩といったスキルを磨いて生業とするのが常だったが、元禄期頃から高利の金貸しが認められるようになると、金融業で財をなす検校も増えた。
そもそも検校になるまでには長い修行期間が必要だが、金銀による盲官位の売買も行われていたという。当道座への加入から検校の位までは73の位階があり、検校になるためには700両以上が必要だったともいわれている。
鳥山検校の詳細な記録は残っていないが、一説には安永2年(1773)に検校の位に就き、やがて当道座の大親分となったという。音楽や鍼灸、按摩などの独占権も有しているだけでなく、高利貸しで莫大な富を築き、大富豪としても知られていた。
一方で、作中でも瀬川付きの新造や禿が口にしたように、高い金利で金を貸し付け、それを時に強引な手段で取り立てることから、検校という立場は忌み嫌われていた。主な借り手は困窮する貧乏な旗本や御家人、財政的に苦しい状況にある大名の家などで、返済できなければ厳しい取り立てにあって土地や財産まで取り上げられたという。屋敷の前で大声で怒鳴ったりすることもあったとか。
さらには家督を乗っ取ろうと画策したり、自死(切腹)寸前まで追い詰めたり、夜逃げするしかない状況まで追い込んだりと、苛烈な取り立てを行っていたらしい。これは鳥山検校に限ったことではなく、江戸時代後期の武士・武陽隠士の随筆『世事見聞録』では「盲人の高利貸しは強欲非道だ」と厳しく非難されているほどだ。
鳥山検校は心配りのできる粋な男として登場したが、瀬川ほどの花魁の揚げ代をサクッと支払えるほどの財力の背景には、悪徳金融業者として疎まれた検校の“裏の顔”も垣間見えるのである。
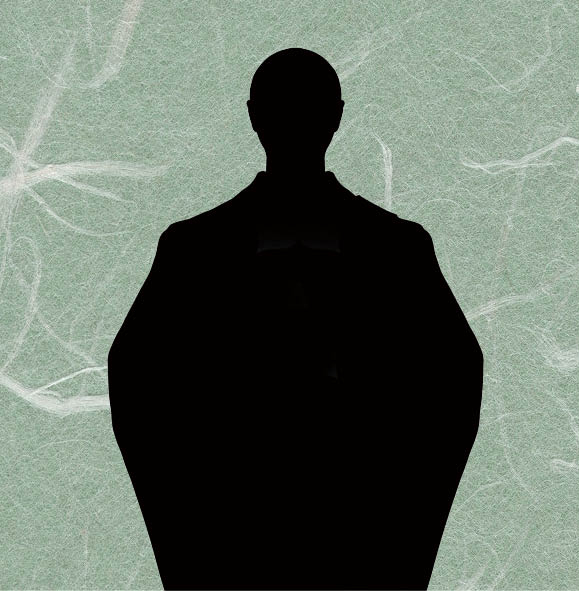
イメージ/イラストAC






