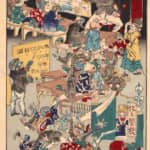世界でも珍しい日本の「火葬率99・9%」 ムスリム土葬墓地はどうなる? 奈良県には「土葬100%」の集落も
世界の中の日本人・海外の反応
大分県日出町でのイスラム教徒の団体による土葬墓地の建設計画や、宮城県知事による土葬墓地の検討を機に、弔い方の多様性について注目が集まっている。日本では火葬率がほぼ100%と世界でもトップクラスの火葬国だが、近代以前は土葬が当たり前で、用地不足を背景に火葬化が進んだという背景がある。改めて、日本における埋葬方法の歴史と伝統について振り返りたい。
■なぜイスラム教徒は土葬にこだわるのか?
火葬でなく自然葬でもない、土葬専用墓地の開設を認めるか否か。昨年より、国東半島の南端にある大分県日出町で大きな論争になっている。
同町の西端にある高平区に土地を購入し、土葬墓地を開設したいと申し出ているのは「別府ムスリム協会」という在日イスラム教徒の団体。日本人との結婚や出稼ぎなどで来日中のイスラム教徒が日本で亡くなった場合、イスラム教の戒律通りに葬られることを求めての働きかけである。
なぜ土葬にこだわるのか。その答えはキリスト教と同じく、一神教に特有の「最後の審判」の教えと関係する。キリスト教の『新約聖書』でもイスラム教の『コーラン』でも、終末の時が到来すると、すべての死者は強制的に蘇り、全知全能の神から天国行きか地獄行きかの審判を下される。
その際、遺体が残っていない者は審判の対象外となってしまう。一神教の信徒とその家族にとっては耐えがたいことなのだ。
■近代以前は土葬が中心で、明治期には「火葬禁止令」も
厚生労働省の統計によれば、2021年度の日本火葬率は99・97パーセントと、世界中を見渡しても突出した数字を記録している。しかし、そんな日本でも、近代以前は土葬が当たり前だった。
仏教では火葬を奨励していたが、遺体を骨だけになるまで焼くのは大変な作業で、時間もかかれば多量の木材も必要となる。明治維新直後の1873年に神仏分離や廃仏思想を背景に「火葬禁止令」が公布されるが、仏教界からの反発と土葬用墓地の絶対的な不足から、わずか2年で撤回とされた経緯もあった。
■土葬用地が学校用地に変わり、学校に「怪談」が生まれた
用地の不足は緊急性のある課題で、1886年の第1次小学校令により初等教育の義務化が定められると、学校用地を確保する必要から、多くの場合、町や村の外れにある墓地が目をつけられた。土葬の遺体は掘り返され、まとめて火葬に。この余波として、夜の学校には怪談がつきものとなる。
火葬場の設置が進んだ大正時代末の1915年でも火葬率は36パーセントで、産業化や都市化にともなう墓地不足を背景に少しずつ火葬が増えていった。半数を超えるようになったのは戦後のことで、1950年には54パーセントを記録。9割を超えたのは1979年以降のことだった。
■奈良県には「土葬100%」の集落も
現代の日本の法律にも土葬を禁止する条文はなく、土葬を禁じるか否かは各自治体の判断に任されている。ルポライターの高橋繁行氏が2021年に刊行した『土葬の村』(講談社現代新書)に詳しいが、現在でも奈良県の柳生の里を中心とした複数の集落に土葬の習慣が残り、土葬率が100パーセントのところもある。
つまり、土葬も日本の伝統文化の一つなわけで、土葬への感情的な反発は多分に無知や偏見によるところが大きい。人口減少が加速する日本では、今後ますますインドネシアやマレーシアなどから働きに来るイスラム教徒が増えるはずだから、日本政府も全国の自治体も、現実的な対応を選択する必要に迫られるだろう。

イメージ