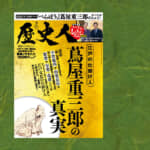【NHK大河『べらぼう』史実で読む】なぜ茶屋務めだった蔦屋重三郎が「江戸一の出版プロデューサー」へと駆け上がっていったのか?
蔦屋重三郎の真実#02
■江戸の世襲社会に挑む! 自身の力で道を切り拓く

吉原の様子を描いた錦絵(『古代江戸繪集』国立国会図書館蔵)
出版界とは無縁な世界で生まれ育ったにもかかわらず、重三郎は敏腕の出版プロデューサーとしてヒット作を連発し、一代にして江戸の出版界をリードする存在となる。そして、編集者や版元の立場に留まることなく、出版界をぎゅうじる地本・書物問屋にまでのしあがったのであり、まさしく江戸のサクセスストーリーを地で行く人物だった。
ヒット作を世に送り出す、いわば裏方として活動しただけではない。文才があった重三郎は狂歌師の顔を持っており、プレーヤーとしても江戸の出版文化を牽引した。
重三郎が出版活動でみせたバイタリティーやチャレンジ精神は他に類をみないと言っても過言ではないが、そのモチベーション、原動力はいったいどこから生まれたのか。
当時は武士の世界だけでなく、町人の世界でも世襲が幅を利かせていた。商人あるいは職人になるにしても、親が商店の主人や職人の棟梁であれば、その業界で有利だったことは否めない。
よって、親とは異なる職種の世界に飛び込んでも成功を収めることはなかなか難しかったのが実情だが、そんな世襲の時代への反発心こそ、重三郎がモチベーションを高めた一番の理由だったのではないか。反骨精神がバイタリティーやチャレンジ精神の源となる。
重三郎は恵まれた家庭環境だったとは言い難い。幼少の頃、両親の離別によって、本人の意思とは関係なく、親元を離れて茶屋の養子となった。
本来ならば、養家の茶屋の主人として飲食業に専念すべきところだったが、あえて異業種の出版界に飛び込んだことに、茶屋の家を継ぐ、すなわち世襲への反発心を見出すことは難しくない。異業種で自分の力を試してみたいと考えたのであり、要するに世襲の壁を打ち破ろうとした。結果からみると、重三郎にとって貸本屋を営んだことが出版界に足を踏み入れるきっかけとなる。
出版界も世襲の論理が幅を利かせた業界であり、問屋あるいは版元にせよ、業界に新規参入した者が、そのポジションを得ることは難しかった。だが、出版の企画となれば話は別である。ヒット作を生み出す企画力は世襲とは関係なく、当人の能力次第であった。
重三郎は貸本業を営むことで培った企画力をもって、閉鎖的な業界に風穴を空けた。ヒット作を連発することで、新規参入ながら出版界をリードする存在となる。さらには、数々のヒット作を世に出した実績を活かして、業界を動かす書物・地本問屋のポジションに就いて、その株を手に入れる。
世襲の時代に対する反骨心が重三郎を突き動かしていたが、吉原という世界で生まれ育ったことも人格形成に大きな影響を与えただろう。
吉原は武士や町人という身分が必ずしも通用しない空間である。金がモノを言う世界だった。重三郎が権力を恐れることなく、時の政治を茶化す黄表紙や、幕府の出版統制令に抵触する洒落本を出版したのは、幕府が定めた身分制の枠外の空間で生まれ育ったことが大きかったのではないか。権力への反骨精神が培われたのである。
そのバイタリティーは、出版界に新規参入した立場であったことと決して無関係ではなかったはずだ。世襲によって受け継いだ身代だ いではない以上、たとえ失敗して身代を失うことになっても、元に戻るだけだった。失敗を恐れずに、新しい企画を次々と世に出したチャレンジ精神は、世襲の立場ではなかったことも影響していた。
吉原で培ったのは、反骨精神だけではない。吉原は文化人の集うサロンとしての顔も持っていたため、彼らと交流を深めることで知的好奇心が刺激されたことも見逃せない。出版プロデューサーとしては、その作品を出版化したいモチベーションが自然と湧き上がってくる。
このように、重三郎のバイタリティーやチャレンジ精神の源となったモチベーションは、世襲への反発と、吉原で生まれ育ったことから生まれたものだったのである。
監修・文/安藤優一郎

photoAC-150x150.jpg)