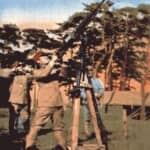堅牢性と良好な作動性を備えた優秀な軽機関銃【96式軽機関銃】
日本軍の小火器~大日本帝国の軍事力の根幹となった「兵士たちの相棒」~【第20回】
かつて一国の軍事力の規模を示す単位として「小銃〇万挺」という言葉が用いられたように、拳銃、小銃、機関銃といった基本的な小火器を国産で賄えるかどうかが、その国が一流国であるか否かの指標でもあった。ゆえに明治維新以降、欧米列強に「追いつけ追い越せ」を目指していた日本は、これら小火器の完全な国産化に力を注いだのだった。

鹵獲した96式軽機関銃を構えるアメリカ海兵隊員。このように本銃は鹵獲使用に耐えられる使い勝手の良さを備えていた。
日本陸軍は、列強に伍(ご)して早い時期から軽機関銃に着目し、11年式軽機関銃を開発・装備した。しかし給弾方式などの設計コンセプトは優れていたものの、工作技術面が追いつかず、実戦では不具合が目立つ不本意な結果となってしまった。
そこで11年式軽機関銃の不具合を是正した、次世代の軽機関銃の開発を1931年に開始。今回の開発は、陸軍小倉造兵廠、東京瓦斯(ガス)電気工業、日本特殊鋼、南部銃製造所の競合試作とされ、最終的には南部銃製造所の試作銃に陸軍側の改良を加えたものが1938年6月に96式軽機関銃として制式化された。
96式軽機関銃は、前作の11年式軽機関銃とは異なり、給弾ホッパに代えてスタンダードな30連箱型弾倉を採用。使用する弾薬も、当初は11年式軽機関銃用に開発された減装38式実包を使用していたが、後の改修によって、普通の38式実包で問題なく作動が維持できるようになった。
このように良好な作動性が得られたため、11年式軽機関銃のような砂塵の多い前線においては「集塵装置」となってしまい、作動不良の原因の一端となっていた塗油装置は備えていない。そもそも塗油装置は、射撃時に撃発後の薬莢が薬室に張り付いて抽筒時に薬莢が断裂し、装填される次弾がそこに突っ込んで作動不良を起こすのを防止することや、弾薬の薬室への送り込みをスムーズにする目的で、11年式軽機関銃に備えられたものだった。
興味深いのは、軽機関銃であるにもかかわらず、96式軽機関銃には銃剣の取り付けが可能なことで、これは世界的にも珍しい。歩兵分隊と行動を共にする銃なので、突撃に際しての配慮と思われる。さらにこの銃剣については、戦後の調査などにより、装着状態で射撃すると命中精度が向上するという報告もある。これはおそらく、銃口部に装着された銃剣がバランス・スタビライザーのような役割をはたすものと考えられている。
38式歩兵銃を基幹とする歩兵分隊に、96式軽機関銃1挺が配されるスタイルは、イギリス軍歩兵分隊がエンフィールド・ライフルを基幹とし、ブレン軽機関銃1挺を配するのと酷似する。後年、イギリス軍では分隊員の1~2名がエンフィールド・ライフルに代えてステン短機関銃を持つようになるが、日本陸軍でも、もし百式短機関銃が配されれば、イギリス軍歩兵分隊と同等の火力を備えることになっただろう。
いずれにしても、96式軽機関銃は兵から好評を得た名銃であった。その生産数は約41000挺(異説あり)と伝えられる。