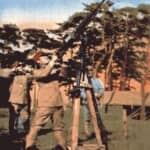国産軽機関銃の試金石の役割を担う【11年式軽機関銃】
日本軍の小火器~大日本帝国の軍事力の根幹となった「兵士たちの相棒」~【第19回】
かつて一国の軍事力の規模を示す単位として「小銃〇万挺」という言葉が用いられたように、拳銃、小銃、機関銃といった基本的な小火器を国産で賄えるかどうかが、その国が一流国であるか否かの指標でもあった。ゆえに明治維新以降、欧米列強に「追いつけ追い越せ」を目指していた日本は、これら小火器の完全な国産化に力を注いだのだった。

11年式軽機関銃。銃の左側面の給弾ホッパにはすでに6個の弾薬クリップが装填されている。銃の左に置かれているのは弾薬箱。
日本陸軍は、諸外国と比べても同等の時期から機関銃の運用について考察を重ねていた。それは、重量があり操作人員も最低4~5名は必要な重機関銃は歩兵と行動をともにする機動性に劣るため、防御用火器として利用。そしてその代わりになる軽量の、操作人員2名程度で運用可能な歩兵と行動をともにできる高い機動性を備えた、いわば軽機関銃というべき機関銃を開発し、中隊レベル以下での機動火力を強化するというものだった。
このような目的のため、第1次世界大戦ではイギリス軍はアメリカで設計されたルイス軽機関銃を、またフランス軍はショーシャ軽機関銃を多数装備した。
そこで日本陸軍も、南部麒次郎に軽機関銃の設計を託した。そして1922年に11年式軽機関銃として制式化の運びとなった。これは世界的にも割と早い軽機関銃の開発・採用と装備化であり、日本陸軍の先進性の象徴となったものの、一方で、大きな問題を起こすことにもなった。
11年式軽機関銃の最大の特徴は、38式歩兵銃用の5連弾薬クリップを、弾倉の代わりに備えられた給弾ホッパに平置きで6個30発装弾できることだ。当初の企図通りこの機構が問題を起こさずに作動してくれれば、歩兵との弾薬の完全互換が達成できたはずだった。
だが、惜しむらくはこの機構は作動トラブルをしばしば起こした。そのうえ、使用する弾薬の38式実包の威力では11年式軽機関銃の作動メカニズムと相性が悪かったため、わざわざ本銃専用に発射薬量を減らした減装弾が供給されるようになり、結局、「歩兵との間での弾薬の完全互換」というコンセプトが逆に悪い結果を生んでしまった。しかもそれだけでなく、38式実包に加えてその減装弾という、弾薬補給上の混乱を招くことにもなった。
また、銃全体の防塵設計も不十分で、中国大陸では給弾機構や機関部に砂塵が入り込んで作動不良や故障の原因となることも少なくなかった。
しかし設計のコンセプトそのものは優れており、それにメカニズムの作動精度が追いつかなかったという悲劇といえる。それでも11年式軽機関銃は、約29000挺が生産されたと伝えられる。
中国大陸の実戦下では、作動不良の頻発が指摘される一方で、経験豊富な銃手が丁寧に手入れした11年式軽機関銃は適切な射撃が可能であり、ともに突撃する小銃手の援護に有効だったというケースも散見される。とはいえ、やはり機構面で不安を抱えた銃であったことは否めないようだ。