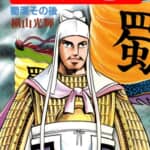曹操の采配ミス?…なぜ夏侯淵は「白地将軍」と呼ばれてしまったのか
ここからはじめる! 三国志入門 第87回
曹操に旗揚げから付き従った血縁の将といえば、夏侯惇(かこうとん)が有名である。今回はその弟分(従弟)にあたる夏侯淵(かこうえん/?~219)の性格、彼が指揮した漢中攻防戦の敗因、白地(はくち)という不名誉なあだ名がついた原因などを史書から紐解きたい。
■曹操の身代わりで罪を被った実直な男

「人形劇 三国志」に登場した夏侯淵。曹操軍の筆頭武将として原作以上に広く活躍する。
正史『三国志』によれば、曹操の妻と夏侯淵の妻は姉妹だったという。夏侯淵には義兄である曹操の身代わりになって罪をかぶり捕まったとか、飢饉のときに死んだ弟の娘を救ったという逸話がある。優しい性格だったようだ。乱世では、このような優しさは命取りにもなろうが、曹操はそんな義弟の性格を愛し、夏侯惇とともに心から信頼して重く用いた。
やがて夏侯淵は立派な将軍に成長。戦法は速戦速攻、機動力を生かした用兵ぶりが有名で「三日で五百里、六日で千里進む」とうたわれた。「弓の名手」とされるのは小説『三国志演義』の話ながら、的に刺さった4本の矢の真ん中を射抜くという、並外れた腕前を披露する場面がある。
やがて、曹操は夏侯淵を長安に駐屯させ、馬超や韓遂をはじめとする西の敵に備えさせた。徐晃・朱霊・張郃(ちょうこう)といった名将も彼の指揮下にあった。羌族(きょうぞく=西域の異民族)と交渉する時、夏侯淵の名を使ったというから、いかに威名が轟いていたかが分かる。
さらに曹操軍が漢中(かんちゅう)を得ると「征西将軍」となり、その要地を守った。かたや兄貴分の夏侯惇は東の揚州方面26軍の総司令官になっていた。東西の守備を、曹操は自分の血族でもある「両夏侯」に任せたというわけだ。ただし、夏侯惇は後方支援が主な任だったのに対し、夏侯淵は最前線で采配をふるう現場指揮官といえた。
曹操はそんな彼に対し「指揮官には勇敢さも必要だが、臆病さも必要だ。常に知略を用いるのだぞ」と忠告していたという。漢中は中原(ちゅうげん)と南の益州を結ぶ重要な位置にあたるため、どこか不安があったのだろうか。そして、その不安は的中してしまう。
■劉備軍に討たれ、漢中を失う!
218年から本格的に開始された劉備軍による漢中攻撃は激しかった。1年もの戦役となり、翌219年には両軍が漢中の定軍山(ていぐんざん)をめぐって激戦を展開。そのさなか、劉備が夜襲を仕掛けてきた。部下の張郃の部隊が苦戦に陥ったと聞き、夏侯淵は兵の半分を割いて救援に向かわせた。

中国・後漢時代 219年勢力図 作成:ミヤイン(参考『中国歴史地図集 第二冊 秦・西漢・東漢時期』中国地図出版社 他)
だが、これは法正を軍師とする劉備軍の巧みな策だった。劉備軍は夏侯淵の本陣が手薄になったと見るや、その陣営を囲む逆茂木(さかもぎ)を焼き討ちにかかる。夏侯淵はこれにおびき出された。陣営を出たところを、高所から攻め降りてきた黄忠(こうちゅう)に襲撃され、あえなく討たれてしまったのである。
かくして漢中は劉備軍の手に落ち、曹操軍は苦境に立った。曹操は絶句したというが、義弟の死より漢中を失ったことに頭を抱えたというべきか。結局、みずから指揮をとる羽目になるが、戦いは長期化。「鶏肋」(けいろく)という言葉を残し、長安へ引きあげざるを得なくなる。さらに同年、荊州が関羽の北上による猛攻にさらされ、あわや遷都まで考えるほどのピンチに陥ったのだ。
かたや劉備軍は歓喜した。過去、常に敗勢を強いられてきた曹操軍を堂々正面から打ち破り、要地を奪ったのだから。劉備は曹操の「魏王」に対抗して「漢中王」を自称。漢中と荊州の両面から曹操を攻めることが可能になった。
また夏侯淵を討った黄忠は征西将軍・後将軍に昇進。「演義」では五虎将にも名を連ねるように後世に勇名を残した。そうした意味でも、夏侯淵の死が時代に与えた影響は大きかったといえよう。
夏侯淵は没後、功臣として称えられるいっぽうで、北宋時代の史書『太平御覧』では「白地将軍」の烙印を押された(淵本非能用兵也,軍中呼為「白地將軍」)。用兵ができない、まぬけな将軍といった意味である。長年の功績が無視され、晩年の失態から汚名を蒙ることになったのは、なんとも哀れだ。生前から散々にこき下ろされた于禁(うきん)よりはマシだろうか。
■夏侯淵の起用は曹操の失策だったのか
「白地」の呼び名はともかく、守りより攻めを得手としたとみられる夏侯淵。その彼に漢中・定軍山を守らせたのは曹操の采配ミスだったのか。野球のように簡単にはいえないが、結論からいえばそうだったともいえる。『魏略』によれば、劉備は夏侯淵を討っても喜ばず、その部下(都督)の張郃を恐れ「一番の大物を討たねば」と言ったという。
実際、夏侯淵の後任となった張郃は、曹操が来着するまでよく持ちこたえた。もし彼に全軍の指揮権があれば違う結果になったのかもしれない。ただ、張郃もその前に張飛との戦いに敗れたことがあったし、確実ともいえない。
荊州方面でも不利となった曹操軍はますます危うくなったが、皮肉なことに同年、劉備軍が荊州(江陵)を失った。関羽が孫権に背後をとられ、あえなく討たれたのである。これで漢中と荊州の二方面から曹操軍を攻めるという劉備の作戦は潰え、曹操軍は幸いにも危機を乗り切った。
劉備軍随一の功臣・関羽の代わりがいなかったように、夏侯淵の代わりが務まる武将も、当時の曹操軍のなかにはいなかったということか。せめて彼を諫められる軍師が陣中にいれば、また別の結果になっただろうか。
余談ながら『人形劇 三国志』に登場する夏侯淵は、とても目立つ存在だった。曹操軍の筆頭格として活躍し、配下のなかで最も出番が多い。中盤では曹操の鎧を着込み、身代わりになって逃げる場面もある。兄貴分の夏侯惇は数話しか出番がないのに対し、異常とも思える活躍ぶりだ。明確な理由は不明だが、ひとつにはカシラの出来栄えがよく、イケメンに設定されたことが大きいようだ。
生前の川本喜八郎氏(人形の製作者)によると、夏侯淵のカシラは、最初は趙雲としてつくったものだったという。当然イケメンなので敵将の筆頭格のカシラにあてがうことになり、夏侯淵に白羽の矢が立ったとみられる。