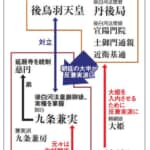打たれ強い不沈艦「大和」型戦艦の傑出した防御力
「戦艦大和」物語 第12回 ~世界最大戦艦の誕生から終焉まで~
戦艦の能力をあらわす指標のひとつに防御力があった。敵の攻撃を受けても簡単には沈まない戦艦「大和」の打たれ強さに迫る。

シブヤン海海戦においてアメリカ軍艦上機群の攻撃後、沈みつつある武蔵。艦首が大きく沈み込んでいるが、左右はほぼ水平を保っているのがわかる。これは魚雷が命中して浸水した舷の反対の舷に注水し、左右のバランスを取った結果である。
世界最大そして世界最強の戦艦である「大和」型の2隻、すなわちネームシップのヤマトと2番艦の「武蔵」は、共に艦上機の攻撃を受けて沈没している。
軍艦の防御力の高さを示す際に「不沈艦」と称することがあるが、ある意味これは理想論に過ぎない。現実には不沈艦など絶対に存在せず、どんなフネでも必ず沈む。だが、沈みにくいように防御力を高めて設計することは可能だ。そして大和型の場合、この点がきわめて優れていた。
それを改めて認識するには、不謹慎かも知れないが、沈没の状況に目を向けてみるとわかりやすい。
大和型の2隻では、まずは武蔵が1944年10月24日のシブヤン海海戦(レイテ沖海戦の1会戦)において、アメリカ軍艦上機群の攻撃を受けて沈没した。
この時、武蔵は爆弾17発、魚雷23本を受けた。そして片舷側だけに浸水して転覆するのを防ぐべく、反対舷注水を実施したため、潜水艦が潜航するように艦首から徐々に沈み込み、最終的には転覆して沈んだ。
一方、大和は1945年4月7日の坊ノ岬沖海戦において、武蔵と同じくアメリカ軍艦上機群の攻撃を受けて沈没した。
この時、大和は爆弾7発、魚雷10本を受けた。そして大傾斜を起こし、転覆直後に主砲弾火薬庫が大爆発を起こしつつ沈んだ。本艦の場合は、武蔵のように反対舷注水がうまくいかなかったので転覆している。
一説では、武蔵撃沈の際に同艦が反対舷注水を実施して最後まで転覆しなかったことから、大和への攻撃では、アメリカ側は片方の舷を集中的に狙って雷撃し転覆を誘ったという説もあるが、この説が事実だと証明するアメリカ側の資料や記録はない。
ところで、フネとは簡単に言ってしまえば、船体の上と中にさまざまな機器を乗せた「うつわ」である。戦艦規模の堅牢な軍艦の場合、単発の艦上機が搭載可能な500kg程度の規模の爆弾では「弾火薬庫への一撃」のような幸運な命中弾が生じなければ撃沈は難しく、魚雷を用いて「うつわ」に孔(あな)を穿(うが)ち、浸水によって沈めるしかない。
この点、武蔵は23本、大和は10本の魚雷を受けている。これを同時代の新戦艦で、やはり航空攻撃を受けて1941年12月10日にマレー沖海戦で沈んだイギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズのケースと比べて見ると、同艦の被雷数は6本で爆弾は1発命中。
また、やはり同時代の新戦艦だが、1941年5月27日にイギリスの戦艦を含む艦隊と交戦して沈没したドイツ戦艦ビスマルクは、約400発の大小の砲弾と、時間をおいて7本の魚雷を受けて沈んだ。
このように、実戦での被雷本数を比較してみると、同時代に就役した各国の新戦艦の中でも、大和型の防御能力が図抜けて秀でていることがおわかりいただけよう。