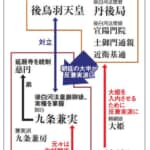戦艦「大和」に群がる敵機を迎え撃つために搭載したフランス生まれの対空機銃
「戦艦大和」物語 第10回 ~世界最大戦艦の誕生から終焉まで~
戦艦の兵装には、主砲、副砲以外にも敵航空機を撃退する対空機銃が存在した。戦艦「大和」に搭載された96式25mm機銃の性能をわかりやすく解説。

海軍航空基地の防空用に陸上に設置された96式25mm機銃連装型。銃座の手前や右側に見える丸い孔の開いた箱状のものが15発入り箱型弾倉。
大艦巨砲主義の申し子ともいえる大和型戦艦だったが、太平洋戦争勃発と同時に、海上戦闘における航空機の有効性が証明され、空母と艦上機を主力とする航空主兵主義が主流となった。そして、すべての艦艇は航空機による空からの爆撃や雷撃で撃沈破され、それは戦艦とて例外ではなかった。
このような状況下、重要となったのが艦を守るための対空火器であり、特に爆撃や雷撃のため近接してくる敵機に対抗する「最後の切り札」となる対空自動火器(機関銃や機関砲)は、なくてはならない艦載兵器となった。
日本海軍は、1934年に何種類かの艦載対空機銃を集めて試験を実施した。その結果、フランスのホチキス社が開発した25mm機銃が優秀なことが判明。そこで海軍は、同社に対して日本向けの小改修を依頼するとともに、ライセンス生産権を取得し、横須賀海軍工廠(こうしょう)造兵部などにおいて国産化する運びとなった。
96式25mm機銃と命名された本銃の毎分発射速度は約150発で、15発入りの箱型弾倉により給弾された。基本形は連装型だが、3連装型と単装型も開発され、日本海軍のあらゆる艦艇に搭載されている。なお、操作要員は3連装型で9名、基本型の連装型で5名、単装型で1名だった。
大和型では、洋上航空戦に対応するべく戦争後期に右舷と左舷に搭載された15.5cm副砲を撤去して対空火器の増備が行われたが、大和の最終的な96式25mm機銃の装備数は、3連装型52基、単装型6挺といわれる。特に大和型では、砲との距離によっては致命的な46cm主砲の爆風を遮る遮風シールドが備えられた3連装型もあったが、同シールドに防弾効果はなかった。
映画『男たちの大和/YAMATO』でも描かれているように、戦艦「大和」最後の戦いとなった坊ノ岬沖(ぼうのみさきおき)海戦では、雲霞(うんか)のごとく襲来するアメリカ軍艦上機を迎え撃ったが、甲板上に露出した銃座に配された操作要員には、爆弾やロケット弾の炸裂、機銃掃射などで多数の死傷者が生じた。
坊ノ岬沖海戦で日本側が撃墜したアメリカ軍艦上機は、わずか5機にすぎない。しかし52機が被弾損傷し、うち5機は空母帰還後に修理不能で廃棄されている。大和が率いた第1遊撃部隊を攻撃したアメリカ艦上機は約300機なので、その約六分の一に命中弾を与えたことになる。
もっとも、命中弾のすべてが25mm機銃弾というわけではないが、操作要員たちはよく訓練されており、かなりの命中精度といえよう。もし日本側がもっと高威力の対空機銃を装備していたら、撃墜機数も増えたに違いない。