技術的限界が露呈した「戦艦大和」装備の高角砲
「戦艦大和」物語 第11回 ~世界最大戦艦の誕生から終焉まで~
戦艦を攻撃してくる敵航空機、この厄介な敵を迎撃するもうひとつの兵器が高角砲であった。その性能と問題点を浮き彫りにする。

40口径89式12.7cm連装高角砲を前後に2基装備した水上機母艦「千歳」の前甲板の様子
大和型戦艦には、当然ながら対空火器が備えられており、そのひとつの「主役」が、前回紹介した96式25mm機銃だった。しかし同機銃は近接対空射撃用のものであり、中距離対空射撃用としては、40口径89式12.7cm高角砲(こうかくほう)が装備されていた。
大和型に装備されたのは、40口径89式12.7cm高角砲A1型改3と称される、連装砲架に載せられたものだった。戦艦「大和」「武蔵」ともに、完成時には同砲を6基12門装備していたが、海戦の様相が洋上航空戦主体となったので、両艦ともに右舷と左舷の15.5cm副砲塔を撤去し、その跡に同高角砲6基12門を増設することとされた。
ところが砲の生産が間に合わず、大和のみ増設され、武蔵では、代わりに25mm3連装機銃を増備したという(異説あり)。
大和型に搭載された40口径89式12.7cm高角砲A1型改3は、主砲射撃時の強烈な爆風を避けるために爆風楯を備えていたが、大和に増設された6基には、爆風楯の生産が間に合わなかった。そこで爆風を受けやすい位置の増設砲架に対して、既存の砲架の爆風楯を移設している。
40口径89式12.7cm高角砲は、カタログ上の値では1門当たり毎分14発が発射できることになっていたが、人力装填のため訓練次第で発射速度は速くも遅くもなり、しかも射撃時間が長くなると、装填手の疲労のせいで装填速度の低下が生じた。
そのため、短時間の値では20発を撃ったケースも存在するが、公式の報告書では毎分12発と評され、現実的には7~8発程度だったようだ。
それよりも問題となったのは、対空時限信管の起爆タイミングの調定であった。敵機までの距離に基づいて信管の起爆時間を設定し、至近で炸裂させてその爆風や破片で撃墜破を目論むのが高角砲だが、信管調定器の精度が今ひとつだったという。
この点、同じ12.7cmのアメリカ海軍の5インチ砲では、大戦中期以降のことだが、敵機に近づくと自動的に起爆するVT信管(レーダー信管)を備えており、信管調定器の必要がなく、かなり誤作動も生じたものの、概ね許容範囲の起爆精度が得られていた。
また、40口径89式12.7cm高角砲A1型改3は砲架の旋回と砲の俯仰のスピードが遅く、高速で飛行する敵機に追随できる迅速性に欠けるという点も、現場では問題視されていた。
かような次第で、大和型における40口径89式12.7cm高角砲A1型改3の評価は、25mm機銃に比べてさほど高いものではなかった。
だがその一方で、大戦後期に建造された松型駆逐艦の主砲に採用された40口径89式12.7cm連装高角砲は、対水上・対空兼用の使い勝手のよい砲という評価を得ている。
つまり同砲への評価は、使い方次第だったようだ。


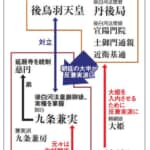

b1my000e0a-e1658738552690-150x150.jpg)

