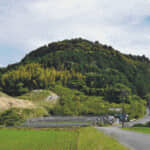伊達政宗に学ぶ「コンプライアンス対応」の成功と失敗
武将に学ぶ「しくじり」と「教訓」 第1回
■コンプライアンス遵守が求められる現代

仙台城跡(仙台市青葉区)にある伊達政宗騎馬像。1964年に2代目の像として建てられたが、今年3月の地震で亀裂が入り、修復中(2022年7月現在)。
昨今、企業はコンプライアンスの遵守を求められています。コンプライアンス対応というと、法令遵守をイメージしがちですが、実際には「社会規範」「社会道徳」や、「ステークホルダーへの配慮」も含まれています。法的な責任だけでなく、倫理観を持った誠実な活動が重要です。
そのため、コンプライアンス違反は企業のブランドイメージを損ない、業績に直接的な影響を与える場合もあります。近年では、試験データの偽装や食品の賞味期限や産地の偽装などが明るみになり、大きなダメージを受けている例が増えています。
戦国時代にも、コンプライアンス違反やその疑いによって所領を削られ、ダメージを受け続けた武将がいました。それは独眼竜(どくがんりゅう)こと伊達政宗(だてまさむね)です。
ただ、政宗の興味深いところは、途中でコンプライアンス遵守の姿勢に切り替えに成功し、評価を逆転させた点です。
■奥州に届いたコンプライアンス遵守の通達
日本の中世にも、コンプライアンスに近い概念は存在していました。鎌倉幕府の「御成敗式目」です。これは武家社会での慣習や道徳をもとに制定されました。武家は、御成敗式目を社会的な規範として行動する事を求められました。
室町時代にはこれを補完する形で「建武式目(けんむしきもく)」が制定されています。応仁の乱以降、中央政権による統制が取れない時期が続きましたが、豊臣秀吉が朝廷の権威を背景として、室町幕府に代わる中央政権をつくりました。そして、全国に私戦停止を求める「惣無事令(そうぶじれい)」を出し、各地の勢力にコンプライアンス遵守を求めます。
それは、奥州一統を目指す伊達政宗の元にも届きました。
伊達家は鎌倉時代から奥州の地頭職をつとめる古い家柄です。政宗は10代で伊達家の家督を継ぎ、父輝宗(てるむね)亡き後、伊達成実(しげざね)や片倉景綱(かたくらかげつな)などの有能な家臣に支えられながら、数々の合戦をくぐり抜けていきます。
1589年には芦名家を「摺上原(すりあげはら)の戦い」で破り、会津地方を手に入れました。政宗は20代という若さで、奥州一統を達成したのです。現在の福島県の大部分と、山形県と宮城県の一部を支配下に置き、石高は家督継承時の72万石から、遂に110万石を超えました。従属している国人の地域も含めると、支配地域は150万石に及んだとも言われています。
ただし、これは豊臣政権が求める私戦停止を無視して達成した成果でした。
結果として政宗の行動は処罰の対象となります。しかも、この件以降も、以下に記載するようなコンプライアンス軽視と取れる行動を続け、所領を削減され、時には移封の対象にもなります。
■伊達政宗のコンプライアンスを軽視した5つの行動
1つめのコンプライアンス軽視は、奥州一統を遂げた抗争です。1587年に豊臣政権から停戦命令が出ていたのを無視し、芦名(あしな)家を破り会津地方を支配下におきました。加えて小田原征伐への参陣にも遅れるという始末です。佐竹家や南部家などが続々と参陣する中、政宗の行動は、秀吉の心証を大きく悪化させました。手に入れた会津は没収され、支配地を72万石にまで減らされました。
2つめは葛西大崎一揆(かさいおおさきいっき)を煽動(せんどう)した疑いです。これはかなり致命的なコンプライアンス違反でした。政宗は葛西大崎地域を手に入れるために、一揆を煽動したと言われています。豊臣秀次や徳川家康までが鎮圧軍に加わる、大規模な一揆になりました。
さらに鎮圧後に、政宗のコンプライアンス違反の証拠として、一揆を煽動したと思われる政宗の手紙が見つかりました。結果、伊達家の本拠地であった米沢は没収され、全盛期の半分ほどの58万石にまで減らされました。しかも、米沢は関東東北の監視役の蒲生(がもう)家、次いで上杉家の支配下とされてしまいます。
3つめは豊臣秀次切腹事件です。政宗は、秀吉から関白を継承した秀次(ひでつぐ)と懇意にしていました。それが元で、秀次の謀反(むほん)疑惑への関与が疑われました。これは秀吉側による言い掛かりだと思いますが、危うく伊予へ転封されそうになりました。これまでのコンプライアンス違反による心証の悪さの影響かもしれません。
4つめは徳川家康との姻戚(いんせき)関係の構築です。大名同士の私婚を禁じた「御掟(おんおきて)」を破り、政宗の長女・五郎八姫(いろはひめ)と家康の六男・松平忠輝(ただてる)を婚約させます。これもコンプライアンス違反として、五奉行などから糾弾されます。ただ、この件は、家康の政治力によって封殺され、事なきを得ました。
5つめは関ヶ原の戦いでの一揆の煽動です。政宗は早くから東軍に通じ、家康から米沢エリアを含め「百万石のお墨付き」をもらっていました。しかし、またしても隣国の南部領での一揆煽動が露見し、百万石の約束も反故となりました。
徳川家としては、政宗によるコンプライアンス違反も織り込み済みだったのかもしれません。処罰する代わりに、西軍として敗けた上杉家が、伊達家の本拠地だった米沢に封じられます。会津には蒲生家が戻ってきて、蒲生家と上杉家の二家が、伊達家を牽制するような形になりました。
■幕府設立のタイミングで方針を大きく転換して貢献
政宗はコンプライアンス軽視の行動を取って領土の拡大に力を注いだものの、結果として家督継承時の72万石にすら戻す事ができませんでした。
その後、徳川幕府による支配体制が確立されてくると、打って変わってコンプライアンス遵守に方向を転換します。幕府の命令による、天下普請にも誠実に応じます。大坂の陣が始まると、これまでのような一揆の煽動を行わず、徳川方として参陣します。その結果、戦後には、伊予宇和島10万石の加増を受けて、合計72万石にまで戻すことに成功しました。
また、徳川幕府による武家法「武家諸法度」にも従順な姿勢で対応していきます。3代将軍家光が大名に参勤交代を命じた際には、政宗自ら進み出て強く賛意を表明し、反対意見を封殺するなど幕府に貢献しました。
政宗は、コンプライアンス遵守に励む事で、家光から厚い信頼を受けるようになり、ついには、徳川御三家以上の待遇を得るようになりました。常に警戒されていた頃とは隔世の感があります。
こうした政宗の事例からは、コンプライアンス対応の重要性が見えてきます。もう少し早く対応していれば……という思いもありますが、江戸幕府設立という節目で切り替えに成功した点は高く評価できます。
体制や組織が新たに一新されるタイミングは、何かを変える絶好の機会であり、政宗はその機にうまく乗じたといえます。そのおかげもあり、伊達家は幕末まで仙台藩として存続できました。
現代でも、大手素材メーカーのデータ偽装によるコンプライアンス違反があり、企業の業績に大きな影響を与えました。これは刑事事件にまで発展し、企業イメージを大きく悪化させ、社名の変更にまで至りました。このメーカーはデータ偽装事件の前にも、政宗のように何度かコンプライアンス違反を起こしています。始めの違反の時に真摯に対応していれば、歴史ある社名も残せていたかもしれません。
今も昔も変わらず、コンプライアンス遵守は組織の永続性にとって重要な要素といえます。