江戸の若い女性から武士までが虜に! 「焼き芋」はなぜ幅広い客層に受けたのか?
江戸っ子に愛されたファーストフード 第6回 「焼き芋」
江戸時代中期、飢饉対策で全国に普及したサツマイモ。甘味を持つこの素材を使ったおやつ「焼き芋」は瞬く間に江戸中を席巻した。誕生秘話から売り方まで、その人気の秘密に迫る!

雪の江戸を描いており、画面右側に〇やきという看板が出ている。この看板に十三里と書かれているはさつまいもが「九里(栗)より(四里)うまい十三里」といわれていたから。十三里は当時さつまいもの名産地として名高かった川越への江戸からの距離だ。 「名所江戸百景 びくにはし雪中」国立国会図書館蔵
毎年のように、新しいスイーツが出てきて、ブームになっているが、江戸時代に今のような人気のスイーツはあったのだろうか? 実は、砂糖を使った菓子が一般に広まったのは江戸時代だったので、当然スイーツはあった。砂糖は、正倉院に記録があるほど古くから中国から入ってきていたが、当時は調味料としてではなく、長い間身分の高い人だけが口にできる薬として扱われていた。
それが、戦国時代、ヨーロッパの文化とともに金平糖やカステラなど砂糖を使用した菓子が日本に伝わると、織田信長など当時の権力者たちはその甘美な味に魅了されたようだ。彼らの思想とは合いれない部分のあるキリスト教が伝播するというリスクを知りながらも、彼らがヨーロッパとの交易を完全に禁止できなかったのは、砂糖の魅力に勝てなかったことも大きかったからだろう。
その後、薩摩が大坂で国産の黒砂糖を販売するようになって、これを使用した菓子が一般に広まっていく。この頃になると、砂糖の代金として金、銀、銅が国外に流出することが問題となり、8代将軍徳川吉宗が砂糖の国産化に向けて注力。すぐに結果は出なかったが、讃岐で和三盆と呼ばれている砂糖が誕生するに至ったのだ。
と、なると一番人気があったスイーツは、砂糖をたっぷりと使ったヨーロッパ生まれの南蛮菓子なのだろうか? それとも砂糖入りの餡が入った饅頭などの和菓子なのだろうか? 一番人気は好むと好まざるを得ず、現代を生きる日本人ならば一度は口にしたことがあるはずだ。子供頃、遠足で行ったと時に食べたという人もいるだろう。最近ではスーパーやコンビニエンスストアでも買うことができる。
江戸時代にも各町境に設けられた木戸番をする番所で販売していたので気軽に購入することができた。こうした番所には本来であれば町役人たちが詰めていなければならないのだが、人を金で雇い代わりに番をさせていたのだ。賃金が安いため、番所で雑貨などを売ることが黙認されていた。ここでの人気商品が焼き芋だったのだ。シーズンには朝6時ごろから焼き始めて午後10時ぐらいまで客が途切れることがないほどだったという。当時も焼き芋に使われた芋はサツマイモだった。
サツマイモは17世紀ごろ日本に伝わったとされているが、なかなか広まらなかった。しかし、享保の飢饉の時、青木昆陽(あおきこんよう)という学者がやせた土地でも栽培可能なサツマイモのすばらしさを説き、8代将軍徳川吉宗が、幕府の小石川御薬園(現小石川植物園)内で栽培させた。その後種芋が全国に配られて、寛政年間(1789~1801)ころに庶民のおやつとして人気が高まったとされる。最初は蒸かしイモだったのが、江戸神田の甚兵衛橋で「原の焼き芋」として売り出したのが焼き芋の始まりで、江戸では「〇焼き」や「八里半」と看板に書くことがあった。〇焼きはイモを切らずに丸のまま焼くこと。八里半はスイーツの材料として人気が高い栗(九里)に似た味ということを表している。
スイーツというと女性が大好きというイメージが強いが、甘い物に目がないという男性に意外と多い。江戸時代にも当然おり、江戸に単身赴任中の藩士が朝食代わりに前の日に買った焼き芋を食べたという記録も残っている。




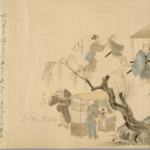
-150x150.png)
