江戸グルメを代表する「うなぎ」は なぜ当時も高級食材だったのか?
江戸っ子に愛されたファーストフード 第5回 「うなぎ」
「寿司」、「蕎麦」、「天ぷら」とともに江戸4大名物であった「うなぎ」だが、その実態は江戸の庶民たちが気軽に楽しめる食材ではなかった。高級食材「うなぎ」をめぐる裏事情を紹介する。

店先でうなぎをさばく人の奥に岡持と思われる容器が置かれているので、この店では店内で飲食させるのではなく、店頭での販売と出前専門店だったようだ。「職人盡繪詞. 第2軸」国立国会図書館蔵
天丼、牛丼、かつ丼、親子丼、海鮮丼など、様々な丼があるが、では、最初の丼物とされているものは何だろうか。
丼物の魅力はなんといってもごはんとおかずが一緒に食べられることで、忙しい時にも簡単に栄養のある食事を採ることができる。丼が生まれたのは、忙しいのにもかかわらずおいしいものを食べようとした人のアイデアだった。
大久保今助という人が文化年間(1804~1818)に、考案したといわれている。大久保今助は、常陸(現茨城県)の農民であったが、江戸に出て水戸藩御用達として財を成し、歌舞伎の興行主となったが、忙しくて食事に出かける時間がなかったので、うなぎを芝居小屋に出前させた。しかし、うなぎだけでは運んでいるうちに冷めてしまう。冷めてしまっては、うなぎはあまりおいしくない。そこで、温かいご飯と一緒に注文することを思いついた。うなぎが冷めないようにするためうなぎをごはんの間に入れたのだ。うな丼という呼び方は明治になってからのもので、江戸時代はうなぎ飯やどんぶりといい、うな重も江戸時代にはなかった。
このうなぎ飯はよほどおいしかったのだろう、あっという間に上方まで伝わったという。もっとも大久保今助だけでなく、当時の人たちがうなぎ好きであったことも大きな要因になっているだろう。ただし、江戸で名のある高級店ではそのブライトが許さなかったのだろうか、いくら人気があってもうなぎ飯を出さなかったという。
ところで、「江戸前」というと現代人は九分九厘「すし」を思い浮かべることだろう。江戸(現東京)のおひざ元の海で獲れた魚を使った握りずしという意味だ。実は、江戸前=すしとなったのは明治以降のこと。江戸時代には江戸前はうなぎを指す言葉であった。うなぎは、古くから食べられていて、奈良時代の歌人大伴家持(おおとものやかもち)が知人に勧めたという記録が残っている。当初はぶつ切りにして食べていたが、やがて、上方で蒲焼が発明されると江戸でも作られるようになるが、上方は腹開き、江戸では背開きで、これは今でも変わらない。
うなぎの蒲焼が夏の土用に食べられるようなったのは、平賀源内という今でいうマルチタレントのような人が知り合いのうなぎ屋にたのまれて「本日、土用丑の日」というキャッチコピーを考えてからという。ちょうどこのころからうなぎを「江戸前」と呼ぶようになったとそうだから、同じ時期にうなぎの人気が出て来たのかもしれない。この「江戸前」のうなぎはどこでとれたものを指しているのかは、諸説あるが、現在の品川から深川にかけて取れたものというのが一般的なようだ。ここ以外でとれたうなぎは「旅うなぎ」といってワンランク落ちるものとされていた。現在でも四国の四万十川でとれた天然うなぎや、養殖ものでも静岡の浜名湖産は、ブランドものとして人気が高いのと同じようなあつかいなのだろう。
最近は様々な要因からうなぎは簡単に口にできる値段ではなくなった。江戸時代もうなぎ飯は一般的な店で1杯64文(約1920円)と気軽に食べられる値段ではなく、うなぎ飯を出さないような高級店ではもっとうなぎは高かったそうだ。このため庶民はもっぱら屋台で売っている1串16文(約480円)を買っていたという。



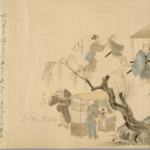
-150x150.png)

