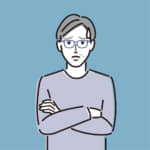朝ドラ『ばけばけ』不遇の幼少期、差別と偏見に晒された結婚生活、そして日本へ…… 小泉八雲とはどんな人物か?
NHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』は、第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」が放送中。主人公・松野トキ(演:髙石あかり)は、しじみ売りをして家系を助ける日々。ある日、レフカダ・ヘブン(演:トミー・バストウ)が英語教師として松江にやって来る。日本文化に興味津々のヘブンと、それに振り回される錦織友一(演:吉沢亮)の追いかけっこに、トキも巻き込まれ……という展開だ。さて、どこか陰のある雰囲気のヘブンだが、モデルとなった小泉八雲もまた、幼年期から苦労の多い人生を送っていた。
■家庭環境に恵まれず、苦労の連続だった前半生
小泉八雲は、本名を「パトリック・ラフカディオ・ハーン」という。1850年に、イオニア諸島合衆国(現在はギリシャ領)のレフカダ島で誕生した。父親はアイルランド人、母親はギリシャ人という生まれだったが、4歳の時に両親が離婚。八雲は両親と離れて、父方の大叔母にあたるブレナン婦人に引き取られた。婦人は大富豪で、厳格なカトリック。そのため幼少期は厳しく教育され、その反動でカトリックへの反発心が芽生えたからか、ケルト神話や土着信仰に対する感受性の豊かさを発揮するようになったといわれている。
16歳の時に、遊具が左目にぶつかった事故によって失明。その翌年、17歳の時には養ってくれていたブレナン婦人が破産して経済的に困窮するという不運に見舞われる。このまま一生を終えるわけにはいかないと一念発起した八雲は、19歳になった年に移民船に乗り込んでアメリカへ渡った。1869年(明治2年)のことである。ちなみに、この前年、1868年(慶応4年)に、後に妻となるセツさんが誕生している。2人は18歳差だった。
渡米した八雲は、その後新聞社でジャーナリストになり、ペンで生計を立てていく。多岐に渡るジャンルの記事を執筆し、その文章は高く評価された。1874年、24歳の時に最初の結婚をしたものの、妻となる女性が黒人のルーツを持ち、当時現地では法的には認められない結婚だったことから、正式に受理された記録はないという。それほど愛した女性ではあったが、差別や偏見に晒された2人の結婚生活は約3年で終わりを迎えた。
離婚後、ニューオーリンズに移り住んだ八雲は、やはりジャーナリスト・文筆家として着実に実績を積み重ね、高く評価されるようになっていった。この頃にはクレオール文化やブードゥー教に興味を持っていたようである。
日本との縁をつないだきっかけの1つが、1884年にニューオーリンズで開催された万国博覧会だ。そこで日本文化に触れ、興味を持ったという。さらに、八雲が生涯尊敬し続けた女性ジャーナリスト、エリザベス・ビスランドが自身の日本での旅行体験を熱弁したことで、来日を決意したとされる。なお、来日の動機として、英訳された『古事記』を通じて関心を持ったという説もある。
1890年、横浜港に到着し日本の地を踏んだ八雲だが、その直後にトラブルによって新聞社との契約を破棄。しばらくは横浜で過ごしていたが、万国博覧会で知り合っていた服部一三の斡旋もあって、島根県の中学校で英語教師としての職を得て松江に移住することになった。
ここまで振り返っても、まさに波乱万丈の人生であり、恵まれなかった家庭環境や偏見に晒された結婚生活によって孤独感を深めていたことは想像に難くない。それでもペンで自身の道を切り拓き、人並み外れた好奇心と感受性の豊かさで新たな世界へ足を踏み入れた心の強さに改めて感服してしまうのだ。
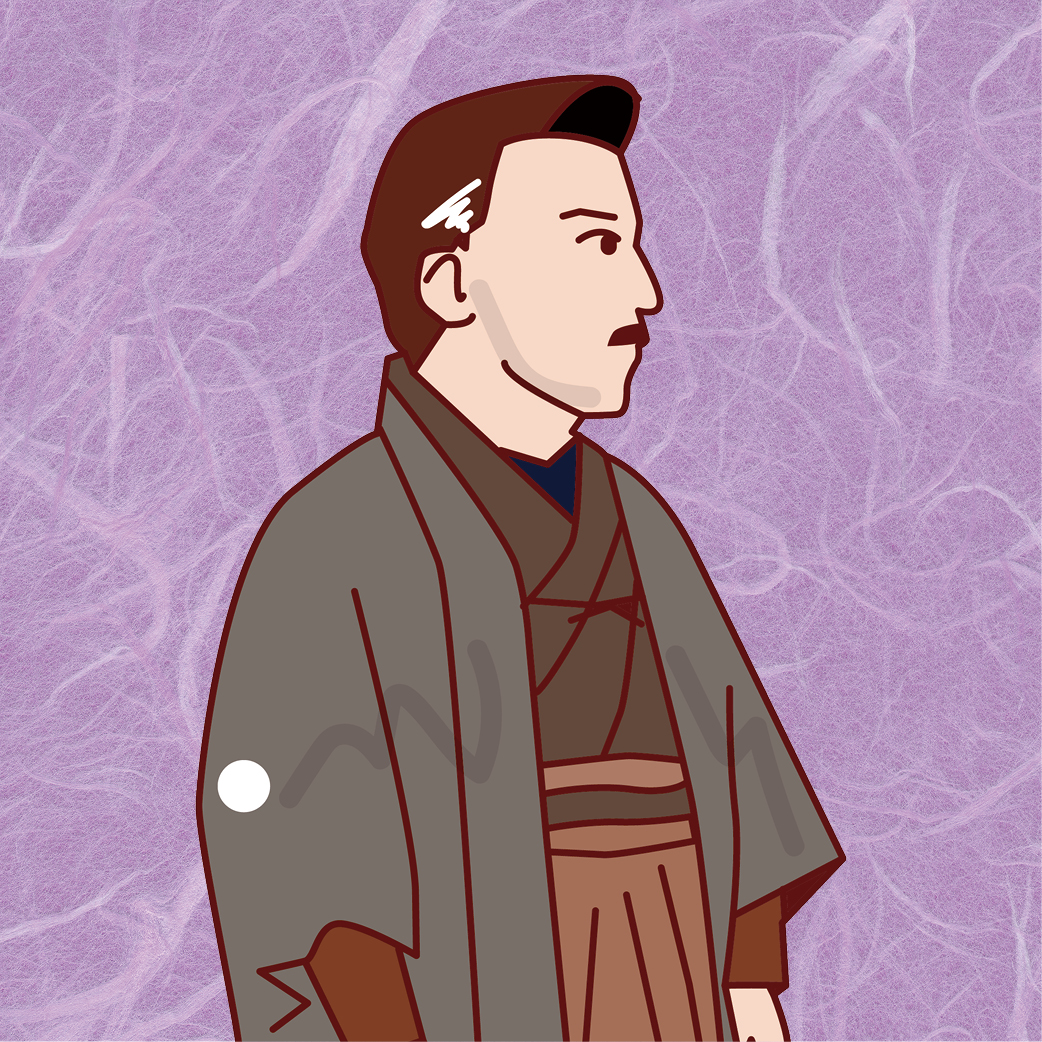
イメージ/イラストAC
<参考>
■「連続テレビ小説 ばけばけ Part1」(NHK出版)
■「小泉セツ 八雲と「怪談」を作り上げたばけばけの物語」(三才ブックス)