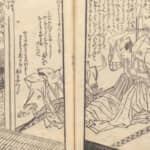田沼意次への「重すぎる罰」とは? 徹底した「田沼排除」の残酷さ
大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第34回「ありがた山とかたじけ茄子」が放送された。ついに老中首座に就いた松平定信(井上祐貴)のもとで、幕府による厳しい統制が始まろうとしていた。蔦重(演:横浜流星)は田沼意次(演:渡辺謙)を訪ね、意次の名を汚すことになったとしても「書をもって世に抗う」ことへの決意を語る。立場は違えど“より豊かな世”を目指してきた2人は手をとりあって言葉を交わした。作中では意次に処分が言い渡される場面があったが、意次にはあまりにも過酷な罰が待ち受けていた。
■松平定信が政治のトップに立って追罰をくだす
度重なる天災による被害や飢饉、そしてタイミングが悪すぎた全国御用金令などによる政治責任を取る形で、田沼意次は老中辞職に追い込まれた。最大の庇護者であった10代将軍・家治の死もまた、意次失脚のきっかけのひとつとなった。
意次は自分の息子や娘を通じて姻戚関係による地盤強化を図っていたが、それも瓦解。元田沼派の面々は手のひらを返して意次との縁を断った。
ここにきて意次に対して厳罰を下すよう動いたのは、徳川御三家だった。御三家は幕閣に対して「幕政混乱を招いた意次に政治責任をとらせること」を求めた。老中辞職だけでなく、さらに重い罰を与えようというのだ。
そして天明6年(1786)閏10月、意次に対して2万石の没収と謹慎が申し付けられた。これによって意次は3万7千石に減封されることになった。しかし同年12月には謹慎も解かれている。11代将軍・家斉は元々意次の働きもあって次期将軍に擁立された背景もあったし、この頃には甥の意致が御側御用取次という役職にも就いていた。意次は翌天明7年(1787)の年賀の式で江戸城にあがり、家斉にも拝謁している。この時点では非常に厳しい状況であってもまだ復権の道は閉ざされていなかった。
ところが、意次への執拗な「罰」は終わらなかったのである。
世にいう「天明の打ちこわし」を経て、天明7年(1787)6月に松平定信が老中に就任。しかも御三家や一橋家の治済(将軍家斉の父)という強力な後ろ盾を得て、いきなり老中首座となったのである。これをもって“松平定信政権”が成立したと言っていいだろう。
敵対していた松平定信が政治のトップに立った以上、意次へのさらなる罰は避けられない状況になった。この時には先述の甥・意致も御側御用取次の職を免じられていた。そして同年10月にはさらに所領2万7千石の没収、隠居、下屋敷での蟄居謹慎が命じられたのである。「在職中の不正」がその理由だった。これによって意次の所領は1万石まで減る。ギリギリ「大名」を名乗れるレベルだ。しかし今回は「隠居」を命じられたことで、幕政への復帰の道は完全に断たれた。
意次が隠居するに伴い、家督は孫の意明(亡くなった息子・意知の長男)が継ぐ。相良城も取り上げられ、所領は陸奥国信夫郡及び越後国頸城郡で1万石とされた。減封かつ転封処分ということになる。田沼家は城持ち大名ですらなくなってしまったのだった。ここまで執拗に処罰を下したのは、やはり田沼政権に対する不満やストレスを発散させたいという思惑が大きいだろう。世間は“悪徳政治家”田沼意次を憎悪し、若くて優れた藩政を為してきた松平定信(しかも徳川家の血筋)に期待した。叩けば叩くほど、「田沼の世の終わり」を見せつけることができ、新政権への期待感を煽ることができた。それだけ江戸城にも、江戸の町にも、田沼政権への不満が溜まっていたのである。
天明8年(1788)正月から、田沼家の成功の象徴だった相良城の取り壊しが始まった。そして意次は同年7月、70歳でこの世を去った。蟄居謹慎処分が解かれないままの、失意のうちでの死だった。

イラストAC
<参考>
■安藤優一郎『田沼意次 汚名を着せられた変革者』(日経ビジネス文庫)