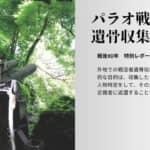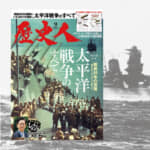【お盆の謎】ご先祖さまの霊を導く「灯籠」と「盆提灯」
夏の伝統風習「お盆」を知る! 【第2回】
今週からお盆のシーズンに突入! 家族での帰省や行楽で、全国各地が賑わう時期でもある。日本の伝統的な風習であるお盆は、そもそもどのような目的でいつ頃からはじまったのか? 墓前の灯籠(とうろう)、送り火、盆おどり、精霊流しなど、お盆にまつわる行事、地域や宗派ごとの相違点、タブーもふくめて、意外に知らないお盆の謎をわかりやすく解説する。
■仏前に灯明をともし、祖先の霊を供養した平安貴族

盆棚(精進棚)に並んだお花、お供えもの、盆提灯、灯籠
先祖供養の行事でもあるお盆には、ご先祖さまや故人の霊が迷わず家に戻ってこられるように、初日に迎え火を、最終日に送り火を焚く。ご先祖さまの霊をお迎えするのが迎え火、お盆が終わり、再びあの世へお送りするのが送り火の役割だ。さらに迎え火・送り火には、故人の冥福を祈り、感謝の気持ちを表す供養の意味もこめられている。
迎え火・送り火の起源は不明だが、平安時代には盂蘭盆(うらぼん)の法要で、貴族たちが仏前に灯明(とうみょう)をともし祖先の霊を供養していたと考えられている。鎌倉・室町時代には仏教が広まり、精霊を迎え供養し送り出すという、現在のお盆に近い考え方が定着した。
迎え火は、お盆の初日である8月13日の夕方、自宅の玄関先や墓地の入り口などで、焙烙(ほうろく)と呼ばれる素焼きのお皿の上でオガラ(麻の幹)を折って積み重ね、燃やして先祖の霊を迎える。迎え火の種火は、お墓参りの際、お墓やお寺でおこした火を自宅に持ち帰り、その火を使って迎え火を焚いた。オガラとは、古くから清浄な植物として考えられてきた麻の皮をはいだあとに残る芯の部分のことだ。
■現在の住宅事情が「灯籠」や「提灯」を後押し
現在の住宅事情では、玄関先やベランダで実際に火を焚くことは難しく、その代わりとして灯籠や提灯が迎え火・送り火の役割となった。ご先祖さまの霊は、子孫たちが用意した灯籠や提灯の明かりを目印に、懐かしい自宅に帰ってくるのだ。昔は灯りが贅沢品だったので、提灯や提灯飾りは極上のお供え物であり、たくさん用意できるほど供養になるとされた。
お盆の灯籠や提灯は、一般的には、お盆がはじまる13〜16日まで飾るのだが、地域や宗派によって異なる場合がある。また、宗派を問わず新盆(初盆)の時だけは、白紋天(しろもんてん)と呼ばれる白提灯を飾る。この白提灯には、故人の魂を清浄無垢の白で迎えるという意味が込められているのだ。白紋天は、お盆が終わったらお寺などでお焚き上げをする。地域によっては、初盆(新盆)を迎えた家に親戚や故人と親しかった人が盆提灯を贈る習慣がある。
8月16日の夕方には、再び迎え火を焚いた同じ場所で、焙烙にオガラを折って積み重ね、火をつけて燃やし、送り火としてご先祖さまの霊を送り出す。お見送りをした後は、ご先祖様がこの世に未練をのこさないよう、お盆飾りはその日の内に片付けるとも言われた。京都の「大文字焼き」や長崎の「精霊流し(しょうりょうながし)」は、ご先祖様の霊を送り出す送り火の意味を持っているのだ。