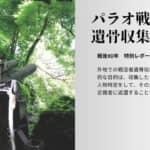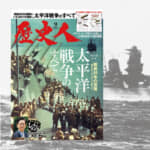【お盆の謎】その起源、目的、準備、進め方とは?
夏の伝統風習「お盆」を知る! 【第1回】
今週からお盆のシーズンに突入! 家族での帰省や行楽で、全国各地が賑わう時期でもある。日本の伝統的な風習であるお盆は、そもそもどのような目的でいつ頃からはじまったのか? 墓前の灯籠(とうろう)、送り火、盆おどり、精霊流しなど、お盆にまつわる行事、地域や宗派ごとの相違点、タブーもふくめて、意外に知らないお盆の謎をわかりやすく解説する。
■先祖崇拝と仏教が融合し「お盆」が誕生

京都の伝統行事・大文字焼き。五山の送り火とも呼ばれる
お盆とは、死後の世界にいらっしゃるご先祖さまや亡くなった故人をお迎えし、感謝を伝える期間である。自宅で迎え火を焚いてお迎えし、仏壇周りの盆かざりやお供え、お墓参りなどのご供養を行うのが一般的だ。日本では古くから祖先の霊をまつる習慣があり、これが中国から伝来した仏教と融合して、お盆の習慣となった。
一般的なお盆の期間は8月13〜16日。地方によっては7月中旬ごろ、8月中旬〜9月上旬に実施するところもある。これは地域によって重視する暦が異なるからであり、明治時代以前の採用されていた太陰暦では7月15日前後、明治以降は新暦の8月15日前後に行われるようになった。
お盆という言葉は、仏教における「盂蘭盆会(うらぼんえ)」、または「盂蘭盆(うらぼん)」を略した言葉とされる。言葉の由来は、その昔、釈迦(仏教の開祖)の弟子の母親が餓鬼道(がきどう)に落ちた際、釈迦の教えにしたがって高僧たちに食べ物や飲み物をふるまい、その施しによる功徳(くどく)が母親を救ったところからはじめられたものとされる。
日本にお盆が伝わったのは7世紀頃とされ(諸説あり)、当初は朝廷が営む供養として位置づけられていた。仏教形式によるお盆の法要がはじめて営まれたのは、斉明天皇の頃の657年とされる(諸説あり)。
■江戸時代になり庶民にも定着
お盆が民間に普及しはじめたのは、鎌倉時代に入ってからとされ、その後、室町時代には送り火の風習が浸透。江戸時代に入るとお盆は庶民にも定着し、僧侶たちが家々をまわってお経をあげるようになった。
お盆の時期には、家族揃ってお墓参りに行き、墓掃除とお参りを行うのが一般的だ。お墓参りの日程に特別な決まりごとないが、ご先祖さまをお迎えする意味も込めて、お墓掃除はお迎えする前日の8月12日までに済ませ、お盆に入る13日のお墓参りが理想とされている。
地域によっては、お盆中日である8月14〜15日にお墓参りをすることもあり、これを「留守参り」とよぶ。お盆の時期、ご先祖さまがお墓を留守にしている間、お墓を守ってくれる仏様に対して感謝を込めてお参りするようになったと伝わる。
お盆の最終日である16日には、ご先祖さまをお見送りするために墓参りをする(地域によって行わない場合もあり)。送り火の行事が催される場合などは、家庭ごとにお墓参りをしない場合も。
お盆の期間中、お墓参りに行ってはいけないとされる日は原則ない。仏滅や友引は縁起が悪いと思われがちだが、仏教とは直接関係がなく、お墓参りには問題ないとされている。
また、お盆にお墓参りに行かない地域もある。そのような地域では、お墓参らなくとも、ご先祖様の魂は位牌を依り代(よりしろ)として帰ってくると考えられているからだ。
新盆(初盆)とは、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆のこと。通常のお盆とは異なり、新盆は故人が初めてご自宅に帰って来る一度きりの機会という点で違いがある。よって、親族や知人・友人などの大勢で、通常のお盆よりも丁寧に華やかにお迎えする行事とされている。
多くの会社がお盆休みを休日とするのは、江戸時代の「薮入り」の影響がある。藪入りは、住み込みで仕事をしている奉公人が、お正月とお盆の前後に休みをとって実家に帰ることができる習慣だ。現代においても、年末年始や夏季の帰省として残っている。特に、夏季の帰省はお盆の風習と結びつき、家族や親族が揃ってご先祖さまの供養を行う風習として根付いた。