田沼意知の「政略結婚」の相手とは? 子にも恵まれ公私ともに順調だったはずなのに…
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第25回「灰の雨降る日本橋」が放送された。蔦重(演:横浜流星)は浅間山の大噴火で灰が降り積もる日本橋の店を守ろうと奮闘。てい(演:橋本 愛)と“商いのための夫婦”になって新たな一歩を踏み出す。一方、田沼意知(演:宮沢氷魚)は、危険を承知で自分のために尽くす誰袖(演:福原 遥)への想いを打ち明け、2人はつかの間の幸せに浸った。さて、意知と誰袖のラブストーリーはフィクションだが、史実の意知はこの時まさに公私ともに順風満帆だった。その半生を振り返る。
■意次が息子・娘の結婚で築き上げた「田沼派閥」
意知は、意次の長男として寛延2年(1749)に誕生した。父・意次は16歳で後の9代将軍・家重の小姓に取り立てられ、享保20年(1735)に田沼家の家督を継いだ。その後わずか19歳で従五位下、主殿頭に叙任され、延享2年(1745)に家重が将軍となると本丸に移り、翌年には小姓頭取に出世。寛延元年(1748)には御側御用取次見習の身分で小姓組番頭に昇格し、家禄も加増されて2000石に達した。仕えていた家重が将軍になってエリート街道を本格的に進みだしたこの頃に、待望の長男が生まれたわけである。意次はその後も家重と10代家治の厚い信任をベースにして目覚ましい出世を遂げていく。
意次は明和9年(1772)に御用人と兼ねる形で老中に昇格する。いよいよ幕政を主導していくようになるが、一方で家柄という面では弱く、“成り上がり者”と揶揄されるのは避けられなかった。そのため、意次は自身の政治基盤を盤石なものにすべく、幕府の要職につく人物や有力な大名・旗本の家と姻戚関係を築いた。
嫡男だった意知の妻として迎えられたのは、石見浜田藩主であり、老中を務めた松平康福の娘である。天明元年(1781)に老中・松平輝高が死去したことにより、意次の先任の老中は康福のみとなったが、既に姻戚関係にあったため“田沼派”に取り込むことに成功していた。
四男・意正は沼津藩主であり同じく老中の水野忠友、六男・雄貞は伊勢菰野藩主である土方雄年、七男・隆祺は丹波綾部藩主である九鬼隆貞の養子となり、娘たちも自分の派閥に取り込みたい大名家に嫁がせ、姻戚関係による“田沼派閥”が構築されていくのである。これが意次の強さでもあり、一方で「親族や姻戚関係にある家の者ばかり取り立てる」という反感を買うことにも繋がった。
さて、意次が権勢を誇るなか、意知の方も公私ともに順調だったようだ。明和4年(1767)には19歳で従五位下、大和守に叙任され、天明元年(1781)には幕府の奏者番に抜擢されている。また、プライベートでは、安永2年(1773)に意明、安永9年(1780)に意壱、天明2年(1782)に意信という息子が誕生している(いずれも生母不詳)。
意次にとっても、自分が築き上げたものを息子、やがては孫へと受け継がせていくための状況が整っていったことに安堵したことだろう。
そしていよいよ意知は天明3年(1783)、35歳の時に若年寄として幕政の中枢に加わるのだ。これはゆくゆくは老中に就任させるためのステップでもあったが、家督も継いでいない、所謂“部屋住み”の状態である意知が若年寄になることは異例だった。
しかも意知は、意次と同様に中奥に入ることも許され、事実上御用人を兼ねる立場になっていた。これで完全に世襲の準備は整い、“田沼政権”が継承されるであろうことは誰の目にも明白になったのである。しかし、すぐ目の前には田沼親子が想像もしなかった落とし穴が待ち受けていた……。
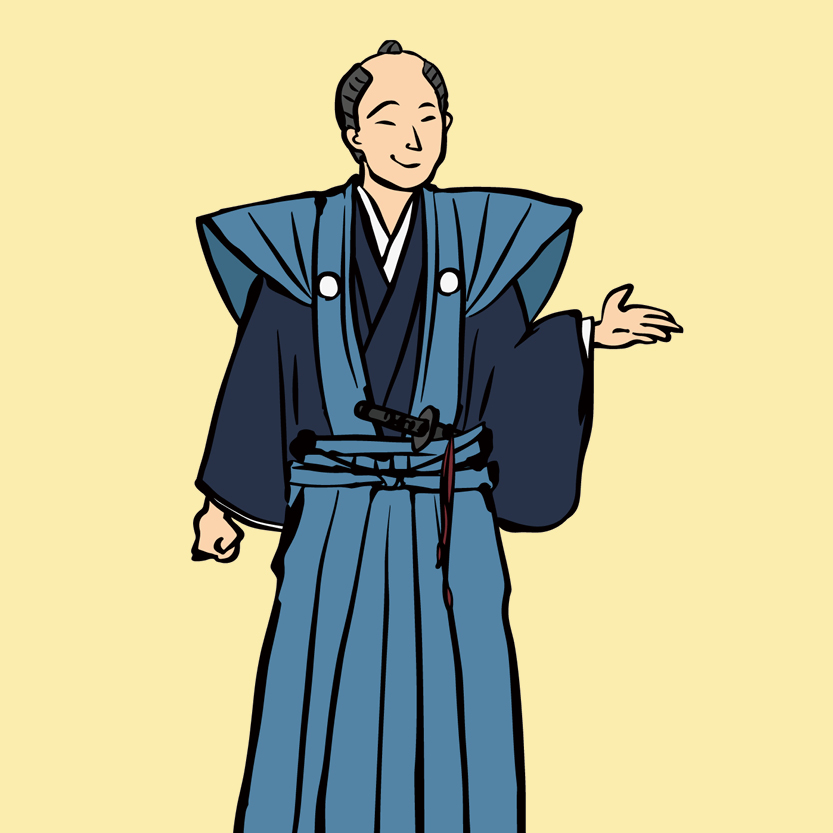
イメージ/イラストAC
イメージ/イラストAC






