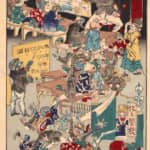なぜ、正月に子どもに「現金」を渡すようになったのか? 高度経済成長期に一般化した「お年玉」の由来
世界の中の日本人・海外の反応
■農村社会の解体とともに、お年玉が現金化
子どもにとって、正月の楽しみとなっているのがお年玉である。それが一番の楽しみという子どもも多いのではなかろうか。
昨今の相場は知らないが、そもそもお年玉に現金を渡すようになったのは昭和30年代(1955~1964)のことで、古くは鏡餅を分け与えるのが一般的だった。
日本にお年玉の風習が根付いたのはいつ頃か。正確な時期は定かでないが、中国伝来の風習で、もとは「御歳魂」と記されたというから、平安時代か鎌倉時代まで遡るのかもしれない。
御歳魂とは、正月に歳神(新たな年の神)を迎えるため供えられた鏡餅を指す言葉である。これを家長が割り、一年を無事に過ごせるようにとの祈りを込め、家族に分け与えたのが本来の姿だった。
時代が下り、近世になると、武士の家では太刀を、町人の家では扇を、医者の家では丸薬を贈るようになるが、農民家庭では鏡餅を分け与える風習が受け継がれた。しかし、農村社会の解体が急速に進むに伴い、お年玉の風習も変化を余儀なくされ、高度経済成長期からは親の職業に関係なく、現金を渡すのが一般化した。
■本場・中国では旧正月に贈られる

イメージ
お年玉文化の本家である中国はどうかと言えば、お年玉は「圧歳銭(ヤースイチエン)」と呼ばれ、「紅包(ホンパオ)」という赤色のポチ袋に貨幣を入れて渡す風習が漢代以降に生まれたようである。
伝説によれば、毎年大晦日の夜には「崇(スイ)」という妖怪が現われ、子どもに悪さをした。妖怪の手で頭を触られた子どもは数日間、発熱に苦しんだ。
そのためどの家庭でも、大晦日の夜には一晩中明かりを灯し、一睡もせずに子供を見守り続けたが、ある夫婦が試しに8枚の銅貨を赤い紙に包んで子どもの枕元に置いたところ、崇が悲鳴をあげて逃げていった。
以来、どの家庭でもそれをまねるようになったという。人びとは8枚の銅貨を「崇を抑えるお金」と呼び、「崇」と「歳」が同じ発音なことから、正月の魔除けとして子どもに贈るそれを「圧歳銭」と呼ぶようになった。
赤色の紅包が使用されるのは、赤色が活力、幸福、幸運の象徴と見なされているから。中に入れる金額は吉祥幸運を意味する偶数に限られるが、「死」を連想させる4のつく金額は不可で、8で始まるか8で終わる金額が最適とされる。現在の中国ではコインも不可で、紙幣を、それもくっきりとした新札を入れなければならない。
旧暦が健在な中国では、子どもに「圧歳銭」を渡すのも新暦ではなく旧暦の正月、いわゆる旧正月(春節)で、現在の台湾と韓国も同様である。世界広しといえど、お年玉文化を持つ国はおそらくこの4か国だけだろう。