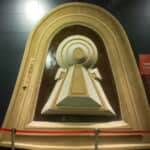日本人の新しいもの好きは古代から? 前方後円墳の広がりと仏教伝来時の様子は似ていた!
[入門]古墳と文献史学から読み解く!大王・豪族の古代史 #085
いろいろ考えていると、前方後円墳が広がった背景と欽明朝(きんめいちょう)以降に仏教を積極的に受け入れた情景が重なって見えてきた。仏教の受容と前方後円墳の普及には、もしかすると同じようなメリットがあったのではないだろうか?

兵庫県神戸市にある五色塚古墳。古墳の建造では、このように膨大な数の葺石を敷き詰めなければならない。(撮影:柏木宏之)
■新たな文化と技術を受け入れて育てる好奇心と向上心
仏教は、欽明天皇の時代に百済(くだら)の聖明王(せいめいおう)から公伝します。崇仏(すうぶつ)派と排仏派が対立をしますが、それは単なる宗教対立とはいえなかったと思います。仏教が包含する新文明を崇仏派の蘇我(そが)氏が独占して権力を強大にすることを物部(もののべ)氏は恐れたのでしょう。
「仏教」と一口に言いますが、釈迦(しゃか)の教えを中心にした哲学と価値観が根本にあるだけではなく、それを理解し実践するためには瓦葺(かわらぶき)の寺が必要です。もちろん五重塔などの高層建築技術、伽藍配置(がらんはいち)やその学問的意義、そして仏像を作る木工(もっこう)・鋳造(ちゅうぞう)・鍍金(ときん)技術やデザイン美術、そのほか蝋燭、線香、仏具、荘厳具(しょうごんぐ)、そして漢字の読み書きや漢語の理解など、大和国(やまとのくに)になかった最新の文明が一挙に流入してくることを意味したのです。
明治維新の時、新政府は海外からお雇い外国人を高給で大勢招き入れ、海外に公費留学生を派遣して近代化を急ぎました。それと同じことが、仏教を受け入れることで巻き起こります。
仏教を正式に取り入れた飛鳥時代は、朝鮮三国から瓦博士(かわらはかせ)や高僧、文字に長けた学者や官僚などを大勢受け入れて大和の若者に学ばせました。そのリーダーの代表格が聖徳太子だったと考えてよいでしょう。このように新文明は瞬く間に広がりますし、その価値を理解した者は貪欲に受容します。大和王権が地方に前方後円墳文化を広げられたのも、同じようなことではなかったでしょうか。

大阪府高槻市にある今城塚古墳にて。こうした埴輪群も、高度な技術で数多く製造されていた。
(撮影:柏木宏之)
■大和王権は豊かな文化と技術提供によって拡大した?
弥生時代から古墳時代に移行した時、見たことのない巨大な人工物である前方後円墳は、人々にとって驚愕の建造物だったでしょう。そのうえ円墳部と長く伸びる方部が連なった異様な形状には、人々を納得させるに十分な死生観や思想があったはずです。
さらに地方の国々は前方後円墳を受け入れると、未知の新文化を手に入れることができました。巨大な構造物を築造する地形の選定方法や測量技術、そしてうず高く段築(だんちく)するための基礎・土木・版築(はんちく)技術、膨大な葺石(ふきいし)の運搬・施工法、埋葬施設工法、そして埋葬時の儀式といったものです。
さらに膨大な数の円筒埴輪(えんとうはにわ)や形象埴輪を製造しなくてはなりません。大きな埴輪を生産するのは並大抵の技術ではありません。埴土(はにつち)の選び方、こね方、造形技術、乾かし方、焼き方、さらには窯の造り方など、とんでもないほど多岐にわたる新技術と新文明を学ぶことができるのです。
そういった最新技術のプロ集団を大和王権は派遣して地方の若者に学ばせたことでしょう。それらはすべて前方後円墳築造にぶら下がる最新のソフトです。ハード面は土木工具や木棺石棺製造のための工具に必要な鉄部品の供与、そしてなんといっても副葬する最高品質の美術品であった銅鏡の贈呈!
仏教を取り入れることで得られる最新文明に大きな魅力があったのと、極めてよく似ているような気がしてなりません。大和王権が武力や鉄だけで近隣諸国を従わせたわけではないことを改めて感じますね。