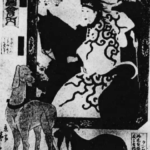抵抗する舞妓の着物を剥いだ女、布団に引きずり込んだ男… 美少女の新人舞妓が経験した衝撃的な「水揚げ」
炎上とスキャンダルの歴史
■少女たちの「初体験」に価値があった花街
大阪を代表する花街・宗右衛門町。その老舗置屋こと「家形」に舞妓として所属することになった14歳になったばかりの千代葉(ちよは)は、姉さん分の芸者・八千代の元・旦那の梅原の手によって布団の中に引きずり込まれる衝撃的な経験をしています。明治42年(1909年)12月のことでした。
千代葉はのちに『花喰鳥』という自伝を残しているのですが、読者にとってショッキングなのは、この「水揚げ」と呼ばれる儀式化された性の初体験が、抵抗する千代葉の着物を別の女たちが無理やり剥ぎ取り、下着一枚に相当する襦袢姿にすることで始まったという描写です。
舞妓たちは現在なら小学校高学年程度でしょうか。それくらいから16、7歳くらいまでの間、最低3回は、姉さん分の芸者の後援者の一人で、必ず年配の太客が選ばれ、「水揚げ」が行われ続けたそうですが、それが舞妓たちの女性としての人格形成に暗い影を落とすことは間違いありません。
当時の千代葉は初潮さえ迎えていない少女だったので、第一回目の「水揚げ」では性交不成立に終わりました。
そんな失意の千代葉を襲ったのが、「初恋」のさらなる衝撃だったのです。おぞましい「水揚げ」から3ヶ月ほど経過した明治43年(1910年)3月、花街が春の恒例としていた「あしべ踊り」のための稽古のさなか、偶然出たお座敷で、千代葉は市川松鳶という女形の歌舞伎役者に出会い、初めての恋に落ちています。
恋に落ちたきっかけは、誰も自分などの踊りに興味はないだろうと思いながらも一生懸命に舞う「たつ」でしたが、「チラッと私が松鳶さんを見たら、松鳶さんも、私を見ていました。そして私が、ハッとして眼を外らすと、松鳶さんも、ハッとしたように眼を外らしました」。
本来なら学校の教室で起きるような初恋の情景が、夜のお座敷で生まれたのですね。
「色街という社会に突き出されて、現実にみせつけられた男の姿といえばただ厭らしい、あたかも醜い肉と脂肪の塊」と思っていたにもかかわらず、水も滴る美男――市川松鳶の「美しい優姿」に自分の心臓が「かつて覚えたことのない血潮の奏で」る音を感じてしまう千代葉でした。
しかし舞妓になったばかり、おまけに14歳を迎えたばかりにもかかわらず、すでに千代葉には複数の身請け話が来ていました。そのひとつが千代葉がよく呼ばれている「丸屋」というお茶屋の女将を通じての話で、五十路手前の「古川はん」からのお誘いでした。
千代葉は迷いました。例の歌舞伎役者・市川松鳶が気になって仕方ないのです。もともと舞妓に恋愛の自由はありませんし、もうすぐ大阪を去って東京に戻ってしまう松鳶に入れあげるなど、破滅を招く危険な誘惑です。
――しかし、人知れず恋のため息をついているだけのつもりだった千代葉の変化に気付いた数少ない女が「丸屋」の女将でした。「丸屋」の女将は千代葉に、もし古川はんの身請け話を受け入れのであれば、いつでもウチで松鳶さんと会わせてやると裏取引を持ちかけます。旦那である古川さんから「逢状」が届いたと偽って、「丸屋」で松鳶さんとの密会がセッティング可能だというのです。
「しかし、一見優しい丸屋のおかみさんの言葉の中には、松鳶さんを利用して、古川はんへ義理立てする落胆が含まれていたのです」。のちに自伝『花喰鳥』の中で千代葉が語るように、身請け話が丸屋を通じて成立すれば、女将の懐にも大金が転がりこむ算段でした。
松鳶と再会したい千代葉の純情を見透かすように、「丸屋」の女将は松鳶との密会をセッティングしてくれました。二人は天下茶屋でデートし、そのまま「瓢亭」というお茶屋で会食。やがて周囲から人が消え、「もれてくる微かな陽の光の中に、のべられた一組の夜具と二の枕がほの白く浮びあがって」いる離れの一室において、二人きりに。こうして松鳶によって、千代葉に「女の証」が授けられたのでした。
成就した恋の喜びを隠すのに千代葉は必死だったはずです。しかし彼女を暗い現実に引き戻すのが、「丸屋」からの古川はんの逢状(指名)でした。夢のような幸福な時間には「対価」が求められる――それが花街の掟だったのです。

イメージ/イラストAC