玉音放送の3日後にソ連軍の奇襲…故郷に帰れず理不尽な敵に立ち向かわざるを得なかった「占守島の戦い」
戦後80年特別企画
日本領だった千島列島北東端の島、占守島(しゅむしゅとう)で起こった日本軍とソ連軍の死闘。それは日本が降伏を表明した後に起こった戦いであった。終戦の報に触れ、故郷に帰る希望に喜んだ日本軍将兵であったが、祖国を守るため、決然と理不尽な敵に立ち向かったのである。

占守島の戦いで、ソ連軍を撃退するために進軍する陸軍第11戦車連隊の九七式中戦車。日本陸軍の主力戦車であったが、防御力はとても強力とは言い難いものだった。装甲板はもっとも厚い部分でも25mmしかなかった。
昭和20年(1945)8月18日午前2時半頃、千島列島北東端の占守島竹田浜は、突如として国籍不明の軍隊による奇襲上陸に見舞われる。それとともに、海上の軍艦からの艦砲射撃も始まった。この地を防衛していたのは、独立歩兵第282大隊(大隊長:村上則重少佐)隷下の1個中隊と大隊砲3門、速射砲3門、野砲2門、臼砲4門であった。
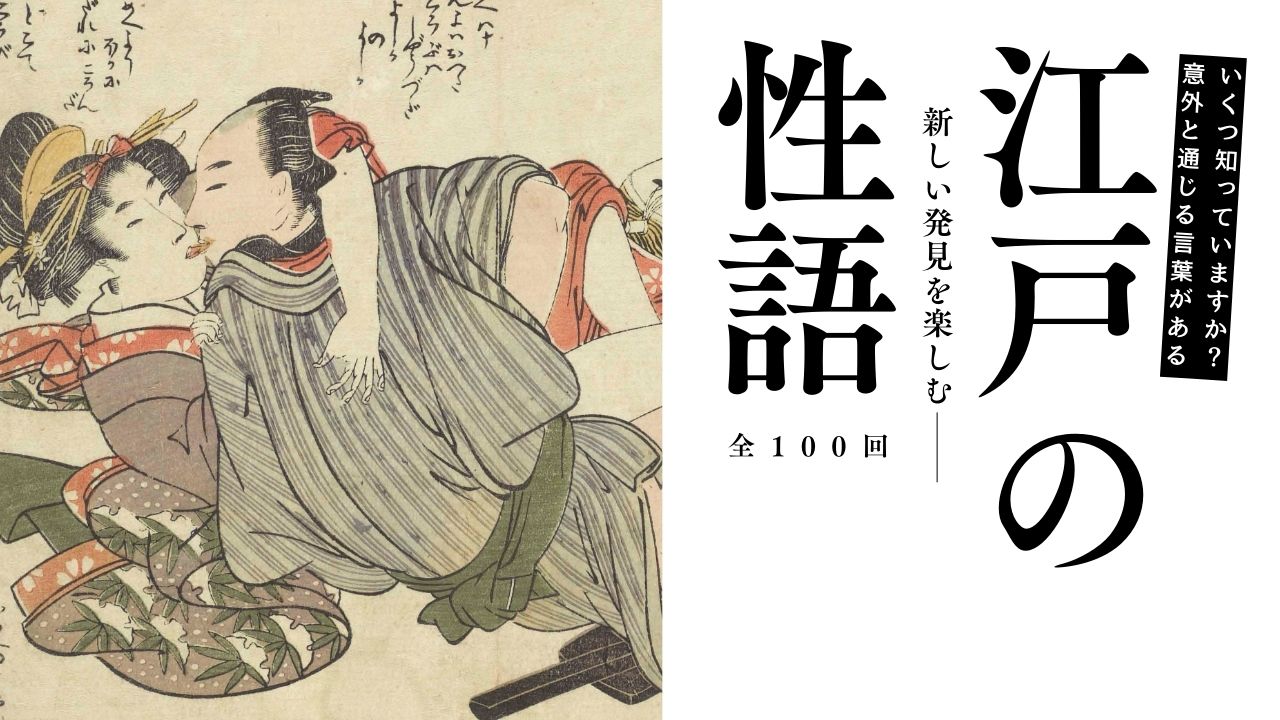
極東ソビエト軍総司令官のアレクサンドル・ヴァシレフスキー元帥(中央)。8月15日、ヴァシレフスキーは第二極東方面軍司令部と太平洋艦隊司令部に対し、千島列島北部の占領作戦の準備、実施に関する命令を発した。(写真は1945年に旅順で撮影されたもの)
すでに8月15日にポツダム宣言受諾が公表され、正午の玉音放送に続き、占守島の守備隊にも北海道の第5方面軍から
・大本営より一切の戰鬪行動停止すること
・ただし止むを得ない自衛行動は認める
・武装解除の完全徹底は18日16時とする
という命令が届けられていた。部隊の将兵は戦争が終わったものと思っていた。だが「こんな真夜中に砲撃しながら上陸してくるのが、停戦交渉のための軍隊であるはずがない」と判断した村上少佐は、ただちに反撃を命令。国籍不明の敵に対し激しい砲撃を加え、上陸用舟艇13隻を撃破。指揮官が乗っていた舟艇も沈んだため、上陸部隊の統制は乱れた。軍艦は艦砲射撃で日本軍の砲台を制圧しようとしたが、効果はなかった。そのうち日本軍は、上陸してきたのはソ連軍だということを認識する。そしてこの地域を担当する第5方面軍に、ソ連軍上陸の報を入れた。

樋口季一郎中将は情報に基づく合理的な判断を下す名将であった。ハルビン特務機関長時代に、多くのユダヤ人の満州国通過を認め、多くの命を救った人物である。軍人であるがゆえに、杉原千畝ほど話題になっていない。
第5方面軍司令官は、陸軍きってのロシア通と言われる樋口季一郎(ひぐちきいちろう)中将であった。他の指揮官ならば、ソ連が上陸してきたのは武装解除の特使と思い込んだかも知れない。だが樋口中将は「ソ連ならばこの機に乗じて攻めてきてもおかしくない」と判断。中央に打診することなく戦闘開始を即断。「断乎、反撃に転じ、ソ連軍を撃滅すべし」と命じた。
そもそも占守島を含む千島列島は明治8年(1875)、日本とロシアの間で「樺太・千島交換条約」を結び、平和裏に日本領土となっていた。ところが1945年2月のヤルタ会談における秘密協定で、ソ連はドイツ降伏後2〜3カ月以内に日本との戦争に参戦する見返りに、日露戦争後に日本へ割譲した樺太南部の返還と、千島列島すべての引き渡しを要求、英米に承認させた。ところが亡くなったルーズベルト大統領の後任、トルーマン大統領が8月15日に通達した一般命令には、ソ連の占領地域に千島列島が含まれていなかった。
それに憤慨したスターリンは、千島列島および釧路と留萌(るもい)を結んだ線より北の北海道北東部をソ連占領地域とすることを求めた。だがアメリカに拒否されたため、実力で奪い取るために軍を派遣したのである。






