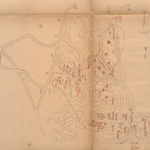国の為に尽くした女学生を描く『一番美しく』と『日輪の遺産』その姿にいま何を感じるだろうか?
◼️戦時中に製作された『一番美しく』
先の大戦では、出征する男性が増えるにつれ、代わりの労働力として未婚女性も動員されるようになった。戦局の悪化とともに強制的な動員がかけられ、彼女たちは女子挺身隊(ていしんたい)と呼ばれ、軍需工場などで働くこととなる。そんな彼女たちにスポットが当たった映画も、もちろん存在する。
冒頭から「撃ちてし止まむ」のスローガンが掲げられる『一番美しく』は昭和19年(1944)年4月13日に公開された。巨匠・黒澤明監督2本目の作品であり、国の為に成果をあげようと懸命に働く女性たちの姿が描かれている、いわゆる戦意高揚映画だ。
出演する若手女優たちは撮影前の約2ヵ月間、実際の光学工場へ入所し訓練を重ねたという。ゆえに、劇中における彼女たちに振る舞いは実際におけるものと遜色ないだろう。ましてや、目下戦時中の製作であるから、国の為に尽くそうと熱心に働く彼女たちの献身さは真に迫るものがある。
黒澤明は本作品が公開する1年前に「(外国映画の面白さに勝つには)ただ日本人の国民性の深奥に根ざすばかりである」と書き残している。矢口陽子(後の黒澤明夫人)が演じた主人公の渡辺ツルは人一倍責任感が強く、自分のことよりも同僚の仲間を想う女性である。そんな彼女が「がんばって! がんばって!」と声を張り上げるシーンは、観ているコチラをも鼓舞するようである。黒澤明の狙いの一端が垣間見える。
しかし、そんな戦意高揚も空しく、映画公開から半年後には初めて組織的な特攻隊が飛び立ち、さらには米軍機の空襲が本格化するなど、国民の生活はますます厳しいものとなっていく。
◼️『日輪の遺産』から感じるもの
『日輪の遺産』(佐々部清監督/2011年公開)は山下奉文(ともゆき)将軍が奪ったマッカーサーの財宝というワクワクする題材でありながら、終戦間近の女生徒たちに降りかかった悲しい物語である。
森迫永依(もりさこえい)、土屋太鳳(つちやたお)らが演じた勤労動員として召集された女子中学生たちは、『一番美しく』の彼女たちと同様に与えられた仕事を一生懸命に遂行する。特に級長として皆を引っ張る森迫永依は渡辺ツルのようである。その級長が時を経て老齢女性となるのだが、この女性を八千草薫が演じている。
八千草薫自身もまた、軍需工場で働いていた経験があるという。それもあってのことだろう。この作品に対する思い入れは強かったと作品公開時に語っている。それを踏まえて観ると、その表情や眼差しには、代名詞である上品さや可憐さを超え、二度と同じ過ちを繰り返してはならないという「強さ」が感じられる。この作品の八千草薫の演技は出色である。
原作となった小説『日輪の遺産』のあとがきに著者の浅田次郎は〈「どうしようもない終わり方」をおもいついた〉と記している。その通りの悲劇である。けれども、映画では女生徒を指揮した将校がマッカーサーに向かって、「いつの日か、必ず日本製品が米国を席巻するでしょう」と言い放つ場面がある。戦後、自動車業界などでその言葉通りになることがわかっているだけに、この台詞が少しの救いになる。
そして、戦争後に黒澤明の作った作品もまた米国を席巻する。フランシス・フォード・コッポラやスティーブン・スピルバーグ、ジョージ・ルーカスといった米国を代表する名だたる監督が彼を慕い、アカデミー賞名誉賞の受賞も果した。
外国映画の面白さに打ち勝たんとした黒澤明の念願も叶ったといえるだろう。
改めて女子挺身隊へ思いを馳せてみる。いま、ここに自分が生きているということは、母が、祖母が、曾祖母が、その誰かが戦争に従事し、戦火をくぐりぬけ命をつないだということである。そのことをしっかりと胸に刻みたい。

車の整備をする女子挺身隊員(『写真週報』338号 昭和19年9月13日号/国立公文書館蔵)