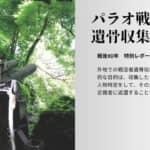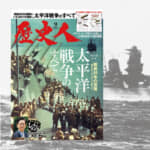【お盆の謎】お盆になると現れる「キュウリ」や「ナス」の人形とは?
夏の伝統風習「お盆」を知る! 【第3回】
今週からお盆のシーズンに突入! 家族での帰省や行楽で、全国各地が賑わう時期でもある。日本の伝統的な風習であるお盆は、そもそもどのような目的でいつ頃からはじまったのか? 墓前の灯籠(とうろう)、送り火、盆おどり、精霊流しなど、お盆にまつわる行事、地域や宗派ごとの相違点、タブーもふくめて、意外に知らないお盆の謎をわかりやすく解説する。
■キュウリは故人のお迎え、ナスはお見送りで活躍

キュウリとナスで作られた精霊馬、精霊牛
お盆になると、仏壇やお墓などで、キュウリやナスに4本の割り箸をさした、馬や牛のお飾りを見かけることがあるのでは? これは「精霊馬」(しょうりょううま)、「精霊牛」(しょうりょううし)とも呼ばれる、現世とあの世を行き来する乗り物で、故人やご先祖さまを迎え入れる役割を担っているのだ。
キュウリは足の速い馬に見立てられ、ご先祖様に早く帰ってきてもらいたいという願いが込められている。もう片方のナスは、ゆっくりと歩く牛に見立てられ、ご先祖様にゆっくりと景色を楽しみながらあの世に帰ってほしいという願いが込められているのだ。
精霊馬・精霊牛はナスとキュウリで作るのが一般的だが、わらを材料として作る地域もある。キュウリとナスはどちらも手に入りやすく親しみ深い野菜であり、お盆の時期に収穫量が多いという理由から、精霊馬、精霊牛として使われるようになったと考えられている。また、形が馬や牛に見立てやすいことから、との説もある。
キュウリやナスで作った精霊馬、精霊牛は、8月13日の迎え日を迎えると仏壇や精霊棚に飾られる。8月16日に送り火が終わってから片付けるのが一般的だ。迎え火のときはキュウリもナスも頭を内向きにして置き、送り火のときには外向きに置く。 地域によっては、ご先祖様が東から来ると考えられているため、キュウリの馬を西向き、ナスの牛を東向きに配置することもある。
■お役目を終えたキュウリ・ナスを食べてはいけない
浄土真宗は、開祖である親鸞の教えにより「人はすべて死して仏になる」という考えの宗派である。このため、浄土真宗には「先祖はいつでも遺された者達の側で見守っていてくれる」という思想があり、基本的にお盆行事は行わない。よってお盆飾りである精霊馬や精霊牛を飾ったりすることもない。
お役目を終えたナスとキュウリは、一昔前までは「精霊流し(しょうりょうながし)」として自宅近くの川に流すことが一般的であった。しかし、現代の生活様式や意識の変化から、最近では川に流すことほとんど見かけなくなった。では、どのように処分すればいいのか?
お寺などでは、お供えして役目を終えた品物や、お札やお守りを燃やす「お焚き上げ」を行っていることがあり、そこに持ち込むことができる。しかし、お寺によっては決められた品物しか受け取らない場合や、お焚き上げ自体を行っていないお寺も多く、持ち込みが可能かどうかを確認してから行くようにする。また、自宅で処分する場合は、庭に埋めることもできる。
自宅に庭がなく、近くに処分を頼めるお寺がない場合は、家庭ゴミとして処分も可能だ。そのままゴミとして捨てるのは忍びないと思う場合は、キュウリとナスを半紙に包んで塩をふり、お清めをしてから処分する。
お役目を終えたナスとキュウリを食べることはお勧めできない。精霊馬・精霊牛はほかのお供え物とは異なり、人が食べて供養するものではないと考えられているからだ。故人や先祖を運んでくれたことに感謝して丁寧に処分する。