「瘡(かさ)」梅毒のこと【江戸の性語辞典】
江戸時代の性語97
我々が普段使っている言葉は時代とともに変化している。性に関する言葉も今と昔では違う。ここでは江戸時代に使われてた性語を紹介していく。
■瘡(かさ)
性病の梅毒のこと。
江戸時代はコンドームがなかったため、男女はみな「ナマ」で性交していた。結果として、梅毒などの性病が蔓延した。
また、抗生物質がなかったため、梅毒は不治の病だった。
(用例)
①戯作『仕懸文庫』(山東京伝著、寛政3年)
深川の岡場所で、遊女が薬を飲んでいるのを見て、客の男がからかう。
男「瘡(かさ)の薬か」
女「知りやせん」
さすがに、女はむっとしている。
■瘡気(かさけ)
梅毒の症状のこと。あいつは瘡気がある、などと言った。
(用例)
①戯作『滑稽富士詣』(仮名垣魯文著、文久元年)
近所のしゃも七先生という男の噂をして、
この前、しゃも七先生が骨がらみになりかかったとき。横町の雌犬とつるんで瘡気を抜こうとしたのは……
「骨がらみ」は病状が重くなったこと。ここは、梅毒が悪化したのであろう。
当時、梅毒にかかった男は、メス犬と性交すると病気を犬にうつし、自分は治るという迷信があった。
■瘡かき(かさかき)
梅毒患者のこと。
(用例)
①戯作『東海道中膝栗毛』(十返舎一九著、文政5年)
弥次郎兵衛が宿屋の女中と密会の約束をしたのを知って、連れの喜多八が邪魔しようと、女に言う。
「こりゃあ、内緒のことだが、あの男はおえねえ瘡かきだから、うつらぬようにしなせえ」
■瘡毒(そうどく)
性病の梅毒のこと。話し言葉では「かさ」と言うことが多い。また、「瘡毒」と書いて、「かさ」と振り仮名をすることもある。
(用例)
①『反故のうらがき』(鈴木桃野著、嘉永年間)
明石藩の某藩士は武芸にはげんでいたが、
三十計(ばかり)の頃、瘡毒を受けて身節いたみ、武事を講ずることも自由ならず。口惜き事かな。
症状は人により差があるが、この武士は武芸を断念せざるを得なかった。
■鼻が落ちる(はながおちる)
梅毒が進行した状態。梅毒が進行すると俗に「鼻が落ちる」と言われた。
(用例)
①戯作『花筺』(松亭金水著、天保12年)
若旦那が女郎買いをしているのを知り、ある人が妾を持てと勧める。
「方々で食いちらかすよりゃあ、あの子を世話にでもしておきなさると、まあ、第一、鼻の落ちる気使えがなしさ」
素人の女を妾にすれば、梅毒にかかる恐れはない、と。
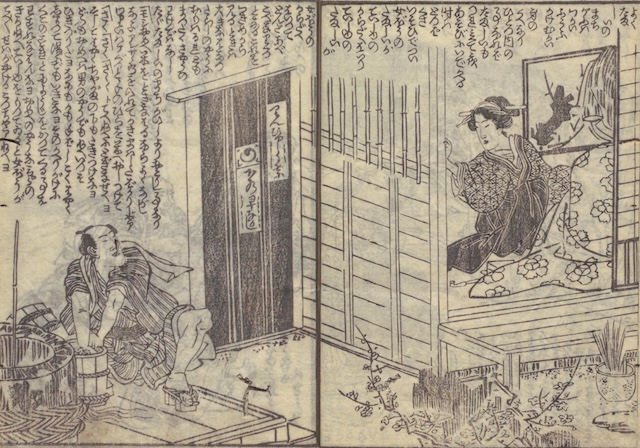
黒塀に貼られた「りんびょう薬」「月水早ながし」の札。「りんびょう」は性病の一種の淋病、「月水早ながし」は堕胎薬である。『滑稽多新形』(東里山人著、文化15年)、国立国会図書館蔵







