朝ドラ『あんぱん』超エリート帝大生が海軍少尉になるまで 最後に兄に伝えた「願い」とは?
朝ドラ『あんぱん』外伝no.38
NHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』、第11週は「軍隊は大きらい、だけど」が放送中だ。嵩(演:北村匠海)は弟の千尋(演:中沢元紀)と再会するが、彼は海軍少尉になっていた。佐世保から駆逐艦に乗って南方に向かうという。史実でも、やなせたかし氏の弟である千尋さんは海軍少尉として海に出たという。今回は千尋さんの足跡を追う。
■愛らしい少年から文武両道の好青年に成長
柳瀬千尋さんは、大正10年(1921)に父・清さんと母・登喜子さんの第二子として誕生した。兄・嵩さんとは2歳違いである。大正13年(1924)に清さんが病没すると、生前から約束していた通り清さんの兄である寛さん夫妻の養子となった。明るく、子供らしい奔放さと愛嬌で誰からも愛され、寛さん夫妻もわが子として愛情を注いで育てあげた。後に、実母の再婚によって嵩さんが後免町の柳瀬医院に引き取られてからは、養父母と実兄の4人で暮らした。
中学生になると学業でも武道でも才能を開花させ、文武両道の立派な男子学生に成長。成績優秀で、中学4年の時に1年早く受験をして、旧制高知高等学校(現在の高知大学)に合格した。昭和13年(1938)4月25日付の官報には、「入学許可者」の「高知高等学校 文科甲類」の生徒一覧のなかにその名前が掲載されている。高校に入っても相変わらずよく勉強ができ、運動神経も抜群、しかも物腰柔らかな好青年だったという。
昭和14年(1939)、千尋さんが高校2年生に進級する直前に、伯父であり養父でもある寛さんが急逝した。この時、嵩さんは旧制専門学校・東京高等工芸学校の図案科(現在の千葉大学工学部)で絵や図案を学んでいた。危篤の電報を打ったとて、当時は東京から高知に帰省するには一昼夜かかる。それでも千尋さんは寛さんの臨終に間に合わなかった嵩さんを「兄貴、遅い!」と詰ったという。やなせたかし氏の著書『アンパンマンの遺書』などでは、その時千尋さんに何も言い返せず、ただ寛さんの棺にすがって泣くしかなかったと記されている。
昭和16年(1941)春、千尋さんは京都帝国大学法学部に進学。古都京都は養父母が出会った思い出の地でもあった。そんな場所で仲間たちと切磋琢磨しながら学生生活を謳歌し、エリートへの道を突き進むはずだった千尋さんだったが、戦争はそれを許さなかったのである。
同年10月、勅令第924号「大学学部ノ在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ関スル件」によって、 大学・高等専門学校の在学または修業年限(3年)が6ヶ月短縮されることとなった。卒業が半年繰り上げられたのである。ちなみにこの年、兄の嵩さんは出征し九州小倉の野戦重砲隊に入っている。
昭和18年(1943)9月、予定より半年短い2年半で京都帝国大学を卒業した千尋さんは、志願して海軍予備学生となった。まずは4ヶ月という短期間に海兵団で基礎教育を受けるのだが、エリート学生たちにとって、厳しい訓練と勉強に忙殺される日々は過酷なものだった。その後、試験を経てその結果や適性に応じて、それぞれ専門教育を受けることになっていた。
千尋さんは耳が良かったこともあって、「対潜学校」(元々は「機雷学校」だった)に採用されることになった。端的に言えば、対潜水艦を想定した専門的な訓練を行う場である。海の中で敵の潜水艦の音を聴きとって対応するため、聴覚を鍛える訓練も必要だったという。
昭和19年(1944)5月、対潜学校での4ヶ月の教育課程を終えた千尋さんは、海軍少尉に任官されることになった。3日間だけ休暇を与えられると、故郷の高知に戻って養母であるキミさんらと会ったらしい。
兄弟もまた、再会していた。千尋さんは一度だけ小倉にいた兄の嵩さんを訪ねたそうだ。そこで兄弟は久しぶりに言葉を交わした。やなせたかし氏の著書『やなせたかしおとうとものがたり』に収録された詩の一遍にはその時のことが記されている。それによると、千尋さんは「自分はもうすぐ死んでしまうが、兄貴は生きて絵を描いてくれ」と言い残したという。
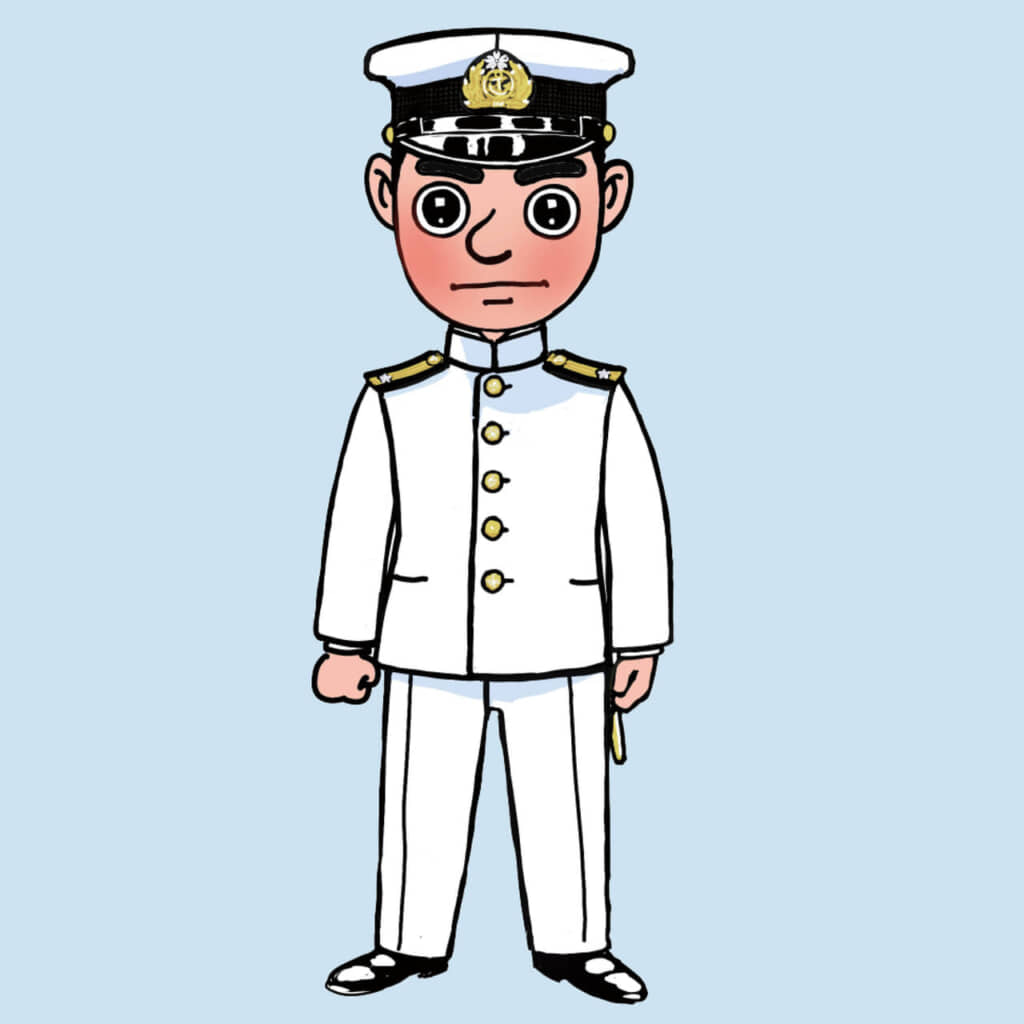
イメージ/イラストAC
<参考>
■やなせたかし『アンパンマンの遺書』(岩波現代文庫)
■やなせたかし『人生なんて夢だけど』(フレーベル館)
■やなせたかし『やなせたかし おとうとものがたり』(フレーベル館)
■門田隆将『慟哭の海峡』(角川書店)
■文部科学省『学制百年史』「戦時教育体制の進行」(学制百年史編集委員)






