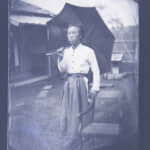【東京23区城跡めぐり】戦に敗れた父を追って入水した照姫 悲劇舞台となった豊島氏の石神井城
江戸城を築いた太田道灌に攻められて居城と逃げ込んだ先で2度も落城。敗走の末に、城に隣接する三宝寺池に沈んだ豊島氏とその娘の悲劇をご紹介する。
みなさんは照姫という名前を聞いたことがあるだろうか。戦国時代、戦いに敗れて亡くなった父を追って、池に身を投げたという悲劇のヒロインである。
その悲劇の舞台となったのが、東京都練馬区にある三宝寺池だ。悲劇の舞台となったこの池は都立石神井公園の西側に位置し、東京23区内だとは思えないほどの静謐さを保つ。平日の昼間でも散歩を楽しむ人やスケッチをする人などもいて地域の憩いの場になっている。
かつて、この三宝寺池の南側に石神井城があった。城の水を確保すると同時に北側の守りとして三宝寺池を利用するための選地だったのだろう。池の北側は、かなり急な斜面となっており、池の南側で城の主郭だったとされる場所には土塁や堀跡などが残っている。しかし、城跡保存のため、良好な部分は柵に囲まれて立ち入ることができない。
この地に城が造られたのは、室町時代ではないかと考えられているが、詳しいことはわかっていない。藤原一族の宇多氏がこのあたりを治めていた。しかし、鎌倉時代後期に桓武天皇の曽孫にはじまる秩父平家の流れを汲んだ御家人の豊島氏と婚姻関係を結び、その後豊島氏の所領となった。豊島氏は、現在の東京都練馬区や板橋区、足立区、埼玉県新座市あたりに領地を有していた有力な武士であった。
文明5年(1473)、室町幕府が関東を支配するために置いていた鎌倉公方を補佐する関東管領の家臣長尾景春が、人事に不満をもち挙兵。この戦いを長尾景春の乱という。この時、豊島氏は長尾景春側についた。兄の泰経が石神井城、弟の泰明が5キロメートルほど離れた練馬城で、河越城と江戸城の通行を遮断した。ちなみに泰明がいた練馬城跡は、現在東京都立練馬城址公園として整備され、当時の土塁を見ることができる。
公方扇谷上杉家の家宰であった太田道灌は、自分の居城江戸城と主の本拠地である河越との往来がままならない状況を打破するため豊島氏を潰すことを計画。まずは練馬城を攻めようとしたが、豊島兄弟は城を出てしまう。そのため江古田・沼袋(現東京都中野区)で戦うことになったが、弟の泰明は道灌に討ち取られてしまった。
残った兄の豊島泰経が石神井城に戻ったところを、道灌が攻撃。泰経は降伏したものの、降伏の条件に含まれていた破城を行わなかったため、道灌は再び石神井城を攻めたてた。城は落ちたが、泰経は、道灌の軍勢が来る前に城を出て、小机城(現神奈川県横浜市)まで逃げた。これを道灌が追撃し、落城。その後泰経は行方しれずとなった。
だからだろうか。冒頭に述べたように地元では、泰経は石神井城に戻り、金の鞍を置いた白馬にまたがって、三宝寺池に沈んだと伝わる。そして、これを知った娘照姫も後を追って池に入ったのだ。これにより、豊島氏は滅亡した。
池のほとりには豊島泰経の墓と伝わる殿塚と照姫の墓とされる姫塚が立っている。姫塚は、太田道灌が照姫を憐れんで建てたものだそうで、塚の側に立つ松に登ると池の底に沈んだ金の鞍が見えるという。実は、照姫は実在しなかったらしいのだが、こうした伝承が語り継がれるということは、地域の人々がかつてこの地を支配していた豊島氏をいつまでも忘れないということだろう。その証拠に石神井では、昭和63年(1988)から4月に照姫まつりが盛大に行われている。

三宝寺池の池畔に立つ石神井城址の碑。この碑の後ろ側に石神井城主郭部分の土塁などが残っている。残念ながら柵で囲われているが、柵の外側からでも目視が可能だ。