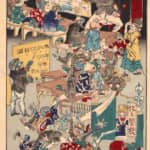外国人が驚く「日本のスゴい鉄道」なぜ世界でいちばん時間に正確なのか? 背景に「地形」があった!
世界の中の日本人・海外の反応
■「正確な鉄道」は日本人の国民性なのか?

鉄道
時刻表通りに運行する鉄道は、訪日外国人が驚くことの一つである。一年365日、始発から終電まで、事故でもない限り分単位で正確に走る列車など、世界中探してもほかに例がないからだ。日本人の国民性、生真面目さの表れと説明されることが多いが、本当はどうなのか。
世界で最初に開業した鉄道はイギリスのリバプール・アンド・マンチェスター鉄道で、時は1830年1月のこと。それから19世紀中頃までに西ヨーロッパ全土とアメリカ合衆国で敷設・開業が進んだ。日本でも1872年に新橋~横浜間、1874年に大阪~神戸間が開業している。
新橋~横浜間も大阪~神戸間も着工したのは同じく1870年。計画自体はそれより何年か前に持ち上がっていたが、設計にあたり、一つ問題があった。左右のレール間隔(軌間)を広軌(国際標準軌)の1・435メートルにするか、狭軌の1・067メートルにするかの選択である。
■「狭いレール」を選択した日本
当然ながら、広軌にした方が一回に運べる物資の量が多く、スピードも出せる。けれども、山間部の多い日本で広軌を走らせるには問題が多すぎた。山があれば、迂回をさせるかトンネルを掘るかのどちらかしかないが、広軌は狭軌に比べ、迂回の曲線半径を大きく取らなければならない。
明治の前半であれば、用地の確保に問題はないが、建設費用の膨れ上がりは何としても避けたかった。当時、日本は近代化を急ぎながら、いまだ金満とは呼べない状況だったからである。
かくして明治日本は狭軌を選択したが、第一次世界大戦で戦争景気を体験した頃から旅客・貨物ともに需要が爆発的に増え始めた。
「広軌に改めるべき」とする意見もあったが、いまだ鉄道網の及んでいない地方への敷設を優先すべきとの主張を前にしてかき消され、需要の増加には「速度を上げ、運行数を増やすことで対応すべし」とされた。
■定時運行せざるを得なかった
けれども、「言うは易く行うは難し」とはよく言ったもので、運行数を増やすには何をどうしたらよいのか。人員の増加と車両の増産だけで解決する問題ではなく、渋滞や足止めなども避けねばならない。
諸々の問題をすべて解消するには、方法はただ一つ。それはすべての列車の「定時運行」だった。普通列車や急行・特急列車、貨物列車が混在する鉄道上を支障なく回転させ続けるには、すべての列車に時間を厳守させるしかない、との結論に達したのである。
一見、飛躍した理論のようにも思えるが、「時間厳守」「時刻に正確」は一種の呪いのように、鉄道関係者だけでなく、日本人全体に広く浸透した。近年は時間厳守に綻びが見え始めたとはいえ、鉄道の分野に限れば事情は変わらず、時刻表通りに運行する鉄道は、いまや日本が誇るべき美徳の代表格となっており、捨て去る理由もあるまい。