大河ドラマ『光る君へ』で注目の姫 藤原道長の正妻・源倫子とはどのような人物だったのか?
紫式部と平安のヒロインたち#01
大河ドラマ『光る君へ』で黒木華さんが演じる源倫子は、左大臣家の姫としての教養と人柄が魅力。一方で主人公まひろ(紫式部)に貴族社会の厳しさを教えてくれる気高い存在です。今回は史料に残る倫子と道長についてご紹介します。
■藤原道長の正妻となった高貴な生まれの姫君
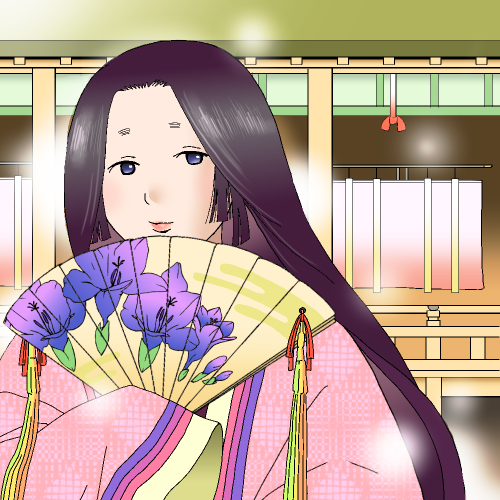
ⓒ関根尚
大河ドラマの中で、いかにも高貴な女性らしく、春風のように穏やかでおっとりと描かれているのが源倫子(りんし)です。彼女が藤原道長の正妻でした。
源倫子は左大臣源雅信の娘で、母は藤原穆子(ぼくし)でした。道長とは永延元年(987)に結婚したようです。道長との結婚をめぐって、『栄花物語』「さまざまのよろこび巻」に次のような印象深いエピソードが紹介されています。
父雅信は倫子を天皇の后にしようと考えて、大切に育てていました。ところが、道長が倫子に求婚してきたのです。当時、道長は最高権力者兼家の子でしたが、正妻時姫の3番目の男子で、その妻になることは、天皇の后に比べれば、ずいぶん落差があるという存在でした。そのため雅信は道長の求婚に対して、良い顔をしなかったといいます。その時、母の穆子が道長の将来性を鋭く見抜き、道長を婿にするよう、夫雅信に強く迫りました。雅信は穆子の説得に負けて、しぶしぶ道長との結婚を認めたのです。道長は当時22歳、倫子は24歳でした。
雅信は左大臣という高官で、また宇多源氏の血を引く高貴な人物でした。その人物の婿になったというのは、その後の道長の人生にとって大きなアドバンテージとなりました。倫子との結婚は道長の人生を切り開いたのです。倫子は道長との間に彰子(一条天皇中宮)をはじめ、妍子(三条天皇中宮)、威子(後一条天皇中宮)、嬉子(東宮敦良親王女御)ら4人の后を生みました。
長男頼通も五男教通も倫子の産んだ子で、2人とも関白の位まで上りました。ちなみに、道長にはもう1人、源明子(源高明の娘)という妻がいて、この間にも6人の子供がいましたが、子供の昇進速度は圧倒的に倫子の生んだ子のほうが速かったのです。
『栄花物語』「はつ花巻」に拠ると、道長は息子の頼通の結婚をめぐって、頼通に向かって「男は妻次第だ」(「男は妻(め)がらなり」)と言ったといいます。道長にとって、これは実感だったことでしょう。倫子を妻にできた幸運を道長はよくわかっていたのです。後に、娘彰子が皇子を生む実家となる、道長の邸宅・土御門殿も元々は義父雅信のもので、これを道長が譲り受けていたのでした。頼通は具平親王の娘隆姫(たかひめ)と結婚しますが、隆姫との間に子はなく、頼通の子の少なさが摂関家の将来に微妙な翳りを投げかけます。
『紫式部日記』には、倫子も登場しています。紫式部と倫子とのやりとりも興味深いのですが、それはまた別の機会に触れることといたしましょう。
<参考文献>
福家俊幸『紫式部 女房たちの宮廷生活』(平凡社新書)






