紫式部をかわいがった伯父・藤原為頼の愛情 和歌の達人が残した歌に見え隠れする姪への想いとは?
『紫式部日記』『紫式部集』で辿る紫式部の生涯#07
大河ドラマ『光る君へ』では、主人公のまひろの家族として両親と弟が登場した。しかし、史実では紫式部の身近には、父や弟のほかにも愛すべき家族の存在があった。今回は、伯父・藤原為頼についてご紹介する。
連載第1回目で触れましたように、紫式部の曾祖父藤原兼輔は中納言に上り、紀貫之などの歌人を庇護しました。しかし、祖父の雅正は女房歌人の伊勢との風雅な和歌のやりとりが伝わるものの、地方の国守を歴任する受領止まりでした。さらに紫式部の父である為時は漢学者として有名ですが、越前守、越後守を歴任した、中流貴族でした。
為時には兄がいました。藤原為頼です。紫式部の伯父にあたる人物です。為頼も丹波守、摂津守などを歴任した中流貴族でした。為頼も大河ドラマには登場しない人物です。
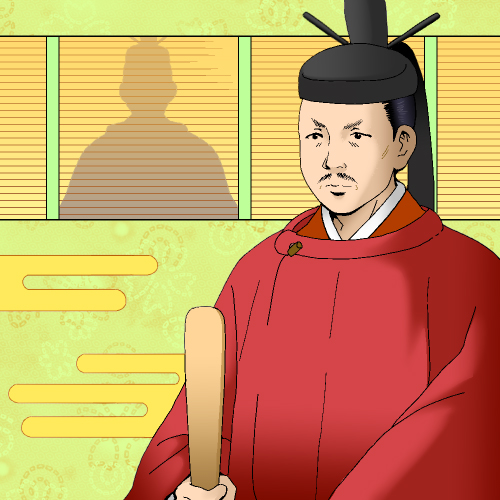
イラスト/関根尚
為頼は花山天皇に皇太子時代から仕え、花山帝即位後に、従四位下に昇進しました。花山帝の在位中は日が当たっていたのですが、わずか在位二年での急な退位で、運命が変転したのは弟の為時と同じでした。
為時が漢籍・漢詩に優れていたのに対して、為頼は和歌に優れていました。『為頼集』という家集を残し、勅撰和歌集『拾遺和歌集』に五首の和歌が採られています。『為頼集』に拠ると、為頼は当時第一級の文人として知られた、村上天皇の第七皇子具平親王に親しく仕え、文芸サロンとなっていた親王の邸宅千種亭に出入りし、具平親王や藤原公任と親しく交流していました。為時も具平親王の家司を勤めたことがあったようで、兄弟で具平親王に仕えていたのです。具平親王については次回取り上げたいと思います。
さて、後に紫式部が父為時に伴われ、越前国に下ったときに、為頼は次のような歌を詠んでいます(『為頼集』)。
越前へくだるに、小袿のたもとに
夏衣薄きたもとを頼むかな祈る心の隠れなければ
(夏衣の薄い袂を頼みにすることだよ。あなたの無事を祈る心は隠れなく、あなたの身に寄り添っているのだから)
詞書には、紫式部に向けて詠まれたとはっきりと書かれていませんが、小袿という女性の着物に歌を付けたというのですから、この小袿は越前に下る姪へのプレゼントで、歌も紫式部へ向けて詠まれたと考えるのが自然でしょう。姪の旅の安全を祈る思いが詠まれていて、この伯父が紫式部を可愛がっていたことが推察されます。『為頼集』には、この歌に続けて、次のような歌が載っています。
人の遠き所へ行く、母に代はりて
人となるほどは命ぞ惜しかりしけふは別れぞ悲しかりける
(あなたが大人になるまでの間は、私は命を惜しく思っていたことだ。しかし今日の別れの悲しさは命を惜しく思っていたことが後悔されるくらいだ)
この歌は詞書にあるように、母に代わって詠んだといいます。この母は、為頼の母だと思われます。為時の母でもあり、紫式部の祖母でありました。曾祖父兼輔とともに醍醐天皇の治世を支えた右大臣藤原定方の娘です。前の歌との関連から、紫式部が越前に下向するにあたり、母(紫式部にとっては祖母)になり代わって、為頼が離別の歌を詠んだと考えることができます。
為頼は紫式部が一人前になるまで命長らえたいと願っていた、老いた母の思いを汲み取って詠んでいます。ここから、この母が母を早く喪った為時の子供たち、孫たちを幼少期から気遣い世話していたと推測することもできそうです。祖母、伯父為頼と、為時の家族の結束が伺えます。
実際、兼輔の旧邸であった賀茂川沿いの堤第(つつみてい。現在の京都市上京区蘆山寺付近)内の別の建物に、伯父為頼も住んでいたとすれば、日頃から頻繁に顔を会わせる伯父さんだったはずで、紫式部を可愛がっていたことも納得がいきます。大河ドラマでいえば、しょっちゅう家にやってくる宣孝の役回りと重なるわけで、だから為頼の存在がカットされたと考察してみても(邪推ですが)面白いかもしれません。為頼には、こんな歌もあります。
孫の、女にて生まれたるを聞きて
后がねもししからずはよき国の若き受領の 妻がねならし
(この孫が将来后候補になったらうれしいけれど、もしそれが無理でも、良い国の若い受領の妻候補になってくれたらなあ)
生まれた孫が女の子だったと聞いて詠んだ歌です。孫が后候補になることは難しくとも、収入の多い国の受領ならば、まだ手が届くということでしょうか。それでも、たいていの中流貴族は苦労を重ねたうえで地方の国守となるのであり、若くして受領になるのは少数派で、選ばれた人たちだったのです。「若き受領」というところにも、為頼の願いが感じられるでしょう。実際、姪の紫式部の結婚相手は受領層でしたが、二十歳くらい年長だった宣孝でした。このような歌を詠む為頼は、洒脱にして、愛情深い人物だったのではないでしょうか。
為頼は長徳四年(998)に亡くなりました。ちょうど弟の為時が越前守在任中のころでした。紫式部が宣孝との新婚生活のために京へ戻ってきた時期であったと推測されます。為時・紫式部父子が為頼の死をどのように受け止めたのか、残念ながら伝わっていません。
<参考文献>
福家俊幸『紫式部 女房たちの宮廷生活』(平凡社新書)
筑紫平安文学会『為頼集全釈』(風間書房)






