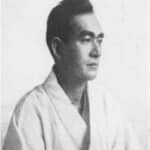非モテを暴かれ婦人公論の編集者を殴打! 文藝春秋の創業者・菊池寛の「恥ずかしすぎるスキャンダル」
炎上とスキャンダルの歴史
ベストセラー作家であり、文藝春秋の創業者でもある菊池寛。当時、菊池の指示のもと「文藝春秋」では作家たちの私生活について書き立てていたが、菊池自身のプライバシーは守られていた。ところが、あるとき中央公論社の「婦人公論」が、菊池がカフェ女給を口説き玉砕する様子を小説で発表。激怒した菊池は、「とんでもない事件」を起こす。
■ベストセラー作家として裕福になった成功者・菊池寛
今日まで続く芥川賞、直木賞の制定者、そして文藝春秋社の創業者にして初代社長を務めたことで知られる菊池寛。『真珠夫人』などに代表されるエンタメ文学の大ベストセラー作家でもあり、世間的には立派な成功者でした。
しかし、彼は夏目漱石の門下生で、「純文学」――この語も菊池が作ったものだとされています――を志していたのですが、その方面では芽が出ず、盟友の芥川龍之介に完敗。「大衆文学」に転じています。菊池は、自身の人気を背景に、通常なら原稿料2円のところ、30円も請求していたそうです。
裕福な菊池の周囲には食えない作家たちが群れを成し、金をたかりました。彼らから「生活第一、芸術第二」の「通俗小説家」だと囁かれているのは百も承知です。菊池は将棋をさしながら、左右のポケットに詰め込んだ紙幣を、貧乏文士たちにくれてやるのが趣味だったとか。将来性のある者には右のポッケから10円札、才能がない者には左のポッケから5円札……と、区別はしていたようですが。
■根深い容姿コンプレックス、そして非モテ

菊池寛
気さくとも、傲慢とも見える彼の態度からは「金で解決できない悩みなどない」という言葉が思い浮かびがちですが、菊池には凄まじいコンプレックスがありました。自身の小太りの容姿に対する劣等感です。
学生時代の菊池にはこれに加えて、極貧というコンプレックスまでありましたが、創作と事業の大成功でそれは克服できました。ところが、思春期からコジらせ続けている容貌コンプレックスの根は深く、卑屈に振る舞うクセがぬけず、女性からはモテないままだったようです。
■カフェ女給への「ガチ恋」を暴かれ…
文藝春秋社の社名にもなった看板雑誌「文藝春秋」では、菊池の指示のもと、有名作家たちの私生活が暴かれ、あることないこと、噂の記事が書きたてられていました。作家が知的アイドルであった時代の話です。
もちろん菊池は文藝春秋社の創始者ですから、彼のプライバシーは守られていました。しかしあるとき、まるで「文藝春秋」の記事を彷彿とするような文体で、銀座のカフェの女給に熱を上げ、「ガチ恋客」となって迷惑がられる菊池自身の不器用な恋愛作法、そして外見上の問題を揶揄したモデル小説『女給』(昭和5年・1930年)が、中央公論社の人気雑誌「婦人公論」に掲載される事件がおきました。
菊池はすぐさま、「事実と小説の内容が異なる!」という反論『僕の見た彼女』を中央公論社に送ります。ところが「婦人公論」はその反論文さえ、読者獲得のエサとして用いるべく、タイトルをキャッチーな『僕と「小夜子」の関係』に書き換えてしまいました。
怒りの炎に油を注がれた菊池はついに編集部に出向き、編集者を殴打。暴行罪で提訴されるという大事件をおこしてしまったのです。
容貌など気にしていないと振る舞うことが男らしさであると信じられていた昭和初期、菊池寛の容貌コンプレックスは、現代の我々が想像する以上につらかったのかもしれません。
画像出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」(https://www.ndl.go.jp/portrait/)主婦の友 20(12)12月號



-150x150.jpg)