諸葛孔明が「東南の風を呼ぶ」シーンは、どのように描かれてきたのか? ~正史から演義、ドラマまで~
ここからはじめる! 三国志入門 第92回
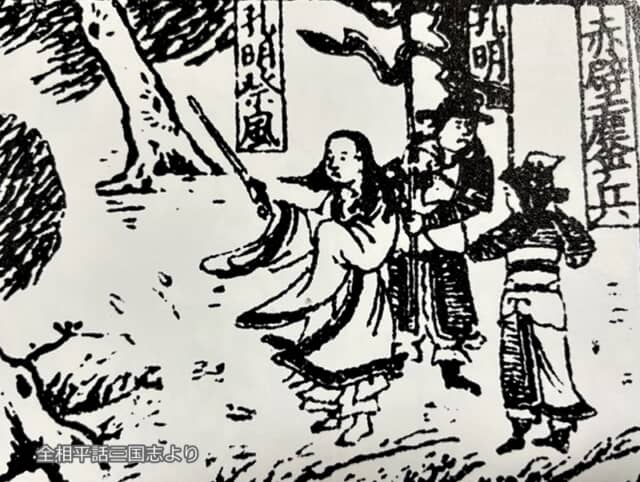
風を呼ぶため祈祷する諸葛亮(孔明)全相平話三国志より
小説『三国志演義』の名場面に「諸葛、風を祭る」がある。赤壁の戦いを前に諸葛亮(孔明)が七星檀で祈り、東南の風を吹かせる場面だ。その風に乗って孫呉の船団が火攻めをしかけ、西北に布陣する曹操軍の船団を猛火で焼き払い勝利する。
3日で10万本の矢を用意して風までも呼ぶ諸葛亮。脅威に感じた周瑜(しゅうゆ)が彼を害そうとするも、諸葛亮はさっさと船で逃げてしまうというのが、その筋書きである。
ここで注目すべきは、どうして東南の風が吹いたのか。ということであろう。じつは原典『三国志演義』で、そのタネあかしはされない。本当に奇術で風を呼んだか、あるいは偶然に風が起こったと解釈するしかなく、周瑜が恐れをいだくのも当然といえば当然とも思える。
■正史では、どう描かれているか
そもそも、諸葛亮を鬼才にする作り話だから・・・と言ってしまえば元も子もないが、正史ではどうなっているのか。まず『三国志』周瑜伝の本文には「時風盛猛」、つまり折からの強風で火が勢いを増したと記載され、引用史料の『江表伝』に「時東南風急」(ちょうど東南の風が激しく吹いていた)の一文が出てくる。風は自然に吹いていた。孫権軍が好日を見計らって火攻めをしかけたと解釈できる。
もちろん諸葛亮が祈祷したなどとは書いていない。「諸葛亮伝」では、彼が使者に立って孫権を説得、劉備との同盟を実現させ、重要な働きを見せたことが記される。その時点で役目を十分に果たしているわけで、なにも彼が風まで呼ぶ必要はないのだ。
では諸葛亮が単なる外交官の役目を離れ、同盟先の江東で八面六臂の活躍をする筋書きは、どのように形成されたのか。それは「演義」の原型とされる『三国志平話』にも、既にあらわれている。
■使者をぶった切る「過激派」の孔明
「平話」において、諸葛亮は周瑜から計略を訊ねられると、皆が手のひらに「火」の字を書くなか、自分だけは「風」と書いたうえで「戦い当日に東南の風を吹かせてみせる」と豪語する。そして「演義」同様に、黄蓋(こうがい)が火攻めをしかけるタイミングで祈祷をはじめ、見事に呪術の力で東南の風を吹かせる。
ここでも、なぜ風向きが変わったのかというタネあかしはない。代わりに兄の諸葛瑾(しょかつきん)が周瑜に対して「弟は天地の機微に通じている」と話すだけだ。
ちなみに「平話」に登場する諸葛亮は、かなりの過激派。劉備の使者として孫権に会いに来たとき、そこへ孫権に降伏をすすめにやってきた曹操の使者に出くわす。すると「孫権が降伏してしまえば、わが主君の命運も尽きよう!」と、いきなり剣を抜くや使者を斬り殺すのだ。みなが唖然とするなか、魯粛のとりなしもあり、強引に同盟を成立させる。このあたりの展開は「演義」と少し違っていて面白い。
■日本版三国志によるタネあかし
『三国志演義』は確かに偉大な小説だが、諸葛亮を超人的に描き過ぎるきらいがある。奇術で風を呼ぶシーンなどは、荒唐無稽の作り話だと子どもが読んでも思えるぐらいだし、孔明ファンでもドン引きするほど周瑜のようなライバルが貶められている。
吉川英治『三国志』は、そうした原典の怪しげな描写を避けている。隆中(りゅうちゅう)に隠棲していた諸葛亮が、朝夕の風を測って暮らし、天体観測に長けていることを前もって語らせている。これを主な原作とする横山光輝『三国志』も「孔明は気象観測から毎年11月に2~3日だけ東南の風が吹くことを知っていた」という解説を入れる。
それはそれで、地元にいながら風が吹くのを知らなかった孫権軍の連中が間抜けにも読めてくる。しかし、物語の展開を変えない程度にリアリティを織り込んだタネあかしといえた。
もともと、中国でも諸葛亮が風を吹かすカラクリが様々に語り継がれていたようだ。
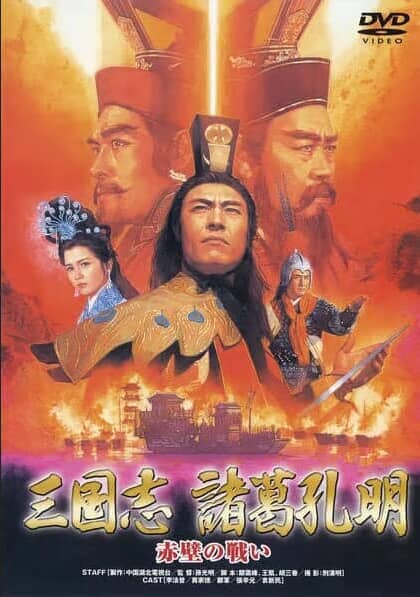
「三国志 諸葛孔明」(赤壁の戦い)DVD3巻のうちの第2巻
その好例が1985年に中国で制作されたドラマ『三国志 諸葛孔明』(原題『諸葛亮』李法曾主演)だ。東南の風を望む諸葛亮が、江東に住む漁師と出会い「わたしゃ当年八十八、冬の東南風(たつみ)にゃ滅多に逢わぬ」という俗謡を聞かされて、ピンとくるシーンがある。
本場の民間伝承が、微妙なかたちで織り込まれていた。かなり古いが映画『レッドクリフ』などより良くまとまった作品ゆえ、機会あればご覧いただきたい。






