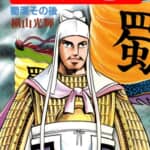劉備と孫権は、なぜ土地を分け合ったのか。関羽と魯粛の会談「単刀会」は、どちらが得した?
ここからはじめる! 三国志入門 第88回
単刀会(たんとうかい)をご存じだろうか? 単刀赴会とも呼ばれるもので、西暦215年に行われた、魯粛(ろしゅく)と関羽(かんう)による会見である。益州を得た劉備(蜀)と、孫権(呉)との間で、荊州南部(荊南)の帰属をめぐる紛争に決着をつけようというものであった。

「単刀会」に臨む関羽と魯粛。三国志演義連環画より
「荊州問題」は、さかのぼること数年前に端を発していた。
赤壁大戦後に孫権軍の周瑜(しゅうゆ)が、劉備軍の加勢も得て南郡(江陵)を1年かけて攻略し、曹仁(そうじん)を荊北(襄陽)へと追い払った。ここから、両軍の紛争につながる駆け引きが始まる。重ねて注意したいのは、ここで出てくる「荊州」とは南郡や江夏郡を中心とした荊州南部(荊南)のこと。襄陽を中心とする北部(荊北)は依然、曹操軍が領していた。
やや複雑なので、正史『三国志』(先主伝・孫権伝・周瑜伝・魯粛伝)や引用文の『江表伝』などから時系列を追っていきたい。
▼209年(赤壁の戦いの1年後)、孫権が周瑜を南郡(江陵)太守に、程普を江夏郡の太守に任命。周瑜は共闘の礼として劉備に公安県を預けた(駐屯させたとも受け取れる)。
同年、劉備は周瑜の手勢を借りて荊南の四郡(武陵・長沙・桂陽・零陵)を攻略。のち孫権と会見、これら四郡の借り受けたとされる。
周瑜や呂範は「劉備を呉に引き留めるべき」と言ったが、孫権は魯粛の言葉に従い、劉備を帰して先の四郡を守らせた。さらに孫権は妹(孫夫人)を劉備に嫁がせて手なずけようした。
▼210年、周瑜が益州(蜀)遠征の準備中に急逝。後任の魯粛は、孫権の許可を得て劉備に江陵を預けた。以後、江陵には関羽が駐在。魯粛は陸口(長沙)に駐在した。孫権は蜀遠征を劉備に提案するが、劉備は自分が蜀を欲しいため、言葉巧みに中止させる。
▼211年、劉備は関羽を江陵に残し、自軍のみで益州(蜀)に遠征。孫権は立腹したが、魯粛がそれをなだめた(その間、孫権は曹操軍と合肥・濡須口で交戦。荊州を魯粛・劉備に任せざるを得なかった)。3年後(214)、劉備は劉璋を降伏させ、蜀を攻略。
▼215年、孫権は諸葛瑾を使者として「荊南を返せ」と劉備に要求。「涼州を取ってから」との劉備の返答に業を煮やし、呂蒙に兵2万を預けて三郡(長沙・零陵・桂陽)を奪い取らせた。(215年・地図参照)
▼これに対し、関羽が3万の兵で益陽に進軍し、魯粛や甘寧と対峙していた。孫権も陸口まで出張って劉備にプレッシャーをかける。劉備も公安まで戻り、両軍にらみ合いになった。
あわや孫権・劉備は一触即発。赤壁以来つづけてきた同盟崩壊の危機となる。そこで魯粛は関羽に「会見」を申し入れた。それまで同様、あくまで劉備側とは「交渉」で状況を打開しようとしたのである。

左/215年(単刀会以前)と、右/219年(劉備漢中攻略直前)の地図。この4年間、荊州南部の分割統治がキープされていた。作成:ミヤイン(参考『中国歴史地図集 第二冊 秦・西漢・東漢時期』中国地図出版社 他)
■単刀会は結局、なんら成果がなかった?
「肅邀羽相見、各駐兵馬百歩上、但請將軍單刀倶會。」(魯粛伝)
魯粛と関羽は、それぞれ短刀一本を帯び、側近数名ずつを連れただけで顔を合わせた。なんとも緊張感に満ちた会見である。
小説『三国志演義』では、この単刀会の場面は、ただ関羽の豪胆さを示すために描かれる。魯粛は関羽を宴席に招き、三郡返還に応じない場合は潜ませていた兵で殺そうと企むのだが、いざ関羽が来るとビビッて実行できない。関羽は「蜀の問題は俺にはわからん。国家の大事はこんな宴席で決めるべきではない」と投げやり。
そして宴もたけなわになると、魯粛の腕をつかんで岸辺まで引っ張っていって、甘寧らが手出しできないうちにその場から舟に乗って立ち去ってしまう。
正史(魯粛伝)では、もちろん様相が異なる。魯粛が「わが方が荊州を貸与したのは、劉備殿が基盤も持たなかったからだ。いま蜀を得たのに劉備殿は土地を返そうとしない」と、切々と関羽に説き、関羽はそれにただ耳を傾けているだけだったらしい。「演義」とは異なり、魯粛が豪胆な人であったことがわかるが、ただこの会見だけで劉備側が完全譲歩したのかはわからない。
結果的に、この領土問題を一応解決したのは曹操の漢中侵攻だった。知らせを受け、慌てた劉備は孫権に譲歩案を申し入れた。湘江(湘水)を大まかな分岐点として荊南を分割。東側の江夏郡および長沙・桂陽を孫権が、西側の南郡(江陵)および武陵・零陵を劉備が領有するというかたちで話がまとまったのである。
特筆すべきは、一度は奪われた三郡のうち零陵が劉備領に返されたところで、劉備にとって大きなメリットといえた。
■孫権は本当に劉備に土地を貸していた?
そもそも「荊州を貸与した」というのは、主に孫権陣営の見方で、劉備陣営にその気はなかったのかもしれない。ただ赤壁の戦いと、その後の四郡支配は孫権の助力あってこそという負い目はあったのだろう。
いっぽうで、孫権陣営も元々は荊州を支配していたわけではなかったし、統治を任せておいて「返還」を要求するというのも、今ひとつ説得力に欠けた。こうした互いの正当性と利害関係のせめぎあいの結果が、荊南分割だったのであろう。そう考えると「単刀会」は、単に関羽がやり込められただけではなかったのかもしれず「演義」の描写も嘘ばかりではないのかもしれない。
孫権としては、おそらく荊南四郡すべてを手のうちに収めたかったところだろうが、妥協せざるを得なかった。ただ少なくとも荊州の半分の権益は確保できたから良しとしたのだろう。ただし、当初は支配下に置いて曹操の備えにしようと考えていた劉備が、ここまで大きくなるとは想定外で、最大の誤算だったに相違ない。
その後の展開について、魯粛はどう考えていたのだろうか。それも2年後の217年、彼が46歳で急逝し、わからなくなった。いずれにせよ彼の死で劉備との和平政策が破綻の兆しを見せたのは確かであった。
後任として陸口に赴任した呂蒙は周瑜にも似た武断派であったが、最初のうちは関羽と親密に接し、孫権側からも関羽を懐柔しようと縁談が持ち込まれた。だが、それを関羽が断ったことで両陣営の関係は悪化の一途をたどってゆく。
「土地とは、ただ徳のある者に帰すのみで、なんら所有が定まっているものではない」(夫、土地者、惟德所在耳。何常之有)
魯粛伝にある、この言葉は単刀会の座にあった一人の人物が発したものだ。おそらく関羽の側近と思われ「演義」では周倉の役割となっている。両陣営の利害がぶつかり合う場ゆえに、魯粛と関羽の一喝で声の主は「場違い」として退席させられるのみで、なんら意味を持たない。
しかし、誰もがハッとする一言であったからこそ、この言葉は正史に書き留められたように思える。「土地」とは本来、誰のものなのか・・・。権力者が弱者をねじ伏せ、奪う行為は正当化されて良いのか。徳あるものが所有者なら誰もが納得するのか。膨大な『三国志』の短い一節ながら、現代人も無関係ではいられない問題である。