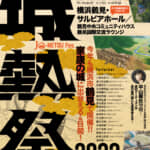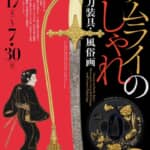『「歴史人」読者とめぐる播磨・但馬の旅』が12月2日に開催!
編集部注目の歴史イベント
2023年12月2日(土)、兵庫県播磨・但馬地方の歴史と食を堪能する日帰りバスツアー『「歴史人」読者とめぐる播磨・但馬の旅』が開催される。 独特の城の縄張り・構造、防御を有した山城が多数残る播磨と、都会では見られない美しい自然と、風情ある街並みや鉱山跡が共存する但馬。長い歴史のなかで育まれた文化を1日たっぷり満喫できるプランとなっている。
■戦国の城跡や食、酒、さまざまな名物を堪能できる地播磨・但馬へ!

「歴史人」読者とめぐる播磨・但馬旅
『歴史人』2023年11月号掲載の特別編集記事「山城めぐりで知る播磨・但馬の魅力」では、兵庫県播磨・但馬地域に残る山城とその歴史をたっぷりご紹介した。そんな播磨・但馬に残る史跡や食、酒を楽しめる日帰りバスツアーが開催される。『歴史人』でその魅力の一端を知った方もそうでない方も、悠久の歴史と独特の文化に浸れること請け合い。貴重な体験ができる上に美味しいお酒とお食事もついて10,000円というリーズナブルな価格も魅力的!
特別な1日を過ごせる播磨・但馬の歴史紀行、ぜひご参加ください!
<開催概要>
■日帰り/姫路出発
■コース№.2100
■旅行日/:2023年12月2日(土)
■募集人員:40名
■最少催行人員:28名
■出発場所:JR姫路駅南バスターミナル
■出発時間:8時30分 ※10分前にご集合ください
■旅行代金:おひとり10,000円(大小同額)
■食事:出石皿そば ※食物アレルギーのある方はご注意ください
【行程】
姫路(8:30出発)
置塩城跡(所要30分:城下より解説) ※山城へは登山いたしません
神崎酒造(所要30分:見学・試飲)
出石城下町めぐり(所要120分:出石そばの昼食とガイドと一緒にまち歩き)
明延鉱山跡(所要60分:ガイドと一緒に明延鉱山探検坑道見学)
神子畑選鉱場跡(所要20分:東洋一の選鉱場跡を見学)
道の駅フレッシュあさご(所要20分:お買物)
姫路(18:30頃)
■播磨・但馬の戦国を物語る山城の歴史
播磨・但馬地方の城と言えば、姫路城(姫路市)や竹田城(朝来市)が有名だが、この地方にはそれ以外にも中世のロマンを感じさせる山城、城郭郡が数多く存在する。中世において播磨の守護は赤松一族が長く任じられてきたが、赤松満祐(みつすけ)の時に室町幕府6代将軍・足利義教(よしのり)を殺害し、幕府軍によって討伐されて没落する。
しかし、応仁の乱の最中に、赤松政則(まさのり)によって、旧領国の支配権が回復された。赤松氏を再興した政則によって築城されたのが、今回の旅で訪れる置塩城(おしおじょう)だ。標高360mの城山には石垣が残り、往時を偲ぶことができる。置塩城は、後期赤松氏(政則、義村、晴政、義祐、則房)の本城となった。東西約600m、南北約400mに広がる「播磨最大の山城」とも評されている。
■殿様の「そば愛」が生んだ名物をはじめとする3大名物

この旅では出石皿そばを食べることができる。その成り立ちの歴史的背景に思いを馳せながら味わいたい。
美しい自然に囲まれた播磨・但馬には、地域の歴史とともに味わいたい「食」の名物がある。そのひとつが「出石皿そば」だ。その歴史は江戸時代中期にまで遡る。宝永3年(1706)、信州上田藩から仙石政明(せんごくまさあきら)が出石藩主としてやってきた。その国替えの際、仙石政明は、信州そばの職人を出石に連れてきたという。それが「出石皿そば」のルーツだとされている。「出石皿そば」は、殿様のノスタルジア(郷愁)が生んだ歴史と伝統ある但馬名物なのだ。旅の昼食には、この出石皿そばを味わえる。
また、但馬の特産として忘れられないのが、古い歴史がある「岩津ねぎ」だ。江戸時代、生野には幕府の代官所が置かれていた。その代官所の役人が、京から「九条ねぎ」の種を生野に持ち帰って、朝来市周辺の農家で栽培させた。生野には有名な生野銀山があり、銀山で働く坑夫の冬の栄養源として重宝されたという。
3つ目は「但馬牛」。日本が世界に誇る絶品グルメのひとつとなっている。国内のブランド牛の多くが但馬牛の改良によって生まれたものであり、但馬牛こそ和牛のルーツなのだ。一時は品種改良などの動きもあったが、最終的に元々の良さが認められて、純潔の但馬牛へと戻っていった。その後、美方郡の山深い里にいた牛たちを中心に新たな血統づくりを始め、そのなかで生まれたのが「和牛の偉大なる父」と言われる雄牛「田尻号」である。田尻号は13年間で1500頭近い資質抜群の子牛を残し、現在の但馬牛のすべてがその遺伝子を継ぐことに。さらに、その子孫たちが全国で種雄牛として使われたことから、現在黒毛和牛の99.9%が田尻号の遺伝子を受け継いでいるといわれる。
■播磨の歴史と風土が育む伝統の「酒」
日本酒発祥の地は、播磨国(兵庫県南西部)という説がある。奈良時代初期に編纂された「播磨国風土記」には、日本酒にまつわる逸話が記載されている。それによると「(伊和)大神の食事(米)が腐り、カビが生えた。そこで酒を醸造し、大神に献上した」とある。つまり、カビが生えた米で酒を造ったということだろう。古くから播磨で酒の醸造が行われていたことを感じさせる。
播磨には「酒米の代表」「酒米の王者」とも称され、全国一の生産量を誇る「山田錦」がある。山間の清水に恵まれ、気候も酒造に適していることから、播磨には老舗の蔵元がいくつもあるのだ。この旅で訪ねるのは、そんな数ある蔵元のうちのひとつで、日本酒「真名井の鶴」で知られる神崎酒造である。神崎酒造は日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」沿いに建っており、創業100年を超える長い歴史がある。

風情ある街並みの一角に佇む神崎酒造。今回、ここでは蔵の見学と試飲を楽しむことができる。
旅行企画実施:
神姫観光株式会社 〒670-0913姫路市西駅前町1番地
〈官公庁長官登録旅行業第2108号〉
詳細やお申込みはホームページから
https://www.limonbus.com/tabitabi/hyogo/topic/2724/