“性病男子”が大流行!? 外国人が驚いた「近世日本の貞操観念」とは
炎上とスキャンダルの歴史
■「性病大国」だった日本
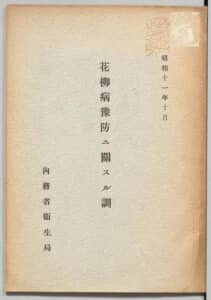
『花柳病豫防ニ關スル調』内務省衞生局
近年、「何々男子」という呼称の増加に歯止めが聞かず、主に流通しているものだけでも100以上にのぼると聞いたことがあります。こうした表現はすでに明治時代にはありましたが、当時、もっとも有名な「何々男子」とは、「花柳病男子」だったかもしれません。
花柳病男子とはなんなのでしょうか。平たくいうと、「性病持ち」という意味です。江戸時代から日本は外国人が驚愕するような「性病大国」でしたが、性病の温床となっていたのは、芸者や遊女といったプロの女性たちでした。
彼女たちと、その職場をまとめて花柳界と呼んだのですが、そこに好んで出入りする殿方と、彼の恋人や妻である女性を中心に、性病の輪が広がっていったのです。
■「性病男子の結婚禁止」を訴えた平塚らいてう
日本における元祖フェミニストの平塚らいてうは、女性たちの身を守るため、「花柳病男子」の結婚を法律で禁じる結婚制限法を作ってほしいと訴えました(雑紙『改造』大正10年2月号)。当時の医療技術では、梅毒、淋病などほとんどの性病を治癒させることは不可能だったからです。まぁ、ほとんどの性病が投薬で治療可能になった現代でも、配偶者が性病だと発覚すれば、夫婦関係に大きな波風が立つものかもしれませんが。
興味深いことに、明治時代以前においては、花柳病になったところで、まったく深刻視されることはなかったようです。おおらかだったのか、諦めてしまっていたのか……。「皮癬(ひせん)七度、梅毒(かさ)三度」ということわざまであり、「人間生きていたら、皮膚病には7回なって、梅毒には3回くらいなるもんだよ」といった意味でした。明治時代以前、梅毒は「かさ」などと呼ばれましたが、「かさ」とは「かさぶた」の「かさ」で、そういう皮膚疾患を伴う症状が出る時期があるがゆえです。
「皮癬」もただの皮膚病ではなく、ある種の性病を指しているかもしれません。実は欧米においても、梅毒と、その他の性病が別の病気であると判明したのは19世紀も半ばになってからのことでしたから……。
■「性行為=恥」の普及で性病が「恥ずかしい病気」に
日本では梅毒になっても仕方ないとあきらめる時代が長く続いていましたが、明治時代になると、外国から輸入された「性行為は恥ずかしい行為」という認識が強くなり、性病は「性行為で感染する恥ずかしい病気」として忌み嫌われるようになります。
抗生物質が発明されておらず、もしくは普及しておらず、性病に効くまともな薬がなかった当時、どのような治療が施されていたのでしょうか。欧米では水銀を皮膚に直接塗りたくって、包帯で巻き、暖炉の前にいると、異臭を放ちながら皮膚が溶けて、梅毒の「かさ」もなくなるという恐ろしい水銀治療が存在しましたが、つらいだけで効果はなかったようです。
日本でも、文明開化の後も花柳病は治療不可能だったので、予防策が講じられたわけですが、「サーナー」なる商品名で女性器内部に塗る殺菌クリームは普及したものの、効果はうすいものでした。陸軍衛生課が作製した「星秘膏」も兵士たちの必須薬とされましたが、内容は抗真菌薬にすぎず、カンジダ系の病気なら効いたかもしれないという程度。梅毒患者については、ペニシリンが普及した昭和期に激減したようです。
現代日本では梅毒の再流行が問題になっていますが、「花柳病男子」もしくは「花柳病女子」という言葉が復活しないように祈るばかりです。
画像…『花柳病豫防ニ關スル調』,内務省衞生局,1936.10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1880950 (参照 2023-08-01)


-150x150.jpg)



