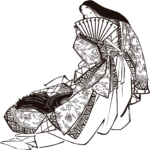「悪妻」と貶められた夏目漱石の妻・鏡子 じつは愛情深い良妻賢母だった?
日本史あやしい話
家事が苦手で朝寝坊。おまけに思ったことをズバズバ言いのける夏目漱石の妻・鏡子。明治時代の凝り固まった視点から鑑みれば、悪妻と呼ばれても仕方のないことだったのかもしれない。しかし、よくよく彼女の動向を探ってみれば、とてもそんな風には思い難い姿を垣間見ることができるのだ。彼女は本当に、悪妻だったのだろうか?
■「鏡子悪妻説」を吹聴したのは?
夏目漱石の妻・鏡子といえば、世間では悪妻ということで話が通っているらしい。お嬢様育ちで、家事が苦手。おまけに朝寝坊とあって、漱石に朝食を食べさせずに出勤させることもしばしばであったという。性格も豪快で、思ったことをズケズケと言い、苦言を呈する漱石とやり合うことも少なくなかったとか。となれば、貞淑な女性像を理想とする明治時代の凝り固まった視点からみれば、悪妻と陰口を叩かれても仕方のないことだったのかもしれない。
では、その悪妻説を世に知らしめるのに手を貸したのはだれか?まずは、その辺りから振り返ってみることにしたい。筆頭は、漱石の門下生で、人物伝『夏目漱石』を著した小宮豊隆あたりだろうか。何と、「漱石の肝癪の根源は、鏡子の無理解と無反省と無神経から来ている」とまで記しているから、実に辛辣である。漱石が神経を患ったのは鏡子のせいだと、あからさまに言うのだ。
また、文豪・永井荷風も自著『断腸亭日記』の中で、『漱石の思い出』を著して生前の漱石の言動を公表した鏡子に苦言を呈している。「未亡人の身として今更之を公表するとは何たる心得違いだ」と手厳しい。書として公表すること自体「女の道ならずや」とまで言うほどだから、よほど腹に据えかねたのだろう。これら著名人たちの言を皮切りとして、鏡子の悪妻説が世に広まっていったと見るべきだろう。
それにしても、である。彼女は本当に、悪妻とまでさげすまされるような女性だったのだろうか?筆者は、そうは思わない。漱石とその家族にまつわる人物伝を読み進めていけばいくほど、彼女が悪妻だったとは、とても信じられなくなってしまうからだ。
■鏡子は、むしろ良妻賢母
ズバリ、敢えて言う。鏡子の悪妻論は、現代人の感覚に照らしてみる限り、言語道断であると。もちろん、当時の倫理観からすれば、朝寝坊で家事もズボラ。さらに言いたいことをズケズケと言うなど、理想の女性像からはほど遠かったかもしれないが、もしも彼女が今日の令和の世に生きた人であったとすればどうか?おそらく、そんな女性はごまんといるに違いない。それをおしなべて悪妻に仕立ててしまっては、日本中悪妻だらけになってしまうからである。
筆者はむしろ、夫・漱石側にこそ問題があったとみなしている。例えば、新婚早々、漱石が新婦・鏡子に対し、「俺は学者で勉強をしなければならないのだから、おまえになんかかまっていられない。それは承知していてもらいたい」と言ったというから、開いた口が塞がらない。もしもあなたが新婚早々、新郎からこんな風に切り出されたとしたら、黙って頷くことができるだろうか? 漱石は、それを言ってのけた。言ったばかりか、それを実行したのである。
結婚3年目にしてロンドンへと単身勉学のために旅立っているが、その間、彼は家庭を省みることがなかった。鏡子の著書『漱石の思い出』によれば、日本に残された家族の生活費は乏しく、「着物なんぞ今まであったものはほとんど着破って満足なものはないといっていいくらいでした」というほどであった。
ちなみに、もう一度、漱石が神経を患ったことに話を戻してみよう。前述したように、その一因が彼女が慣れぬ結婚生活からヒステリーを起こし、それがために漱石を神経症に追い込んだとみなされることに対して、ひと言反論しておきたい。そもそも、漱石が神経症に陥ったのは、漱石がロンドンへと旅立ってからのことだからである。「英国人全体が自分を莫迦にしている」と思い込んだ漱石が、「毎日毎日幾日でも部屋に閉じこもったなりで、真っ暗な中で、悲観して泣いている」という状態が続いて、関係者をヒヤヒヤさせたものであった。帰国後もしばしば精神を病んで、むやみと癇癪を起こしたというのが実情であった。その症状があまりにも強烈だったからか、漱石の長女・筆子や次女・恒子は、父に対して恐怖心を抱き続けたとか。
また、結婚から2年後の事である。彼女自身が結婚生活に疲れてヒステリーを起こし、挙句、投身自殺を図ったこともあったとも。幸いにもこの時は漁師に助けられて一命を取り留めたが、彼女こそ、無理解な夫に悩まされた被害者だったというべきだろう。
漱石自身も、生涯に渡って神経症や胃潰瘍、リュウマチ、糖尿病などに悩まされ続けて苦境に立たされたことは理解できるが、妻子に当たり散らすなど、あるまじき行為である。言わずもがな、それが彼女をとてつもなく苦しめたはずだ。
それにもかかわらず、彼女は、今は亡き夫を思い起こして、「病気の時は仕方がない」と夫を庇ったばかりか、「病気が起きない時のあの人ほど良い人はいない」とまで言い切っている。そんな女性を本当に悪妻呼ばわりして良いものだろうか。否、むしろ、良妻あるいは賢婦だったと言うべきだろう。その上、「いろんな男の人をみてきたけど、あたしゃお父様が一番いいねぇ」とまで言うから、頭が下がるばかり。何とも健気な妻ではないか。
そんな懐の深い妻を大事にしてこなかった漱石。彼女のことを慮ると、ついついひと言言いたくなってしまうのだ。「漱石先生、いけませんぞな、もし」と。

夏目漱石/国立国会図書館蔵