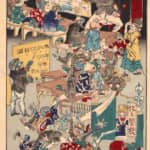頼んでないのに… 外国人が困惑する日本の「有料お通し」文化はいつから始まったのか? インバウンド客への「スマートな説明方法」とは
世界の中の日本人・海外の反応
日本の飲食店で、注文していないのに提供される有料の「お通し」。インバウンド客には馴染みがなく、トラブルになるケースも増えている。海外にはあまりない風習だが、いつから「お通し」は出されるようになったのか? また、外国人に対してはどのように説明すればよいのだろうか。
■英語圏では「強制的な前菜」と呼ばれている日本のお通し

イメージ
訪日外国人の増加に伴い、大きな経済効果がもたらされている一方で、オーバーツーリズムやマナー違反、文化の違いによるさまざまなトラブルについても連日のように報じられている。その中でもよく目につくのが、居酒屋など酒の席での「お通し」トラブルだ。
頼んでいない一品なのに、どうしてその分も支払わなければならないのか。客へのサービスというなら、無料にするのが筋のはず。このため英語圏では、「Compulsory Appetizers(強制的な前菜)」と呼ばれもしている。言われてみればたしかに、日本人でも割り切れない気持ちを抱いている人が少なくないのではないか。
■伝票に別記される「有料お通し」は昭和期から
注文していないのに出てくる料理といえば、中国では茹で落花生や生のニンニク、韓国ではキムチやナムルなど10以上の小皿料理が出てくることがあるが(しかもお代わり無制限)、それらは伝票上に別記されずサービス扱いなので、トラブルのもとになることはない。日本の「お通し」が問題視されるのは、注文した品と並列して、伝票上に単価と個数まで明記されることにも拠るのだろう。
日本における「お通し」の起源は古く、江戸時代の旅宿や料亭に由来するとも言われる。しかし、それらはこみこみの支払いになるから、現在の「お通し」に直接つながるものではない。
伝票に金額まで明示される有料の「お通し」の歴史は意外と新しく、昭和10年(1935年)頃に始まるという。「お通し」という呼び名は、客からの最初の注文を厨房に通し、それを出すまでのつなぎ役であることに由来する。
■新宿ゴールデン街では外国人用に「お通しなし」の対応も
早くからインバウンド客の占める割合が高かったせいか、新宿のゴールデン街ではコロナ前から「お通し」をなくし、代わりにすべてのドリンク代が少し高めの外国人用メニューを用意する店が多かった。
アイルランド人のように夕食を済ませてから飲みに繰り出すタイプの外国人観光客には、「お通し」なしメニューの方が受け入れやすく、穏当な解決策と言えるだろう。
■「カバーチャージ」などと説明するのがスマート
お通しを日本式のチップと説明する手もあるが、世界にはチップの習慣のない国や撤廃した国もあるから、より広範な外国人を納得させるには、「テーブルチャージ」(座席の利用料)とするのが最善かもしれない。
なお、英語圏では「table charge」という言葉はあまり使われず、一般的には「cover charge」が使われるようなので、「カバーチャージ」のほうが適切とも考えられる。いずれにしても、外国人観光客にとって馴染みのある用語で説明しておくのが、よりスマートな解決策となるのではないか。