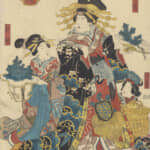大河ドラマ『べらぼう』体で稼ぐ遊女から金を搾り取る「身揚がり」と「紋日」とは?
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第4回「雛形若菜の甘い罠」では、遊女たちの錦絵を制作するにあたって、主人から遊女が入銀を迫られる場面があった。当時の吉原遊郭では、主人たちからさらに金をとられるシステムがあったことについて、取り上げる。
■借金を背負って体を売る遊女たちからさらに金をとる仕組み
そもそも遊郭にいる遊女たちのほとんどは、貧しさゆえに幼い頃に身売りされたり、半ば攫われるように連れて来られたりしていた。人身売買がご法度だったために、建前として女衒(げぜん)を介して妓楼から前借金をして、娘を奉公に出すという体裁がとられた。もちろん本人の意思によるものではなく、家族の借金のかたとして望まぬ奉公を強いられていたことは言うまでもなく、いくら取り繕っても「人身売買」であることに変わりはない。
ゆえに遊女たちは店に対して莫大な借金を抱え、それを返済し続けるというのが基本構図なのである。さらに、行事などでの贈答品代や自分の身の回りの世話をする禿(かむろ)や自分についている新造にかかる金も、遊女が支払わなければならなかった。
毎晩彼女たちが稼ぐ金は、当然懐には入らない。その上、吉原遊郭には「紋日」というシステムがあった。季節ごとの年中行事や、吉原ならではのイベントごとがある日のことで、この日は遊女の揚げ代はもちろん、台の物(食事)などの値段も倍増。さらに、祝儀もはずまなければならないため、客にとっては普段の何倍もの出費になる日だった。
この紋日に客がつかなかった(ノルマを達成できなかった)遊女は、なんとその日の“架空の稼ぎ”を自腹で店に払わなければならなかったという。ただでさえ年季明けまでに返しきれるかわからない借金に上乗せされるのだ。だからこそ、遊女たちは紋日に馴染みの旦那に来てもらえるよう、恋文を出すなどしてねだった。多い時期で年に80日以上も設けられていたといい、遊女にとっても客にとっても頭を悩ませる制度だった。
ほかにも遊女が自腹を切らなければならない場面があった。遊女たちは過酷な労働環境で、年中ほとんど休みもなく働かされていた。多少体調が悪かろうが、客をとることを強いられたのである。どうしても休みたいときの手段が「身揚がり」で、自分でその日の稼ぎ分の金を主人に払えば休日がもらえた。とはいえ、そもそも返済しきれないほどの借金を抱えている遊女たちである。そんなに軽々しく休日を得ることはできなかったのだ。

イメージ/イラストAC
<参考>
安藤優一郎『江戸文化から見る 男娼と男色の歴史』(カンゼン)