「黄表紙本」を世に広めた鱗形屋孫兵衛
蔦重をめぐる人物とキーワード②
1月12日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第2回「嗚呼(ああ)御江戸」では、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)が吉原の案内本『吉原細見』を製作するため奔走する様子が描かれた。その序文を依頼すべく蔦重が探し回った流行作家は、意外にも蔦重がすでに出会っていた人物だった。
■平賀源内の心を動かした蔦重と花の井

『三升増鱗祖』に描かれた鱗形屋の店先の様子(国立国会図書館蔵)。作画は恋川春町。屋号は鶴鱗堂あるいは鶴林堂だったとされる。寛政期に板株を譲り渡した西村屋与八の二代目は、鱗形屋孫兵衛の次男だったらしい。
吉原に客を呼び集め、河岸を立ち直らせようとする蔦重(つたじゅう)が思いついたのは、吉原の案内本『吉原細見』の序に、話題となっていた才人・平賀源内(ひらがげんない/安田顕)の文章を掲載することだった。源内が老中・田沼意次(たぬまおきつぐ/渡辺謙)と知己であると知った蔦重は、以前、田沼と出会うきっかけになった貧家銭内(ひんかぜにない)という人物を訪ねる。
源内と引き合わせる条件で銭内を吉原に連れていき、接待を行なっていると、銭内と源内が同一人物であることが判明する。さっそく蔦重は序文を依頼したが、源内は吉原の魅力を見出すことができず、乗り気でない様子だ。
その席へ、花魁(おいらん)・花の井(小芝風花)が現れる。花の井は源内の亡くなった想い人である二代目瀬川菊之丞(せがわきくのじょう)になりきり、源内を接待する妙案を思いついたのだった。
花の井の舞う姿に在りし日の菊之丞を見た源内は、蔦重の求める序文を書き上げて花の井に渡し、吉原を後にした。
それからまもなくして、さまざまな思いのこもった『吉原細見』が完成し、蔦重は喜びの声をあげるのだった。
- 1
- 2


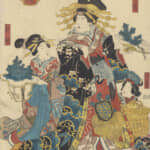
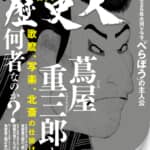
_電子透かしあり-150x150.jpg)

