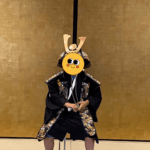古代人のくらしから学ぶSDGsな暮らし!キーワードは「自然を敬い、感謝し、愛でる心」
古代のきほん
古代の人々の暮らしをみていくと、私たちが持続可能な暮らしをしていくうえのでたくさんのヒントが隠されています。人間の暮らしの原点を一緒に調査してみよう!
日本の縄文時代は今から1万6千年前から始まり、1万3千年以上続いたとされます。
人々は、森で動物を狩り、植物を集め、海や川で魚や貝などを獲り、自然界に頼った暮らしを続けてきました。
その間に、ヨーロッパでは小麦などの農耕が始まりました。
エジプトではピラミッドが築かれ、社会の仕組みが大きく変革しました。
外国に比べて、日本列島は遅れていたのかなあ……?
原始的で貧相な生活を続けていたのかなあ……?
そんな風に、思われるかもしません。
でも、決してそうとは言い切れないですよ。
日本の縄文時代にも、驚くべき知恵があったんです。
今回はその知恵をご紹介していきますね!
〇最古級の土器は発展のカギ!

大平山元遺跡 最古の土器に伴う石器群(出典:JOMON ARCHIVES)
青森県の大平山元遺跡から出土した土器は、それまで日本で見つかっていたものよりも4000年も古く、およそ1万6000年前に作られたとわかりました。
これは世界でも最古級の土器なんです!
「でも土器って、ただの食器でしょ?」
そんな風に思っていたとしたら、大きな誤解ですよ。
土器こそ縄文文化の原点であり、発展のカギなんです。
〇土器は食の発展に必須アイテム!

土器の登場は、食文化の発展へ!(出典:JOMON ARCHIVES)
土器の登場は、縄文人の食生活を一変させました。食べ物を煮たり加熱したりできるようになったからです。
今まで生で食べることができなかった植物を、食べることができるようになり、食料の幅がぐんと広がりました。
縄文時代の前、旧石器時代の人々のメインの食料は肉でしたが、縄文人は多くの植物を食べていたようです。
縄文人の人骨調査からも、この事実が裏付けられました。
このように、土器の登場によって縄文人の食生活が変わり、食糧事情が安定しました。
そうした食糧事情の変化は、さらなる変化をもたらします。
動物を求めて移動する必要が減ったので、縄文時代の中期以降には大型の村がつくられて、定住するようになっていったのです。
〇縄文人から学ぶ!SDGsな暮らし方

三内丸山遺跡(出典:Sanmaru Search)
移動が多い生活は、足腰の弱った老人には、過酷な生活だったでしょう。
けれど定住できるようになって、老人も安心して暮らせるようになりました。
老人は、人生で得た経験を子どもたちに伝えることができるようになりました。
たとえば、どの季節に何の植物が獲れるか、どうやって動物を獲るか、といった情報です。
こうして豊富な動植物の知識が、ムラの中、次の世代に伝承されていくようになったのです。
でも、いくら知識が増えたからといって、縄文人は手当たり次第に動植物をとっていたわけではありません。
同じ場所に長く住むためには、自然の生態系を破壊しないようにする必要があります。
ですから、縄文人たちは一つのものにかたよらないように、多くの種類の動植物を利用していました。
そうやって豊かな自然環境のなかで、自然と共存してきたのです。
持続可能な社会、究極にSDGsな生活といえますね。
定住するための工夫として、半栽培と言われる放置的な栽培もしていたようです。
青森県の三内丸山遺跡では、広い範囲にわたって森林を開発して、数世代にわたって、クリだけの林を管理していました。
クリは食料のためだけでなく、建材のためでもあったようです。
この遺跡では、高さが15メートル以上もある大型の掘立柱建物の跡が見つかりました。
その大型の掘立柱に使われていたのは、直径1メートル前後のクリ材です。
この建物が何のためのものだったのかは分かっていませんが、神への祈りを捧げる、神殿だったのではないか、という人もいます。
【今日のまとめ】
古来から日本人は、自然の中に神々がいると考えてきました。
私たちも自然を敬い、感謝し、愛でる心を持っていますが、この精神は縄文の頃から受け継がれてきたものかもしれませんね。
今、自然破壊、環境汚染が地球規模での問題になっています。
気候変動を引き起こし、食糧危機などの問題を引き起こすからです。
今を生きる私たちは、自然に対する感謝の心を思い出し、縄文人の知恵に学ぶ必要があるのかもしれませんね。
◎参考文献
「三内丸山の世界」山川出版社 岡田康博、小山修三編
「縄文学の世界」朝日新聞社 小林達雄
「縄文人の文化力」新書館 小林達雄
「縄文人になる!」 山と渓谷社 関根秀樹
「かわいい古代」カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、光村推古書院書籍編集部譽田亜紀子