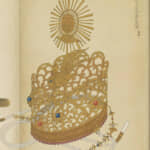女性・女系天皇はなぜ実現しないのか?─皇位継承問題の歴史を追う─
天皇と皇室の日本史
ニュースなどで度々注目を集めながら、いまだに実現していない女性天皇、女系天皇についての歴史を改めて探る。

皇居の二重橋
■候補者不足への対応が急務に! 背景となる「皇位継承問題」
現在の皇室典範(こうしつてんぱん)では、第一条に「皇位 は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と規定されており、女性が天皇に即位することはできない。しかし日本では、古代には推古・皇極(斉明)・持統・元明・元正・孝謙(称徳)、近世には明正・後桜町の10代8人の女性天皇が存在した。ではなぜ、現在の日本では女性天皇が存在することができないのだろうか。
この疑問を解く鍵の時期は二つある。第一は、明治22年(1889)に大日本帝国憲法とともに裁定された皇室典範(旧皇室典範)のなかで、「大日本国皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」(第一条)と定められた時である。これによって、女性天皇や女系天皇が排除された。
第二は、昭和20年(1945)のアジア・太平洋戦争敗戦後、皇室典範が改正された時である。ここでも、明治期と同様に、女性天皇や女系天皇が生まれる可能性は排除された。
ところで、「男系・女系」「男子・女子」についてよく混同するので、その点を見ておきたい。
まず、比較的わかりやすい「男子・女子」から見ておこう。生物学的にその人が男性か女性か、それが「男子」「女子」になる。現在の徳仁天皇は「男性天皇」、前述した推古天皇などは「女性天皇」と分類される。
現在の皇室典範の規定によれば、性別がどちらであるのかが天皇になれるかどうかを決めるのであり、男性ならば天皇になる資格が存在し、女性ではそれがないことになる。つまり、現在の日本では女性は天皇にはなれず、女性天皇は誕生しない。
一方、「男系・女系」はその人自身の性別は関係ない。天皇家の血を男性(父方)から受け継いだのか、女性(母方)から受け継いだのかで分類される。父親が天皇(もしくは皇族)であればその子は「男系」となり、母親が皇族であればその子は「女系」となる。
現在の皇室典範の規定によれば、男系のみが天皇になる資格があり、女系は認められていない。皇室典範は第十二条で「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と定めており、女性皇族は結婚すると基本的には皇族を離れ、民間人となる。そこで子どもが生まれても、民間人でもあり、しかもその子は女系となるため、男性であっても皇位の継承権は存在しない。女系天皇も誕生しないのである。
以上のような「男系・女系」「男子・女子」を組み合わせると、①男系男子、②男系女子、③女系男子、④女系女子という4つのパターンが存在することがわかる。このうち、現在の皇室典範は①のパターンでしか皇位継承を認めていない。
現在の皇室で言えば、秋篠宮家の文仁親王・悠仁親王などは男系男子、天皇の長女である愛子内親王や秋篠宮家の佳子内親王などは男系女子になり、男性皇族のみが皇位継承の対象者となる。たとえば、愛子内親王が結婚した場合、基本的には皇室から離れ、民間人となる。
しかも、愛子内親王から男性の子どもが産まれた場合はその子は女系男子、女性の子どもが生まれた場合はその子は女系女子となるため、現行の規定では天皇にはなることができない。もし、②を認めてその子も皇位継承権を持つと規定した場合、自動的に③か④のパターンとなり、男系から女系になる。つまり、一度女性天皇を認めると、女系になる可能性は大きい。
皇室も生まれる子どもの数が減少し、しかも偶然的に女性のみが続く時期があった。これが皇位継承問題を生じさせる要因となったのである。
監修・文/河西秀哉