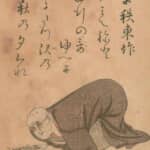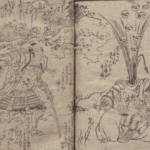甚大な被害を与えた天明の大噴火が伝える教訓
蔦重をめぐる人物とキーワード㉕
■江戸時代最大の天災による被害と教訓
1783年7月8日、群馬・長野県境の浅間山が大爆発した。「天明の浅間焼け」と呼ばれるこの噴火は、噴出量では過去の噴火に及ばないものの、被害規模と社会的影響において、江戸時代最大級の火山災害として歴史に刻まれている。
浅間山は標高2,568メートルの活火山で、古くから噴火を繰り返してきた。最古の記録は685年まで遡り、1108年の天仁噴火は噴出量約1.2立方キロメートルと浅間山史上最大規模とされる。一方、天明の噴火の噴出量は約0.73立方キロメートルと規模では天仁噴火に劣るが、人的被害は桁違いに大きかった。
噴火は4月に始まり、5月に活発化した。そして7月7日から8日にかけて最大の爆発が起きる。火口から高さ150メートルの噴石が打ち上げられ、直径50センチの火山弾が4キロ先まで飛んだ。総噴出量は約10億トンに達したという。
最も悲惨だったのは、北側斜面を襲った鎌原火砕流だった。研究によれば、時速100キロ以上とされる高温の火砕流は、群馬県嬬恋村の鎌原村を一瞬で呑み込んだという。全93戸が消失し、460人以上が犠牲となった。長野原町の小宿村も全滅するなど、55の村が被災。死者1,624人、流失家屋1,151戸という甚大な被害を記録した。
噴火の影響は関東全域に及んでいる。江戸には約3センチの火山灰が降り積もり、日本橋では人々が懸命に灰の除去作業にあたった。碓氷峠では1.5メートルもの厚さで火山灰が積もり、関東北部の農業に壊滅的な打撃を与えている。
火山灰が太陽光を遮ったことで、すでに続いていた冷害がさらに深刻化。これが「天明の大飢饉(だいききん)」の引き金となった。
東北地方の被害はさらに凄惨を極めた。津軽藩では約13万人(一説には20万人)、八戸藩では人口の3分の1にあたる3万人以上が餓死や病死、あるいは一家が離散した。生き延びるために人肉を食べるという地獄絵図も各地で報告されている。
飢饉と物価高騰は、各地で社会不安を引き起こした。特に「世直し一揆」と呼ばれる大規模な農民蜂起が頻発している。
群馬県では、安中藩領の農民が救済を求めて蜂起し、質屋や米穀商を襲撃。10月2日に始まった一揆は約270人から3,000人規模にまで拡大し、中山道の横川関所を突破して信濃国に乱入した。各地の米穀商を打ち壊しながら上田領まで進んだという。
蘭学者の杉田玄白(すぎたげんぱく)は、この一連の騒動を「真の一揆の萌(きざ)し」と評している。まさに社会変革の胎動を予感させる出来事だった。
幕府は熊本藩に復興支援を命じるなど対策に追われたが、全滅した村々の復興は困難を極めた。この危機的状況は、時の権力者・田沼意次の失脚を早め、松平定信(まつだいらさだのぶ)による寛政の改革へと政治の流れを変えていく。
浅間山は現在も活動を続けており、1911年には日本初の火山観測所が設置された。天明の大噴火は、必ずしも最大規模の噴火でなくても、時代背景や社会状況によって、甚大な被害をもたらすことを示している。
この噴火は単なる自然災害ではなく、その後の日本の社会、経済、政治の方向性を決定づけた歴史の転換点だったといえる。災害の「規模」と「影響」は必ずしも比例しないという教訓を、現代に教えてくれている。
- 1
- 2