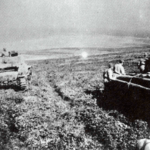石破総理のベトナム・フィリピン訪問の狙いは? 日本は「自由で開かれたインド太平洋」の旗手となれるか?
石破茂総理が2025年4月27日から30日にかけてベトナムおよびフィリピンを訪問した背景には、明確な地政学的戦略が存在する。この訪問は、中国の海洋進出への対抗、米国の関税措置による国際経済の混乱への対応、そして東南アジア諸国連合(ASEAN)との連携強化を通じて「自由で開かれたインド太平洋」の実現を目指す日本の姿勢を反映している。以下、地政学的観点からその狙いを解説する。
まず、最大の狙いは、中国の南シナ海および東シナ海における覇権主義的行動への牽制である。ベトナムおよびフィリピンは、南シナ海で中国と領有権を巡る対立を抱え、中国船舶との衝突が頻発している。石破総理は両国首脳と会談し、安全保障分野の協力を強化することで合意した。具体的には、ベトナムに対し、防衛装備品供与を可能にする「政府安全保障能力強化支援(OSA)」の対象国指定を伝え、フィリピンとは軍事情報包括保護協定(GSOMIA)および物品役務相互提供協定(ACSA)の交渉開始で合意した。これらの取り組みは、力による現状変更の試みを抑止し、法の支配に基づく国際秩序を維持する日本の決意を示すものである。訪問直前に中国の習近平国家主席がベトナムを訪れていたこともあり、日本は中国の影響力拡大を抑えるため、東南アジアでの存在感を高める必要があった。
次に、米国のトランプ政権による関税措置への対応も重要な狙いである。米国はベトナムに46%、フィリピンに17%の高い相互関税を課す方針を打ち出し、両国経済および日本企業の活動に影響が及ぶ懸念が生じている。石破総理は現地の日系企業と意見交換を行い、関税措置の影響を把握しつつ、多角的自由貿易体制の重要性を両国首脳と確認した。これは、米中間の関税戦争がASEAN諸国の「米国離れ」を誘発し、中国への接近を促すリスクを軽減するための動きである。日本は、経済面でのASEANとの連携を深めることで、地域の安定と繁栄を支えるリーダーシップを発揮しようとしている。
さらに、ASEANを世界経済の成長センターと位置づけ、長期的なパートナーシップを強化する狙いもある。ベトナムおよびフィリピンは人口約1億人、平均年齢が若く、経済成長率が高い国である。石破総理はベトナムで半導体人材育成および日越大学でのプログラム開始を表明し、フィリピンではインフラおよび防災分野での協力を約束した。これらは、両国の産業高度化および経済強靱性を高め、日本との経済的結びつきを強める戦略である。また、2025年がベトナム戦争終結50年、太平洋戦争終結80年の節目であることを踏まえ、比島戦没者の碑への献花や残留日系人との面会を通じて、歴史的和解および人的交流も重視した。
地政学的には、米国が東南アジアへの関与を弱める中、日本が「自由で開かれたインド太平洋」の旗手としてASEANとの協力を深める意義は大きい。石破総理の訪問は、中国の影響力拡大を牽制し、経済および安全保障の両面で日本が信頼されるパートナーであることを示すものであった。今後、ASEANとの継続的な関係強化が、日本の地政学的地位をさらに高める鍵となるであろう。

イメージ/イラストAC