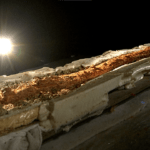トランプ関税はトランプ政権一過性のものか? アメリカの「一国主義と保護主義」のこれから
トランプ政権下で導入された関税政策は、米国の通商政策における大きな転換点として注目される。中国や欧州連合(EU)などに対する高関税は、国内産業の保護と貿易赤字の是正を目的としたものだ。しかし、これがトランプ政権特有の現象なのか、それとも米国が今後長期的に進む保護主義の兆候なのかを判断するには、歴史的文脈と現在の経済・政治環境を踏まえた分析が必要である。
■米国の歴史における一国主義と保護主義
米国は建国以来、国際的な関与と孤立主義の間で揺れ動いてきた。特に経済政策においては、保護主義が長期間にわたり主流であった。独立戦争後の18世紀末から19世紀にかけて、米国は新興国として国内産業を育成する必要に迫られ、関税を活用して外国製品との競争を制限した。たとえば、1816年の関税法は、製造業保護を目的に輸入品に高税率を課した。この時期、英国からの輸入品に対する関税は、国内の繊維や鉄鋼産業を守るための重要なツールだった。
19世紀後半から20世紀初頭にかけて、米国経済は急成長を遂げ、工業化が進んだが、保護主義の姿勢は変わらなかった。1890年のマッキンリー関税法は、平均関税率を約50%に引き上げ、国内製造業を強力に支援した。この時代、米国は世界最大の経済大国へと台頭したが、自由貿易よりも国内市場の優先を重視する政策が続いた。第一次世界大戦後、1920年代の孤立主義的な高関税政策は、1930年のスムート・ホーリー関税法で頂点に達し、平均関税率は60%近くに達した。しかし、この過度な保護主義は世界的な貿易縮小を招き、大恐慌を悪化させる要因となった。
第二次世界大戦後、米国は自由貿易を推進する国際秩序の構築に舵を切った。1947年の関税及び貿易に関する一般協定(GATT)や、後の世界貿易機関(WTO)の設立は、米国が主導した多国間貿易体制の象徴である。冷戦期には、自由貿易が西側陣営の結束を強化する手段とみなされ、関税は大幅に引き下げられた。しかし、1980年代以降、日本や中国の経済的台頭に伴い、米国内では再び保護主義の声が高まった。レーガン政権下での日本車に対する輸入制限や、クリントン政権期の北米自由貿易協定(NAFTA)への批判は、その一例である。
このように、米国の歴史は自由貿易と保護主義のサイクルで特徴づけられる。一国主義と保護主義は、経済的・政治的状況に応じて繰り返し浮上してきたのだ。
■トランプ関税の背景と特徴
トランプ政権(2017~2021年、及び2025年以降の想定される再登板)の関税政策は、こうした歴史的文脈の中で理解する必要がある。2018年に導入された中国に対する関税(最大25%)や、鉄鋼・アルミニウムへのグローバル関税(それぞれ25%、10%)は、「アメリカ・ファースト」を掲げるトランプの経済ナショナリズムの象徴である。これらの政策は、国内製造業の復活、雇用の創出、対中貿易赤字の削減を目標とした。
トランプ関税の特徴は、従来の保護主義とは異なる点にある。第一に、関税の対象が戦略的に選ばれ、特定の国(特に中国)や産業に焦点を当てていることだ。これは、経済的競争に加え、技術覇権や国家安全保障を意識したものである。第二に、多国間協定よりも二国間交渉を重視し、WTOの枠組みを軽視する姿勢が顕著である。たとえば、NAFTAを改定したUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)は、米国の利益を強く反映したものだ。第三に、関税が政治的ツールとして活用され、国内支持層へのアピールや外交交渉の梃子として機能している点である。
■ 一過性の政策か、長期的な潮流か
トランプ関税が一過性のものか、長期的な米国の方針となるかは、いくつかの要因に依存する。まず、国内政治の動向である。トランプの政策は、グローバル化による経済的不平等や製造業の衰退に不満を抱く労働者階級の支持を得た。2024年の選挙結果や世論調査(具体的なデータは割愛するが、保護主義への支持は根強い)からも、こうした声が一時的なものではないことが窺える。バイデン政権下でも中国向け関税の一部が維持された事実を考慮すると、保護主義は党派を超えた潮流となりつつある。
次に、国際環境の変化である。中国の経済的・軍事的台頭や、サプライチェーンの脆弱性が露呈したコロナ禍を経て、米国は経済安全保障を重視するようになった。半導体や医薬品などの戦略物資の国内生産を強化する動きは、関税を含む保護主義的政策と連動する。これらはトランプ個人を超えた構造的要因であり、短期間で解消される可能性は低い。
しかし、長期的な保護主義にはリスクも伴う。高関税は物価上昇や貿易相手国の報復を招き、米国の輸出産業や消費者に悪影響を及ぼす。国際的なサプライチェーンの分断は、効率性やイノベーションを損なう可能性がある。さらに、WTOや同盟国との関係悪化は、米国の国際的影響力を低下させる懸念がある。
トランプ関税は、米国の歴史に深く根ざす一国主義と保護主義の再現であると同時に、現代の地政学的・経済的課題に応じた新しい形の政策である。トランプ政権の一過性の現象というよりは、国内の政治的需要や国際環境の変化を背景に、今後も一定程度継続する可能性が高い。ただし、その形態や強度は、経済効果や国際社会の反応によって変動するだろう。米国が自由貿易と保護主義の間でどのようなバランスを取るかは、21世紀の国際経済秩序を左右する重要な課題である。

写真AC



サンタモニカ-150x150.jpg)