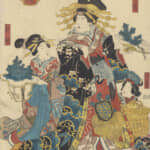約9800万円で「トップ花魁・瀬川」を身請けした「盲目の大富豪」の“悲惨すぎる末路” NHK「べらぼう」の修羅場はどうなる?
炎上とスキャンダルの歴史
蔦屋重三郎/蔦重(横浜流星)が主役のNHK大河ドラマ『べらぼう』。蔦重と両思いのヒロイン・瀬川(小芝風花)は盲人の高利貸し・鳥山検校(市原隼人)により身請けされたのだが、3月16日放送の第11話では、検校がふたりの関係に勘づき静かに嫉妬する様が描かれ、不穏な空気にSNSでは「ゾクっとした」「修羅場!」といった声があがった。そんな検校だが、史実ではどれほどの金持ちだったのだろうか? また、検校は幕府に処罰される経緯とはどのようなものだったのだろうか?
■盲人金持ちが「太客(ふときゃく)」として吉原を支えていた
西暦18世紀なかばの宝暦年間(1751~1764)以降、吉原の上客だったのが「当道座(とうどうざ)」といわれる盲人組合のトップにあたる「検校(けんぎょう)」や「別当(べっとう)」といった位階の人々でした。
『べらぼう』のドラマでは描かれていないようですが、江戸時代の吉原をはじめ、全国の遊里には「紋日(もんぴ)」と呼ばれるイベントデーが結構な頻度で開催されていました。
遊女は暦の上の年中行事にかこつけた扮装をせねばならず、そういう衣装代はすべて彼女たちの負担でした。いかに「紋日」を切り抜けるかが腕の見せ所だったのです。しかも「紋日」は遊女たちの揚げ代が通常営業日の何倍にも跳ね上がるので、太客の中の太客しか吉原では遊べなくなるのですね。
そういう「紋日」の吉原に押しかけたのが「当道座」の盲人金貸したちで、彼らは馴染みの遊女たちの衣装代も軽く負担してやっていました。おそるべき経済力です。
■相場の3倍の「約1億円」で、トップ花魁・5代目瀬川を身請け
幕府が盲人たちに高利貸しを行う権利を認めたのは、6代将軍・家宣(いえのぶ)の治世でした。これ以降、検校以下、別当、勾当(こうとう)といった身分の盲人たちが法定利息よりも高いレートで金貸しを行うようになったのです。
安永4年(1775年)、松葉屋の瀬川を身請けした鳥山検校は、高利貸しとして大成功を収めていた一人でした。鳥山検校が瀬川を身請けするのに費やした額はなんと1400両。高くても500両もあれば足りるとされる身請け相場の約3倍です。
江戸時代中期の1両=現代の7万円くらいとして考えると、1400両=現在の9800万円となります。当時の1両=1石で、1石とは、庶民の成人男性の1年間の食費(正確には1年分の米)に相当するんですね。つまり瀬川を身請けしたければ、1400年分の食費を差し出す覚悟が必要だったのです。
一方、鳥山検校の総資産は1万5000両=現在の10億円程度。つまり瀬川10人分。瀬川1人を身請けしたところで、びくともしない経済力を誇っていたのでした。
それでも、鳥山検校は「当道座」の金貸しの中ではナンバー2だったというのですから驚きます。ナンバー1の名古屋検校に至っては10万3000両もの蓄財をしていたそうですよ。つまり100億円以上を蓄えていたのですね。ほかに松岡検校、松浦検校、相馬検校といった者たちがそれぞれ1万両程度を所有していたそうです。
■武士への金貸しを幕府が問題視し、全財産を没収
しかし、幕府は「当道座」の盲人金貸したちの派手な金遣いや、あくどい商売内容を問題視するようになっていました。盲人金貸したちの上得意は、物価上昇についていけなくなった高い身分の武士たち。武士の中には安易に高利貸しを利用したことで、夜逃げにまで追い込まれる者もいたのです。
こうして鳥山検校が瀬川を身請けしてから3年後、安永7年(1778年)には名だたる検校たち全員が全財産を没収され、江戸市中から追放される憂き目にあったのでした。ちなみに当時、鳥山検校など盲人金貸しだけでなく、将軍直属の武士でありながらも高利貸の副業をしていた御家人たちも処罰されたそうです。
「驕れる人も久しからず」――『平家物語』の一節ですが、「当道座」には盲目の琵琶法師たちも所属しており、皮肉を感じずにはいられなかったでしょう。鳥山検校没落後の瀬川がどうなったのか、たしかなことはわかりませんが、彼の都落ちには付き合わなかったようですね。

イメージ
※参考文献
稲垣史生 編『三田村鳶魚江戸生活事典』平凡社