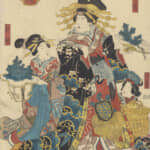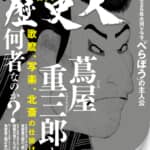「名君」と謳われた徳川吉宗の改革
蔦重をめぐる人物とキーワード④
■称賛と不興が入り混じった大改革
江戸の三大改革として知られる享保の改革、寛政の改革、天保の改革の3つのうち、最初に実施されたのが、江戸幕府8代将軍・徳川吉宗によって行なわれた享保の改革だ。蔦屋重三郎が生まれる前の出来事となる。
吉宗が将軍に就任した1716(享保元)年当時は、幕府の財政が逼迫(ひっぱく)するさなかだった。合戦がなくなったことで武士の収入が大幅に減り、全国で水害などの災害が相次ぐなど、さまざまな要因が絡み合い、幕府の財政は困窮。職人や商人への債務がかさみ、幕臣への俸禄(ほうろく)が滞り、吉宗は就任早々、幕府の財政再建という難題に取り組まざるを得なかったのである。
吉宗が積極的に推進したのが質素倹約だ。前将軍の法要を簡素化するなど豪華な儀式を控えるだけでなく、大名らにも贅沢を禁じた。吉宗自身も自らの暮らしから華美なものを排除し、食事や衣服なども質素なものに改めている。
幕府の歳入が年貢米だったことから、吉宗は諸大名から石高1万石につき百石の米を献上させた。応じた藩は参勤交代での江戸滞在を従来の1年から半年に減じるという待遇を得ることができるという、諸藩の負担軽減と幕府の収入増を狙った一挙両得の政策だ。負担が減ったことにより、実際に経済が活性化した藩もあったようだ。
また、従来の検見法(けみほう)から定免法(じょうめんほう)を採用したのも吉宗の財政政策のひとつ。検見法とは、収穫高に応じて年貢の量を定めるもので、定免法とは、収穫高の多寡にかかわらず一定量の米を納めさせるというものだ。
こうした政策を実施することで幕府の財政は一時的に改善したものの、いくつかの政策は農民の負担が大きく、収穫高の50%を年貢として取り立てられる五公五民や、定免法は実質的な増税となった。その上、凶作の際には深刻な影響を庶民におよぼし、吉宗の治世において、度々一揆や打ちこわしが勃発した。
また、着物の色や素材に制限を設けるなど、庶民の生活の自由も制限している。出版界においても、庶民の間で流行していた男女の性的な情交を描く春画(しゅんが)が、改革により取り締まりの対象となった。これを受けた版元は、表向き出版を差し控えたが、冷めやらない人気の高さを誇った春画は廃止されることなく、地下出版物として流通することとなる。
奢侈(しゃし)を禁じる一方、吉宗は目安箱を設置して庶民の不満や提案を将軍に訴える仕組みを作ったり、目安箱をきっかけに貧しい者でも医療を受けられる無料施設である小石川養生所を設立したり、あるいは教育や学問を奨励したりするなど、庶民目線の政策を取り入れることも忘れてはいなかった。後世に「名君」と謳われた所以といえる。
しかし、1732(享保17)年にイナゴの大量発生による享保の飢饉が発生すると庶民の暮らしはますます厳しさを増し、反発の声が増していく。
享保の改革は幕府財政の一時的な再建を果たすことはできたものの、庶民に多大な犠牲を強いた面も決して見逃すことはできず、評価の分かれる改革といえる。
なお、享保の改革の次に行なわれたのが寛政の改革で、実行したのは吉宗の孫にあたる松平定信(まつだいらさだのぶ)だ。定信の手掛ける改革は、同時代に活躍する蔦重らの出版活動に、大きな影響をおよぼすことになる。
- 1
- 2